海外旅行というと、有名スポットをひたすら巡るイメージ。
「せっかくだから…」「もう来られないかもしれないから…」
なんて考えると、どうしてもコスパやタイパに意識が行ってしまうものです。
そんな旅も悪くはないですが、ちょっと立ち止まって考えてみました。
最近はYouTubeなどのプラットフォームのおかげで、有名な観光地であれば観たいときに好きなだけ観られる時代。
であれば、観るべきものは他にあるのかもしれない。
予定を詰めすぎず、ローカルの店で買い物して、現地の人の生活をちょっとだけ真似てみる。そんな「暮らすような旅」が、思いのほか心地よくておもしろかったり、不便だったり、ちょっと腹立たしかったり。観光っぽくない時間のなかに、意外と豊かな発見があることにようやく気付くことができました。
今回は、そんな「観光スポットに行かない海外旅行」の魅力を、いくつかの旅先での体験を交えながら紹介してみようと思います。
旅の楽しみ方がちょっと変わってきたかもしれない…そんな人に、読んでもらえたら嬉しいです。
別に観光地に行かなくてもいいし、観光しなくてもいい
海外旅行はスタンプラリー?
思えば、どうして海外旅行に出ると観光地に行かないといけないような感覚に陥るのでしょうか。
時間が限られているから?もう二度と来られないかもしれないから?それとも、誰かに自慢したいから?
人によっては全てかもしれないし、全く別の動機があるかもしれません。
何となく背後にありそうなのが、「これだけ時間とお金を使うんだから…」というサンクコストバイアスのような感情。背後には「これだけ時間とお金を使うんだから…」という、いわばサンクコスト・バイアス的な感情が潜んでいるのかもしれません。
特に日本では、働いていると休みが取りづらかったり、取れても短かったりしますし…お土産文化や休日でも業務連絡を取るような習慣もまだまだ残っていますから、何も得ないで帰れない、という心情になるのも仕方ない側面があります。
そう考えると、楽しむための旅行で疲れ果てるという現象は「旅の楽しみ方」のみならず「人生観」に直結した問題なのかもしれませんね。
一方で、旅をするために積極的に環境を整えようとする人は、実際にはそれほど多くないのが現実です。つまり、旅の優先順位は決して高くないとも言えそうですし、日常の義務感から完全に解放される時間として割り切れている人が非常に少ないとも考えられそうです。
自分を取り戻すために時間を使うということ
そのような日本人の旅行スタイルの対比としてしばしば取り上げられるのが欧米の休暇文化、とりわけフランスのバカンス文化です。何もしない、消費は身の丈、というある意味消費文化と真っ向から対立するようなスタイルは、日本人の憧れとして映ることも。
旅を日常からの逃避や自分軸の回復のために使いたいのなら、そんな旅のスタイルをちょっと真似してみるのも一興です。
いきなり全く異なるスタイルを取り入れると戸惑いや疲れにつながることもあるので、まずは「できるところから少しずつ」がコツです。自分の生活圏を少しだけ広げてみるというか、自分のパーソナルスペースをちょっとだけ全く違う場所に拡張してみる、みたいな感覚にすると無理なく楽しむことができそうです。
あえて「したいこと」を極限まで削ってみたり、「何をしないか」「どこに行かないか」を決めてみたり。
さらに旅先で小さな「ひとり遊び」に興じてみると、忙しい日常で見失いかけていた自分の興味や関心に気づけたり、心の底からリフレッシュできるかもしれません。
普段通りに過ごす
まずは何といってもこれ。普通の時間に起きて、普通の時間に食事して、普通の時間に寝る。新しい世界を探索するためにリズムを整えるのは、体調管理にも有効です。
ローカルのお店に行く
名の知れた観光地であっても、地元民の生活は割と質素だったり、スーパーマーケットの雰囲気も日本とさほど変わらなかったりする。
たとえばローカルのスーパーや八百屋に行って、地元の人がどんなものを買っているのか眺めてみる。フランスだと、チーズやワインがずらりと並ぶ棚の前で「うわ、安っ」と驚いたり、逆にちょっとした調味料が妙に高くて戸惑ったり。マルシェも素敵だけど、普通の人たちはカルフールとか格安スーパーにも行ったりしていますね。
スイスやシンガポールのような物価が高い国でもその辺は同じ。
高い物は高いですし、安い物は安いです。
シンガポールではよくフードコートに行って、1ドルくらいのアイスコーヒーを飲んで休憩していました。おかげでコピの注文方法は完全にマスターしましたね(最近は忘れつつありますが…)。またシンガポールのスーパーマーケット関係ではフェアプライスによく行きましたし、ドンドンドンキにも行きました。おかげでドン・キホーテの歌は筆者の頭の中ではすっかりドンドンドンキに浸食されてしまっています。笑
他には、ヨーロッパであえてアジア系の食材店に行ってみるのも面白いです。日本で格安の物が現地では高級品になっていることもよくある。1,000円くらい払って冷凍の納豆を食べるのもたまにはいいかも、ね。
公共交通機関を使う
移動手段も、現地の人の視点で考えてみると、少し違って見えてきます。
空港から直行のシャトルバスや観光地行きの特急列車ではなく、地元の人たちが日常的に使っているバスやトラムに乗ってみる。表記が分かりづらかったり、階段しかなかったりと多少の不便はつきもの。しかも、時刻表どおりに来るとは限らない。それでも、そんな「不完全さ」こそが、その街の「日常」を垣間見せてくれたりするのです。
さらに、シンガポールや香港のライトレールのように、中心街から少し離れた地域を走る交通機関に乗ってみると、空気の質が微妙に変わるのがわかる。賑わいから距離を取った、その街の「もうひとつの顔」。
路線図を読んで悩んだり、うっかり反対方向に乗ってしまったり。そんなミスすら、あとで振り返れば旅の思い出のスパイス。
ポイントは、乗り間違えても焦らず、すました顔で景色を眺めること。演技力も旅のうち。
サードプレイスを見つける
旅先で「家でもない、職場でもない」落ち着ける場所—いわゆる「サードプレイス」を見つけると、その土地との距離がぐっと縮まるような気がします。
たとえば静かなカフェ。日本のように長居OKでWi-Fi完備というお店は多くはないけれど、逆に「一杯のエスプレッソで粘る現地の人たち」に混ざって、ただ座ってみる。人の流れや風景をぼんやり眺めたり、自分の旅を振り返ったりする時間は、観光とはまた違った記憶として心に残ります。
観光地のカフェでも、時間帯を選べばまるで個人の書斎のようにくつろげることがあります。たとえば、パリ中心地にある老舗「カフェ・ド・フロール」は、日中は観光客でごった返していても、深夜になると落ち着いた静寂に包まれます。かつてここに通った文豪や哲学者たちに思いを馳せながら、ゆっくりとコーヒーを味わう時間は格別です。
また、街中のカフェもいいですが、空港や船着き場に併設されたカフェのような、ちょっとした非日常空間もおすすめです。イスタンブールのフェリー乗り場にあるカフェでは、行き交う船や人を眺めながら、静かに書き物をしたり考え事をしたりできる、そんな特別な時間を過ごせました。
誰かと会話をするわけでもなく、観光名所を巡るわけでもない。でも、自分だけの時間と空間を持てる。そんな場所が一つでもあると、旅はぐっと深く、豊かなものになります。
暮らすように旅してみる
旅先での滞在スタイルを少し変えてみるだけで、その街との関わり方はがらりと変わります。ホテルではなくアパートやゲストハウスに滞在する、現地の人と同じように暮らしてみる…そんな旅の形は「ひとり遊び」にもピッタリ。
床屋のような地元民向けのインフラにあえてアクセスするのも面白いものです。
同じ場所に可能な限り長く滞在してみる
旅先での滞在日数をできるだけ長く取ってみる。それも、なるべく同じ場所で。
たったそれだけのことですが、旅の質ががらりと変わります。
たとえば2泊3日の旅では、到着・移動・観光・出発と、常に何かをこなしているうちに時間が過ぎていってしまいます。自ずと時間がタイトになるので、どうしても観光地をなぞるような「型にはまった旅行」旅行になりがち。
一方で、1週間、10日、あるいはそれ以上滞在できると、朝から晩まで何かを「しなくてもいい」余白が生まれてきます。
すると次第に、暮らすように旅する、という感覚が芽生えてきます。現地のスーパーで買い物をし、自炊をし、カフェでぼんやりし、散歩の途中でお気に入りの景色に出会う。観光地でなくても、「今日もこの街にいる」という実感が次第に芽生えてきますし、観光地ですら、いつしか「日常の風景」に変わっていたりして。
そうして過ごしていると、ローカルのお店の常連になって、顔を覚えられることもあるかもしれませんね。
予定を詰め込みすぎず、あえて空白の一日を設ける。そんな旅のスタイルを一度試してみると、「旅=忙しい」という固定観念がゆるやかにほどけていくかもしれません。
アパートに滞在してみる
ホテルは便利で快適ですが、どこか「日常から切り離された感覚」が漂います。そこでアパートタイプの宿に滞在すると、自炊をしたりゴミを出したりと、日常の営みが旅に入り込んできます。最初は少し面倒に思えても、それがあるからこそ「ここで暮らしている」という感覚が生まれます。
特に民泊タイプだとリアルに地元民が住んでいる建物や部屋にお邪魔するかたちになるので、没入感がかなり高いです。基本的にホテルのような完璧なサービスは期待できませんし、思わぬトラブルに見舞われて消耗することもありますが、それも後から素敵な旅の思い出になったりします。
筆者の場合、パリでの宿泊はAirbnbなどの民泊サービスを利用することが多いです。狭いキッチンで手早く朝食を作ったり、カフェのカウンターで立ち飲みしたり…。まるでこの町の住人になったかのような気分になりました。
観光地を「見る」旅から、街を「感じる」旅への転換点だったかもしれませんね。
ローカル向けのサービスを利用してみる(床屋や写真店など)
床屋や写真店のような地元民が利用するようなお店にあえて入ってみるのも、非常に良い経験になります。
髪型は写真を見せることもあれば適当に注文して試してみることも。今のところそこまで大きく失敗したことはありませんが、こだわりがある人は厳しいかも…。
これまで実際に住んでいたシンガポールやジュネーヴはもちろん、イスタンブールでも試してみたことがあります。
写真店もフランスのビザ申請のために写真が必要だったため、イスタンブールで試しました。イスタンブールでは観光地で変身写真を撮る人はいても、普通の証明写真を撮る人はあまりいないのではないでしょうか?
こちらも素敵な体験になりましたし、リアルな物価感覚を身に着けるのにも役立ちました。
現地の生活をちょっとだけ真似てみる
たとえば、洗濯機の使い方に戸惑ったり、ゴミの分別ルールに悩んだり。床屋でうまく言葉が通じずにジェスチャーで切り抜けたり。そんなちょっとした苦労や試行錯誤も、振り返ると不思議と旅の記憶を豊かにしています。
またオマーンで語学留学をしていたときは、友人が公務員で常に民族衣装で通勤する姿を見ていたので、それをまねて自前の民族衣装を仕立ててそれを着て通学していました。中東式トイレの使い方も頑張って覚えましたね…(まあそこまでしなくても良いとは思いますが)。
もちろん、何もかも現地仕様にする必要はありません。お米が食べたくなったらアジア系スーパーで寿司米を買って炊いてみたり、気合を入れて春巻きを作ってみたり。そんな「暮らしと旅のハイブリッド」が、無理のない、でも深い旅につながっていく気がします。
ひとり遊びを楽しむ
一人旅は、自由なようで最初は少し不安。でもその静けさの中に、自分と対話するような深い旅の時間が待っています。誰にも気を使わず、誰かの顔色を伺うこともなく、自分のリズムで遊ぶ。そんな「ひとり遊び」の楽しみ方をいくつか紹介してみます。
公共交通機関を遠乗りしてみる
旅先のバスやトラムに終点まで乗ってみる。そんなシンプルな冒険が、思いがけない景色や出会いを運んでくれます。
例えばシンガポールでは、2階建てバスの2階最前列に乗ってぼーっと景色を見るという遊びをよくやっていました。シンガポールは面積が小さく、大抵の場合ショッピングモールが併設されたバスターミナルが終点になっているので、何も考えずに飛び乗るのにうってつけ。車内で飲食はできませんが、エアコンの効いたスペースでのんびり外の風景を眺めるのは非常に贅沢な時間だと思います。
同じことは香港でもしました。こちらも面積がコンパクトで変な場所まで行ってしまう心配はないため、とりあえず乗る、ということができました。2階建てバスから見る高層マンションが立ち並ぶ景色は、シンガポールとはまた違って圧巻でした。アップダウンが多く景色が目まぐるしく変わっていく点も面白かったです。
このように行き先を決めすぎず「この路線、どこに行くんだろう?」という気持ちで乗ってみると、有名観光地の近くをたまたま通ったり、思いがけず生活感あふれる地域に紛れ込んでしまったり…と、まさに「旅している」という実感が湧いてきます。
エリアによっては治安に注意が必要ですが、昼間の時間帯であれば大きな心配は少ないはず。少しだけ勇気を出して乗ってみると、きっと素敵な思い出になるはずです。
ゴールだけを決めて散策してみる
旅先で散策するときに目的地とルートをあらかじめ決める方も多いと思いますが、ここにもひとり遊びの可能性があります。それが、「目的地だけざっくり決めて、ルートはそのときの気分で選ぶ」という楽しみ方です。
イスタンブールなら「とりあえずグランドバザールの東端の出口まで行ってみよう」、マスカットなら「マトラスークの特徴的な天井がある交差点まで」など、終点だけを決めて歩き出してみる。そんな、ゆるやかなゴールだけがある散策は、観光というよりも探検に近い感覚かもしれません。
途中で迷いそうになったり、通りの喧騒に足を止めたり、気まぐれに脇道へ逸れたり。ふと目に留まった雑貨屋に立ち寄ったり、現地の人と軽く挨拶を交わしたりと、偶然の積み重ねが旅を作っていく感覚。
グランドバザールでは、あの迷路のような通路を右へ左へと進むうちに、いつの間にか自分がどこにいるのか分からなくなることも。でも歩いていくうちに「このあたりは絨毯屋が多いな」とか「この通路はレストランが多くて美味しそうなにおいがするな」といった感覚が自然と身についてくる。RPGで言えば、エリアマップが少しずつ明らかになっていく感じでしょうか。それが妙に楽しくて、最後にはちょっとした達成感すら感じられるのです。
ほかにも、スルタンアフメト地区からアジア側のカドゥキョイへ戻るとき、なんとなくフェリーに乗ってみたり、気分でメトロとマルマライを乗り継いでみたり。どちらのルートも観光地とは少し異なる空気が流れていて、街に対する親しみがぐっと増しました。
すべてをGoogleマップで制覇するより、「たどり着けたらラッキー」くらいの気持ちで歩いてみる。そのくらいの余白が、旅にはちょうどよいのかもしれません。
逆に何も考えずに散策してみる
先ほどは「ゴールだけを決める」散策スタイルをご紹介しましたが、逆に、何も考えずにただふらりと歩いてみるのも、実は一番贅沢な過ごし方かもしれません。
オンフルールでは、観光客が集まる旧港を少し離れたところで、あてもなく街を歩いてみました。午後の静かな日差しのなか、遠くに見えるル・アーヴルの工業地帯や、店先で談笑する人々を横目にひたすら散策してみる。観光地の賑わいから少し距離を置くだけで、空気の温度や時間の流れが少し違って感じられるのが不思議です。
誰の目にも触れないような、でも確かにそこにある暮らしの痕跡に触れると、観光では味わえない「土地との関わり」が感じられます。
何となくですが、思考もクリアになってくる感じがします。
屋外に限らず、巨大な美術館なんかもぼーっと歩いてみると意外な発見があったりします。例えばルーヴル美術館のような場所だと、時間が限られている場合はモナリザやミロのヴィーナスのような有名作品をなぞるような行程になりがち。
もし数日間時間を取ることができれば、何となくインスピレーションが働く作品を見つけたり、面白い観点から作品を眺めたりすることができるかもしれません。
そんな出会いが「旅」なのかもしれませんね。
自分だけのルーティーンを作ってみる
旅先で自分だけの日常の決め事を作ってみるのも面白いです。
例えば「午前中はカフェで読書、午後はスーパーで買い出し、夜は軽く自炊」…そんな風に、自分だけのルーティーンを作ると、旅のリズムが整い、安心感が生まれます。筆者の場合、パリでは朝食を近くのカフェで立ち飲みコーヒーとクロワッサンで済ませたり、深夜の作業にはカフェ・ド・フロールに行ったり。
さらにイスタンブールでは、フェリーに乗る前に決まったお店でロクムを買うというルーティーンもありました。買う量は各種類50gずつで4種類くらいで固定。フェリーでチャイを飲みながらこれらを味わう。これが至福の時間でしたね。
さらに、ジュネーヴで過ごしていた頃、筆者はあえて朝マックに行くのが日課でした。無料Wi-Fiに繋いでレポートや課題に取り組んだり、疲れたらブログを書いて気分転換をしたり。「今日も一日が始まる」と思えるようになる。それは観光では得られない、ちょっとした「定点」、つまり旅先でも立ち返ることができる自分だけの場所や時間が生まれる感覚でした。
朝マックに間に合うように起きるので、寝坊防止にもなって良かったです。笑
たとえ短期の滞在でも、自分の一日を設計してみる。そんな小さな習慣が、旅をもっと自分のものにしてくれます。
物語の登場人物になりきってみる
旅先では、ふだんの自分から少し離れて、その街を舞台に「物語の登場人物」になりきってみるのも楽しいものです。
例えばパリでは、映画『アメリ』のように、誰にも気づかれずに街の小さな変化を観察してみたり、ちょっとした親切をしてみたり、クレームブリュレをバリバリ砕いてみたり。いわゆる「アメリごっこ」です。
筆者も実際に、パリ滞在中にアメリごっこをしてみたことがあります。カフェで人間観察をしたり、無表情でメトロに乗ってみたり、クレームブリュレをひたすら砕いてみたり。場所がモンマルトルでなくても、行為自体に意味がなくても良い。その瞬間だけは誰にも束縛されない「物語の主人公」になっているような気分になるのです。
シンガポールで『紺青の拳』ごっこも面白そう。小五郎みたいにロングバーで飲んだくれてみたり、小さなマーライオン像の近くで「ここ、シンガポールかよぉー!」って(小声で)叫んでみたり…。海賊気分でマリーナバラージを訪れて、「ここに船で突っ込むのかよ…」なんて考えてみたりも?笑
実際に作中に登場する場所をめぐる「聖地巡礼」も兼ねれば、一石二鳥の楽しみ方になるかもしれませんね。
ちなみに、なりきるキャラクターは別に何でも良いんです。実在の人物でも架空の人物でも良いし、年齢や性別が違っても良い。パリのような場所ではたくさんの創作物が思いつきますが、別にそれらに縛られる必要もありません。香港で香港人に擬態してみるのだって立派な「ごっこ遊び」です。
旅先でちょっとした「なりきり遊び」をすることで、その土地との距離感が不思議と縮まっていきます。
「その世界に入り込んだ自分」でいる時間を楽しむ。それはもしかすると、「自分の人生を一歩引いて眺めてみる」ということにもつながっているのかもしれません。誰かの人生を一時的に借りてその街を歩いてみると、街の風景も、そこにいる自分も、ちょっとだけ違って見えてくる気がします。
自分と向き合ってみる
「旅に出ると、自分に出会う」なんて言葉がありますが、実際その通りだと思います。
いつもと違う環境、誰の目も気にせずにいられる時間が、自分の内側に自然と目を向けさせてくれる。ここでは、そんな「自分と向き合う旅のヒント」をいくつか紹介します。
カフェでジャーナリングをしてみる
旅先のカフェで、ただぼーっとするのもいいですが、手帳やスマホにふとした思いを書き留めてみるのもおすすめです。
観光地を回ったあと、感じたこと、心が動いたこと、あるいは普段ならスルーしてしまうような些細な感情や気づきを記録しておく。それはまさに、自分との対話です。
個人的なおすすめは、スマホのメモよりもやっぱり紙のノート。筆者はイスタンブールのカフェでよく「書く時間」を取っていました。ときには日記のように感じたことを綴り、ときには今後やりたいことや、解決したい悩みについて自由に書き出す。旅先という非日常だからこそ、逆に「本当の自分」が浮き彫りになるような感覚があります。
気取らず、無理にまとめようとせず、思いつくままに綴ってみる。数年後に見返すと、その土地の空気とともに、自分の心の輪郭が残っていて、ちょっと感動したりもします。
感情がぐちゃぐちゃで筆致が乱れていたり、逆に非常に丁寧に書いていたり…。その日の心模様がそのまま残っているのが、本当に面白いんです。
ノートは何でもいいのですが、持ち運びしやすいよう、丈夫な表紙のノートを選ぶと長く続けやすいです。
旅とは少し違いますが、シンガポール駐在時代に書いた文章を、筆者はいまでも時々見返します。
一瞬だけあの頃に戻ったような感覚に浸ることができるし、今の悩みをふっと手放すきっかけにもなったりします。
日本や他国との違いについて考えてみる
旅の醍醐味のひとつは、やはり「違いに気づくこと」。便利さ、不便さ、心地よさ、違和感。そうした違いは、比較対象となる「自国」があってこそ感じられるものです。
たとえば、フランスでは「不便だけどその分自由」だったり、シンガポールでは「自由だけど、意外とすぐそばに管理体制がある」といったことに気づくかもしれません。訪れる都市が増えてくると、それらの都市同士の比較という視点が芽生えることも。
観光の枠を超えて現地にどっぷり浸かるほど、日本と他国の違いは、生活の機微の中に現れてきます。
そしてその「違い」は、相手をジャッジするためではなく、自分がどんな環境を心地よく思い、何にストレスを感じるのかを知る手がかりに。日本でも海外でも完璧な場所なんて存在しない。そんな当たり前のことが、自分ごとになります。
- なぜ日本の「便利なもの」がこちらでは全く発達していないのか?
- なぜこの国ではこんな不思議な習慣が根付いているのか?
などなど、色々な問いが浮かんでくるはず。
大切なのは、どこかの国の正解探しをするのではなく、「私はどう感じたか」「なぜそう思ったか」を静かに掘り下げてみること。
それは、自分自身の価値観や優先順位に気づくきっかけになります。
拠点にすることを考える
旅先を選ぶときに「ここに住んだらどうなるかな?」という視点を持ってみるのもおすすめ。観光地以外の生活インフラにも意識が向くため、旅の風景がまったく違って見えてくることがあります。
物価はどうか、生活のペースは合うか、自炊はしやすいか、言葉は通じるか…。また、住むことを想定して街を歩くと、カフェやスーパー、美容室、公園など、普段は意識しない「現地でのリアルな暮らし」や「自分がどんな生活をしたいか」にも目が向くようになります。
筆者の場合、海外生活や旅を通じて、「カフェの営業時間」「スーパーマーケットの営業時間や物価」「文化施設の充実度」「外食のしやすさ」といったことが個人的に非常に重要な要素であることが分かってきました。
もちろん、最終的に拠点にしなくても構いません。
「ここに居てもいいかもしれない」と思える場所が少しずつ増えていくことで、自分の中の「帰れる場所」の地図が広がっていく。それだけでも、旅はとても豊かなものになります。
一度限りの旅行にしないと決めてみる
旅は、特別な非日常の出来事。そう思っていると、旅が終わるたびに少し寂しくなったり、「次はいつ行けるだろう」と遠い目をしてしまったりします。祭りの後の寂しさの余韻も素敵ですが、それが尾を引きすぎるのもまた問題。
でも、発想を少し変えてみる。「旅は、一度きりのものじゃない」と決めてしまうのです。
旅がしやすいライフスタイルに寄せてみる
「年に一度だけのご褒美」ではなく、「暮らしの一部として旅を繰り返す」という視点を持ってみる。
もちろん、誰もがフリーランスやノマドになれるわけではありません。でも、頻繁に旅行できる人たちが、必ずしもお金や時間に恵まれているわけではないのも事実です。重要なのは、「旅を暮らしの延長に置けるかどうか」。
たとえば:
- 格安航空券をうまく使って年に数回だけでも短期で出かける
- 海外旅行ではなく「国内の知らない街」で新鮮さを味わう
- 仕事のついでに半日旅を組み込んでみる
- 留学、駐在、ワーケーション、出張などを最大限に活かす
などなど、こうした工夫で、「旅を身近に感じる暮らし」が少しずつ現実のものになっていきます。
筆者自身も、「移動の制限がかからない暮らしの重要性」を感じてから、「自分で選べるキャリア」「旅行できる生き方」を意識するようになりました。「旅ができるかどうか」は、贅沢ではなく、自由の指標のひとつかもしれません。
違う切り口で何度でも楽しむ
「この街にはもう行ったから、次は別の場所へ」。そう思ってしまうのは自然なこと。
でも、同じ場所でも、切り口を変えればまったく別の体験ができるというのもまた事実です。
たとえば、最初は「観光」として訪れた街を、次は「暮らすように」滞在してみる。あるいは、夏に訪れた街を、冬にもう一度歩いてみる。さらに細かく、普段は通らない道を通ってみる。季節や目的が違えば、街の表情もまったく変わります。
初回は美術館や名所を巡った街も、次はローカルの市場や住宅街を歩いてみる。あるいは、「物語の登場人物になりきってみる」ような旅をしてみる。すでに「ごっこ遊び」を楽しんだなら、今度は違う人物になってみるのも一興です。まったく同じ地図の上でも、自分の目線や気分が違えば、新しい発見は無限にあります。
世界は刻一刻とその姿を変化させていきますし、旅をする自分自身ですら常に同じというわけではありません。
一度きりの「達成」を目指す旅ではなく、「まだ知らないこの街の一面に出会いにいく」ような旅。
それは、旅というより関係性に近いのかもしれません。
何度でも行きたい場所がある。
何度行っても飽きない場所がある。
そんな旅が、人生を少しだけ豊かにしてくれます。
まとめ
今回の記事では、「暮らすように旅してみる」をコンセプトとして、筆者がやっていた「ひとり遊び」などを通じて旅の意義を問い直してみました。
観光地を制覇しなくてもいい。絶景を写真に収めなくてもいい。誰かに語れるような「濃い体験」をしなくてもいい。
旅の楽しみ方に、正解もゴールもありません。大切なのは、自分が何を感じ、どんな時間を過ごしたいか。
静かに過ごしてもいい。日常と同じように過ごしてもいい。「ひとり遊び」に本気で興じてみるのも素敵です。そしてもちろん、気が向いたら思いっきり観光してもいい。むしろ、そうやって力を抜いたときにこそ、「本当の自分」がふと現れることもあります。
そして、そんな旅を繰り返すうちに、「行ってみたい街」が「帰ってきたい街」に変化していく。そんな場所が少しずつ積み重なって、世界の見え方も変わっていくかもしれません。
旅とは人生の時間であり、自分の人生との静かな対話。たとえ特別な体験がなくても、自分らしく旅を重ねることで、世界との距離、自分との距離が、近くなったり遠くなったりする。その過程で日常が愛おしく感じる場面もあるかもしれませんし、逆に思い切ってそこから離れるエネルギーが湧くこともあるでしょう。
そんな旅があっても、いいのではないでしょうか。
以上です。
-1.png)
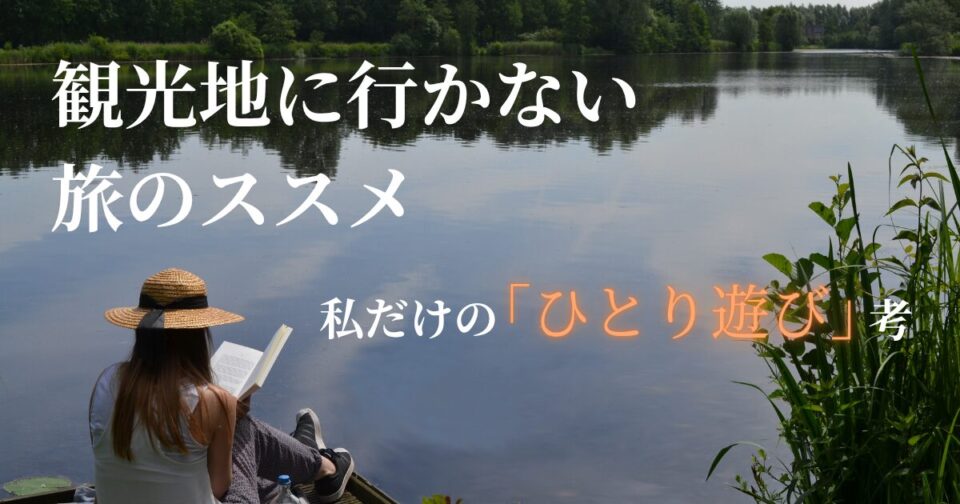
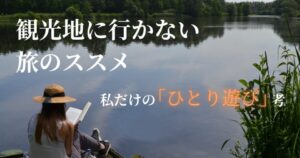
コメント