今や世界中にあるマクドナルドやケンタッキー・フライド・チキン。
そして海外にも意外とあるモスバーガーや吉野家…。
知らない土地で見覚えのある看板を見つけると、ちょっとホッとします。
「よく分からないレストランで高い物を食べるよりはマシ!」と思って入ってみたら…。
同じ看板でも…あれ?なんか違う?という場面に何度も遭遇することに。
色々試してみた結果、いくつかのチェーンは日本で行くのが一番!という結論に至りました(あくまで個人の意見ではありますが)。
今回は、そんな「海外でも見かけるけど、日本でこそ行きたいチェーン店」を実体験ベースで紹介します。
これから長期で海外に行く予定のある方は日本でぜひ食べ収めをしてください(既に海外の方は…頑張ってください)。
モスバーガー

日本発のハンバーガーチェーンの代表格といえばモスバーガー!
現在では東アジアや東南アジア各国に進出しており、現地でも大人気です。
筆者も日本にいたときからモスバーガーが大好き。正直マクドナルドよりも好き。
ちなみにお気に入りはモスチーズバーガーとライスバーガーです。
モスバーガーはシンガポールで行く前にも別の国で何度か行っているので、シンガポールでも期待していましたが、実はシンガポールでモスバーガーに入ったとき、結構ガッカリしたのです。
ライスバーガーは割と日本と同じでしたが、モスチーズバーガーを頼んだときに「ソースが別添え」でビックリしました。日本ではすでに完成形の状態で出てくるのでそのまま食べられますが、別添えになっているとどうしたら良いのか分かりません。
バンズを外してソースをかける?
そのまま脇からソースをかける?
それとも何か別の正解があるの…?
何度か食べましたが、結局正解の食べ方もなぜソースが別添えになっているのかもよく分かりませんでした。
シンガポールのモスバーガーはサラダのクオリティーも日本と比べて微妙でしたね…(なんか野菜のバリエーションが日本と比べてやたら少なかった)。
帰国後にモスチーズバーガーを注文してみましたが、日本ではそのような変更はありませんでしたね。
てっきり日本でも別添えになったと思っていたので、変わっていなくてホッとしました。
なお、シンガポールでもモスバーガーに行ってみたいと思った理由のひとつだったのが台湾のモス。
こちらはかなり現地向けのアレンジ(というかローカライズ?)が効いており、特に朝食限定のオムレツ入りハンバーガーは絶品!ふわっとした卵とモスのバンズが相性抜群で、前に台北に旅行したときは何度か朝食時間帯にモスバーガーに足を運びました。
でもローカライズが進んでいるモスバーガーでも、日本で発売されるオリジナルメニューの方がやっぱり豊富で、さすが本国!といったところです。
モスバーガーはやっぱり日本で食べたいな、と思いました。
ケンタッキー・フライド・チキン

もうすっかり日本のクリスマスには欠かせない存在になったケンタッキー・フライド・チキン、またの名をKFC。
ときどき無性に食べたくなるんですよねー。
もちろん日本発ではありませんが、筆者としては正直日本で食べるべきチェーン店のひとつだと思っています。
スイスでケンタッキーに入ったとき、まず驚いたのはチキンのサイズ。値段が日本よりも大幅に高いことはヨーロッパの物価を考えると仕方ないものの、それにしても小さい。味も微妙で、日本のケンタッキー・フライド・チキンのようなハーブの風味も皆無。
日本だと別のチェーン店との違いが分かりますが、これではただのどこかのフライドチキン…といった印象を受けました。
辛いチキンも試してみましたが、日本売られているレッドホットチキンのようなスパイスの旨味はゼロ。
ただ辛いだけのチキンでした…。
またその後フランスでも利用する機会があったものの、評価は変わらず。正直、ケンタッキーに関しては「ここは海外のほうが良かった!」というポイントを見つけるのが難しいチェーンでした。
そういえばシンガポールも微妙だったな…と思い出しました。もしかしたら海外は全般的に微妙なのかも…。
さらにヨーロッパのケンタッキー・フライド・チキンは客層があまり良くなく、何度か物乞い(子供)にお金をせびられたこともあります。
日本のケンタッキー・フライド・チキンは味も雰囲気も別格だと感じました。
しかも日本のお店は季節ごとのオリジナルメニューが豊富で、全部ちゃんと美味しいのが本当にすごい!
海外のケンタッキー・フライド・チキンはただのファストフード店でした…。
マクドナルド

ファストフードといえばやっぱりマクドナルド!
どこへ行ってもクオリティーが安定しているという安心感がありながら、地域に合わせてしっかりローカライズしているので、旅先で訪れる楽しみもあるチェーン店です。中東エリアではポークを全く使っていないマック・アラビアがあったり、スイスではラクレットバーガーがあったり、試したくなるメニューがいっぱい。
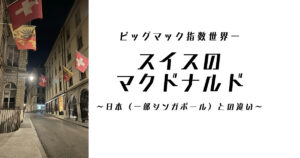
そんな海外でもバリエーション豊かで楽しいマクドナルドですが、「てりやきバーガー」や「チキンタツタ」などの日本オリジナルメニューの存在が当たり前で、さらに「月見バーガー」や「グラタンコロッケバーガー」をはじめとする季節や地域ごとの限定商品を楽しめる環境に慣れていると、海外は全く変化がないと言っても差し支えないほど、海外のマクドナルドは代わり映えがしません(頻繁に変わるのはハッピーセットのおもちゃくらい?)。
シンプルに飽きますし非常に物足りないです。
しかもヨーロッパのマクドナルドは治安がイマイチ。フランスでは当たり前のように物乞いがお金をせびってきます。
またトイレが暗証番号でロックされているため、トイレだけ使いたい人がレシートを見せてくれと言ってくることもあります(勝手にレシートを見られたこともあります)。
ただし、アジア圏になるとローカライズの面白さが見えてきます。
例えばシンガポールのマクドナルドではケチャップやチリソースがポンプ式で取り放題だったり、朝マック時間にはコーヒーと紅茶がお代わり自由だったりと、自由度が高いサービスがあるのです。
こうした工夫は日本にはない魅力で、ちょっと得した気分になりました。
とはいえ総合的には、日本のマクドナルドが一番。
豊富な限定メニューと安定した品質は、日本でしか味わえない価値です。
ちなみに筆者は特に「ベーコンポテトパイ」が好きです。次の復活待ってます。
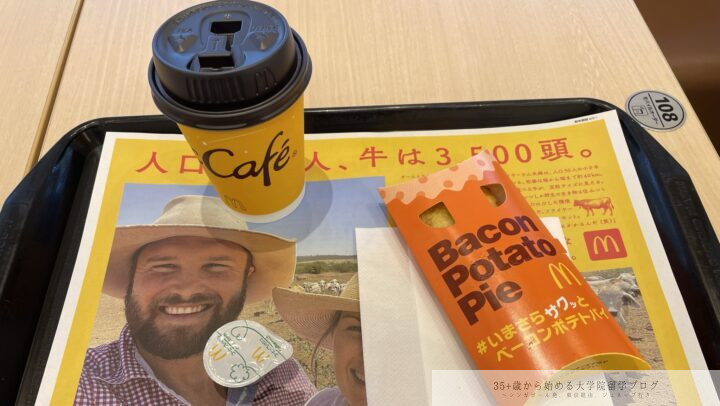
吉野家

シンガポールでも吉野家を見かけて、懐かしさから思わず入店。
ところが日本と比べると、まず価格が高い。日本の1.5倍くらい。牛丼一杯にしてはかなり割高で、気軽に食べられる感じはありません。
そして肝心の味もどこか違っていて「日本のあのシンプルで旨い牛丼」が恋しくなってしまいました。
日本の吉野家は「安い・早い・うまい」の三拍子がそろっていて、忙しいときや小腹を満たしたいときにぴったり。
海外で食べると改めて、その完成度の高さが身に沁みます。
吉野家は日本ではときどき食べていたものの、シンガポールでは結局家で作るようになってしまいました…。
結論、吉野家はやっぱり日本で食べるのがいちばん。
海外での牛丼体験はちょっと残念でしたが、そのおかげで日本の吉野家のありがたみを再確認できました。
一風堂

海外でも大人気の一風堂。
シンガポールとパリで訪問したことがあります。
シンガポールも高いと思いましたが、パリの一風堂は輪をかけて高かったのが印象的です。ラーメン一杯の価格は日本の倍以上、さらに唐揚げが10ユーロという衝撃…。
一番ベーシックなラーメンと唐揚げを頼んだだけで25ユーロくらいかかり、さすがに「これ何食分だろう…?」と考えてしまうレベルでした。日本なら2,000円以内で食べられそうなメニューに5,000円近く払うのは一回で十分かも。
その意味ではシンガポールの一風堂は雰囲気も価格帯も(フランスと比べれば)あまり日本との違いを感じませんでしたが、フランスでは限定らしき特別メニューが色々とあった様子。住んでいたら試したかもしれませんが、短期滞在だとあまり割高なものは試す気になれず。
雰囲気はフランスというかパリらしいシックな感じで、味はちゃんと美味しい。やっぱりフランスにある「なんちゃって」なラーメンとは違います。でも結局海外プレミアムが乗った高めの価格設定が気になってしまい、「高いけれど普通の味」という結論に落ち着きました。
価格・味・ボリュームのバランスがしっかり取れていて気軽に通える「日常のラーメン屋」みたいな一風堂が恋しくなったのを覚えています。
パリなら「ひぐま」とかに行けば15ユーロくらいでセットメニューが食べられることを考えるとやっぱり割高。
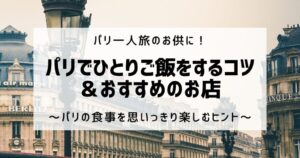
スターバックス・コーヒー
世界中どこにでもあるシアトル発のコーヒーチェーン、スターバックス・コーヒー。
サードプレイスというコンセプトに代表される居心地の良さや人間味のある接客が好評です。
日本でもスタバの接客は他のコーヒー専門店と比較するとかなりフランクな感じですが、海外ではさらにフランクというかカジュアルというか…。人によっては少し馴れ馴れしく感じることもあるかもしれません。
また、海外で標準的なのが、注文時に名前を聞かれてカップに書かれるスタイル。
毎回伝えるのは正直ちょっと面倒だな…と思う瞬間もあります(しかも日本人の名前は聴き取りづらいのかほぼ確実に間違えられるし)。
一方、日本のスターバックスは落ち着いた雰囲気で利用しやすく、呼び出しもレシートや番号でスムーズ。
さらに地域限定フラペチーノや日本ならではの具材を使ったケーキなど、独自のメニューが豊富にそろっているのが大きな魅力です。
さらに日本では2杯目が割引になるのも嬉しい!日本だと他にも同様のサービスがあったりして割と一般的なサービスという感じですが、海外では今のところ見かけません。
ただし一方で、カフェが17時くらいには閉店してしまうヨーロッパでは、比較的遅くまで営業しているスタバは非常にありがたい存在でもあります(といっても21時くらいまでには閉店してしまいますが)。
特にリヨンでは夜の勉強やグループワークなどの機会によくお世話になっていました。
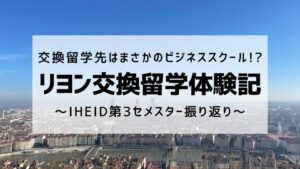
ご当地のお土産も魅力的で、コレクション心をくすぐりますね。

とはいえ、やっぱり使い勝手を総合するとやっぱり日本のスタバが好きかな。
「海外でも行けるけど、やっぱり日本のスタバの方が落ち着ける」。これが率直な感想です。
PAUL

フランスでは街のあちこちにある庶民的なベーカリーチェーンのPAUL(ポール)。
夕方には地元の人々が列を作っていたり、リヨンではクロワッサンとコーヒーで朝食セットが2.80ユーロほどで食べられたりと、日常使いのパン屋さんというイメージ。
当時住んでいたリュミエール地区にあるPAULでは、朝食時間帯には作業着姿のおじさんたちが朝から集まって食べている姿もよく見かけました。

一方、日本のPAULは完全に高級ベーカリーの立ち位置。クロワッサンひとつでも割高に感じることが多く、ちょっと背伸びする存在になっています。ただし、日本ならではの工夫として、コーヒーお代わり自由やパン食べ放題のセットなど、本場では見かけないサービスがあるのが特徴。
さらに日本のPAULは接客も安定して丁寧で、カフェコーナーもフランス感満点。「特別感を楽しむパン屋」としてすっかり定着しています。
筆者個人としてはフランスっぽい雰囲気なのにコーヒーお代わり自由というシステムが非常に気に入っており、よく近くのPAULでコーヒーを何杯も飲みながら朝フランス語を勉強していた時期がありましたね。
同じPAULでも、フランスと日本ではこれほど立ち位置が違うのは面白いものです。
日常使いはフランス、特別感とサービスは日本…そんなコントラストが際立つチェーンです。
まとめ
世界に広がるチェーン店。
実際に現地で試してみると「これはこれで面白い!」という発見もあれば、「いやいや、日本で食べた方が断然いい!」と痛感する場面も多々ありました。
特にこの記事で紹介したチェーン店は「海外にもあるけれど(というか海外発だったりもするけれど)、日本で入るべきだな…」と思ったものです。
もちろん海外で食べる体験にも価値はあります。特に国際的に展開しているチェーン店については、ローカライズされたメニューを見るのも結構楽しいです。しかしやっぱり日本のチェーンは味・サービス・限定メニューのどれを取っても完成度が高く、普段使いするなら断然日本クオリティーだな、と思うことも多かったです。
繰り返しになりますが、これから海外に長期滞在する予定の方はぜひ渡航前に食べ収めを。
すでに海外にいる方は…日本に帰ったときの楽しみにとっておきましょう!
以上です。
-1.png)


コメント