ついに来てしまった第4セメスター!泣いても笑っても大学院留学の最終章です。
授業の単位はすでに取り切っていたため、この学期の中心は修論執筆のみ。
このセメスターではリサーチトリップに出る学生も多く、このタイミングでジュネーヴを本格的に離れる人も少なくありません。
私自身も完全自走型の生活は久しぶりで、修論を進めながらスケジュール管理やモチベーションを維持することに苦労しました。自由度の高さは魅力である一方、戸惑いも大きかったのが正直なところ。
さらに、学業の終わりが見えてきたことで就活にも本格的にリソースを割くようになり、これまでの「学業全振り」から不慣れな国際機関就活への移行に伴ってメンタル面も揺れる日々でした。
この記事では、そんな第4セメスターを総合的に振り返ります。
第4セメスターの振り返り(総括)
まずはざっくりと第4セメスターに起きた出来事を振り返ります。
生活リズムを保つことの難しさ
まず冒頭にも述べた通り、第4セメスターは授業がなく(一応取ることはできる)やるべきことは修論執筆のみ。
つまり、どこに居ても良いし、何をしていても良い。
修論のためリサーチトリップに出掛ける学生がいれば、インターンシップにいそしむ学生も。
とにかく自由なので、すぐに「あれ?自分なにやってるんだろう…」と思ってしまうことも良くありました。
特に筆者はトピックに日本を選んでいたため日本にも一定期間滞在しており、余計にその感覚が強かったです。
気を抜くとすぐに昼夜逆転になってしまいそうで、そのあたりの管理も難しかったです。
国際機関就活のリアルに向き合う
また、このセメスターはEUパスポートを持たない学生の国際就活のリアルに直面した時期でもありました。
特に国際機関に外部から入ることの難しさ。
もとより非常にシビアな状況であることは想定していたものの、内部昇進でポジションが埋まってしまうという現実や、トランプ政権による研究者や国際機関職員を狙い撃ちするようなアメリカ滞在ビザの取り扱い変更と重なって、ここまで状況が悪化することまでは…さすがに想像できませんでした。
ジュネーヴの国際機関の職員から少しだけ話を聞くだけでも、新規採用をストップする機関があったり、既存の職員を降格する機関があったりと、就活生だけでなく既に働いている人々も厳しい状況であることがひしひしと伝わってきました。
ポジション選びの難しさ
さらに難しかったのが、アプライするポジションの絞り込みでした。
インターンシップにもいくつか応募してみたものの、結局職歴が長すぎてミスマッチなのか、箸にも棒にも掛からないという状況。しかもよくよく確認してみると、そもそも職歴にカウントされなかったり、無給だったり、なかなかの搾取ぶり。
インターンシップがここまで不条理なシステムであることは全く知りませんでした…。
さらに新卒である程度間口が広いインターンから入るのも大変なら、間口が絶望的に狭いミッドキャリアで途中から入るのはもっと大変…ということも改めて確認することになったのでした。
今振り返れば、学業に集中しつつもっと早めに動いても良かったな、と思います。
第3セメスターまで学業に全振りしていたのは当時の自分のキャパシティー的に仕方ない部分もありましたが、想像以上に就活が動かないのを実感してから、せめて第3セメスター途中くらいから本格的に動いておけば…というちょっとした後悔があります。
旅する留学生
そのような厳しい状況ではありましたが、久々にシンガポールや香港に行ってみたりと、学生という身分を活用して色々と自由に行動することができた時期でもありました(もちろん貯金と相談しつつ…)。
修論と就活でかなりメンタルが厳しい状態になっていたこともあり、これらの旅行は非常に良いリフレッシュになりました。旅で経験すること自体がそれぞれの内容と絶妙にリンクしていたので、単なる現実逃避にならなかった点も振り返れば良かったなと思います。
ブログ記事もいくつか仕上げることができ、わずかながら収入にも繋げることができた点も!
パリで修論の内容を詰めてからジュネーヴでフィニッシュを決められたのも良かったです。
次の項目からはそれぞれの内容について適宜深掘りしつつ、ミッドキャリア以外の留学生にも役立つよう、周りの学生の動きも順次紹介していきます。
修論執筆の記録
第4セメスターの中心はやはり修論執筆!
リヨン交換留学中にテーマをほぼ確定させて関連の授業を取る&執筆を開始していましたが、このセメスターに入ってから日本滞在で本格的に書き進め、5月のパリで追い込み、そして6月中旬の提出期限に間に合わせて提出。
正直に言えばリサーチの大部分と修論の提出はオンラインでもできるので、実はヨーロッパに渡航する必要はなかったのですが、そこは学業生活の集大成ともいえる時間。
ここでは環境に投資しながら留学生活を思いっきり楽しむことにしました。

トピックの決め方や指導教官決定までの流れといった具体的な修論執筆の方法については、別記事で詳しめに書く予定です。
テーマ確定から執筆本格化へ
第3セメスターまでの留学生活でインプットはほぼ終了。そこからは自分で集めたり指導教官にもらったりした資料を読み進めつつ、修論を書き上げていきます。
修論を書くのは初めてですし、どのようなペースで書けばよいのかもイマイチよく分かりません。
とにかく指導教官と連絡を取りながら進めていきました。ジュネーヴと香港でビデオ通話を繋いで修論の執筆について相談したのは、今では良い思い出です。
3月から4月くらいにかけては、兼ねてから副指導教官(Second reader)をお願いしていたEMリヨンビジネススクールの教授がちょうど多忙なことが判明し、ジュネーヴ側の教授に改めて副指導教官をお願いする必要が生じました。
幸いジュネーヴの教授にはすぐに受けていただくことができましたが、ちょっと冷や冷やしましたね。
パリでの追い込み
日本パートを粗方仕上げた後、5月下旬にはパリに向かいました。
目的は執筆活動。そこで修論の大幅な肉付けを行いました(適宜観光を挟みつつ…)。
5月末の時点で進捗は8割といったところでしょうか。
骨格はほぼ完成し、あとは細かいところを詰めていく作業をジュネーヴで行う段取りになりました。
パリでは割としっかり集中できる環境が整っていたので、特段大きな問題もなく、ほぼ完成まで持っていくことができましたね。このときのエアビーのオーナーに感謝です。
ジュネーヴで修論提出
修論の提出期限は6月15日。
その期限に合わせて6月初旬にパリからジュネーヴに移動し、最後の調整を行いました。
結局修論を提出したのは提出期限の約1週間前の6月10日。
成績が出るのは8月中旬ということで、ひとまず学業は一区切り。
修論を終えたことで、次の段階に移る準備がようやく整いました。
周りの学生はどんな感じだったか
アジア人の学生(特に修論のトピックをアジアにしている学生)はこのセメスターで母国に帰国したりリサーチトリップに行ったりしてジュネーヴを離れる(そして戻ってこない)パターンか、インターンシップなどでジュネーヴや他のヨーロッパ都市に残るパターンが多かったです。
第3セメスターで交換留学をした学生はそのままジュネーヴに戻ってこない、というパターンもありました。
このセメスターの過ごし方は本当に十人十色といった感じでしたね。
積み上げとリフレッシュの旅
このセメスターでは、日本滞在中に何度か旅に出ていました。
修論メインのパリとジュネーヴを除いて、アジアの旅先では修論やブログ記事を書いたりリフレッシュしたり。
上海経由のバンコク&シンガポール旅行
日本からまず向かったのはバンコクとシンガポール。上海経由(空港間移動あり)でした。
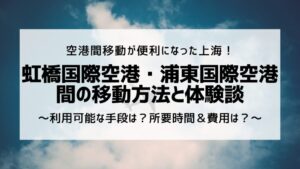
バンコクやシンガポールでは馴染みのエリアを巡ったり、友達や元同僚に再会したり。
ヨーロッパとは全く違う海外を久々に体感しながら、ジュネーヴでは難しい外食をエンジョイしました。
香港&深圳旅行
また、長らく訪問していなかった香港にも、この機会を利用して再び訪れることができました。
ずっと使っていなかったオクトパスカードが簡単に復活できるのは嬉しい驚き。
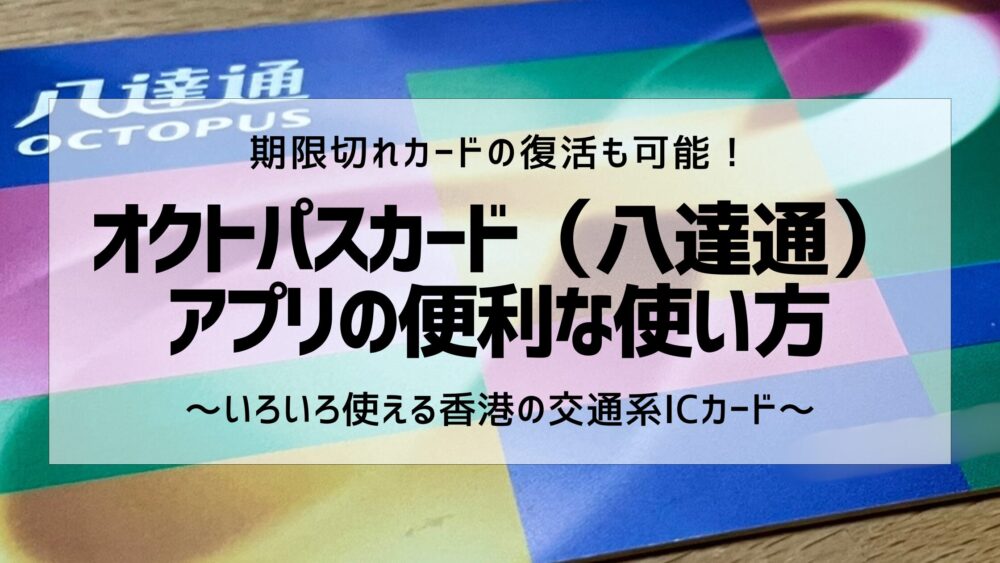
これまでは飲茶や夜景といったある意味定番な観光しかしていませんでしたが、今回はブロガーとして色々な記事を書くこともできて非常に有意義な滞在になりました。
リュックひとつで渡航してみるという実験も、ネタになるという事実がモチベーションに。
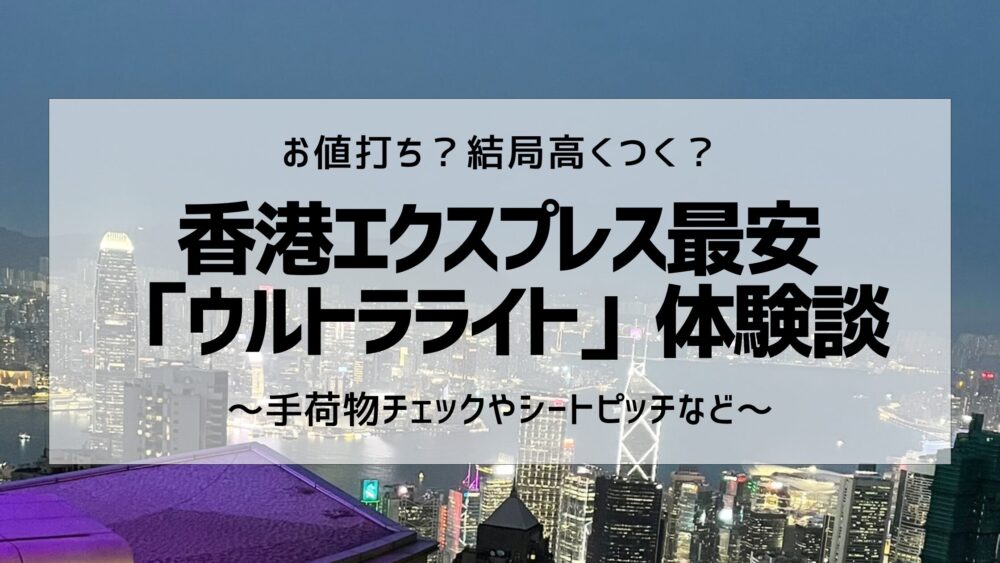
さらに今回の訪問を通じて、シンガポールと香港の比較という観点を持つことができたのも、個人的に嬉しかったポイントです。
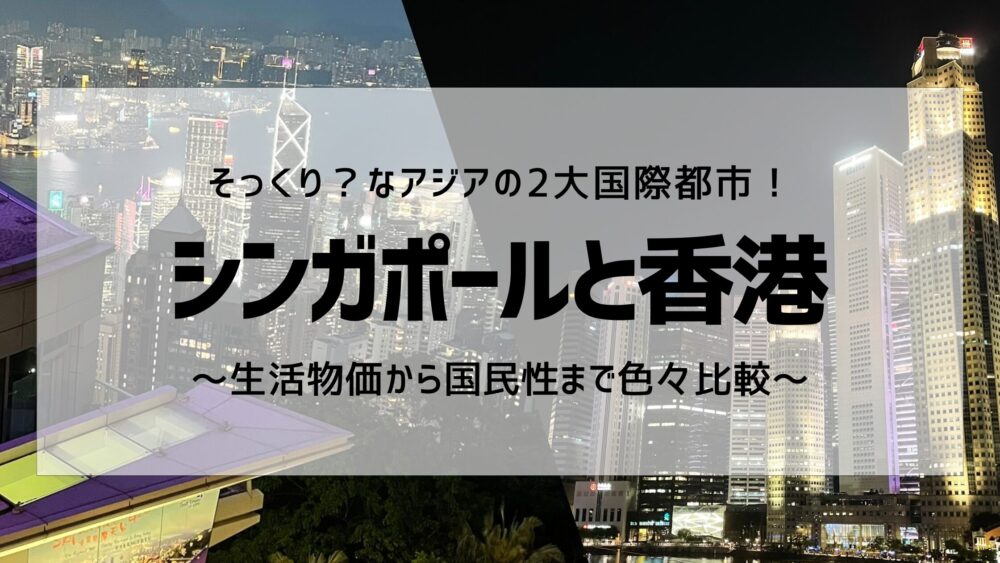
アジアの旅では観光やグルメはもちろん、修論のテーマを別の角度から深掘りしたり、ブログ記事を書いたり。
旅が精神的な支えになりましたし、修論と就活だけに囚われない多彩な経験もすることができました。
就活と葛藤
自由時間が増えたことで就活にも本腰を入れられるように。
その過程で現実に向き合う機会も増えてきました。
日本滞在中の応募・準備
日本滞在中はどうしても日本モードになってしまい、ジュネーヴでの感覚で海外と繋がっている感覚が薄れてしまうのが課題でした。そしてその影響は就活にも。
ジュネーヴやパリでは国際機関の本部があったり英語&フランス語の環境があったので自然とUNやNGOが視界に入るような状況でしたが、日本で入ってくる情報は日本語だったり、海外の報道とは全く違う内容だったり。
改めて日本の報道が国際政治や社会課題について非常に弱かったり偏重していることを認識する機会にはなったものの、どうしても思考は母国語に引っ張られていきます。
その状態で海外モードを保つのが本当に難しかった…。

国際機関やNGOなどの海外ポジションにアプライするときも、どうしても海外モードになり切れない自分がいました。何というか、脳内のスイッチが上手く切り替わらない感じ。
カフェに行くなどしてとにかく海外と同じ状況を再現しながら応募作業を進めていきました。
焦りと希望の間で
周りの学生がインターンシップをしているのを見てどうしても焦ってしまう自分。
ミッドキャリアの自分には合わないことが知っていながらもいくつか応募してみたり。
分かっていた通り、結果は散々でした。
確かに自分のキャリアを安売りするのは良くないです…。採用されなくて逆に良かった。
キャリアカウンセリングも受けて結局P-3~4に照準を定めることにしましたが、結果が全く返ってこない日々。
コンサル採用やLinkedInで海外就職に少しシフトしてきても、なかなか結果は出ず。
日本滞在中に外資系にも挑戦し、すぐに面接までは進みましたが、結局はピンと来ないまま。
まさに「迷走」という言葉がぴったりな時期でした。
一方で、応募を続けるうちに自分の立ち位置やキャリアの可能性が見えてきたという収穫もありました。
まとめ:日常生活と心境の変化
この学期の大部分を過ごしたのは日本。カフェや自宅など環境を切り替えながら執筆を進めました。
ただ、日本にいるとどうしても「海外モード」が薄れ、国際ニュースや情報に触れる感覚が鈍ってしまう瞬間も多々ありました。母国語の快適さに引っ張られながら、それでも「海外で学んでいる自分」をどう維持するか、意識的な工夫が必要でした。
ジュネーヴで迎えた最後の学期
6月に再びジュネーヴへ戻り、修論の最終調整と提出に臨みました。修論執筆自体はそこまで苦労しなかった印象でしたが、それでも終わったことによる虚無感に襲われる感覚がありました。
「これで本当に終わるのか」という寂しさと、「ようやく一区切り」という達成感。その両方を抱えて最後の学期を過ごしました。
心境のまとめ
第4セメスターは、修論執筆・就活・旅が入り混じった、まさに留学生活の集大成のような学期でした。
その一方で、未来が見えない焦りはどうしても付きまとってきます。
そんな感じで計画通りにいかないことも多かったものの、自分なりに最後まで走り切れたことは確かな自信につながっています。
以上です。
・第1セメスター(ジュネーヴ)中間振り返り
・第1セメスター(ジュネーヴ)総括振り返り
・第2セメスター(ジュネーヴ)総括振り返り
・第3セメスター(リヨン交換留学)総括振り返り
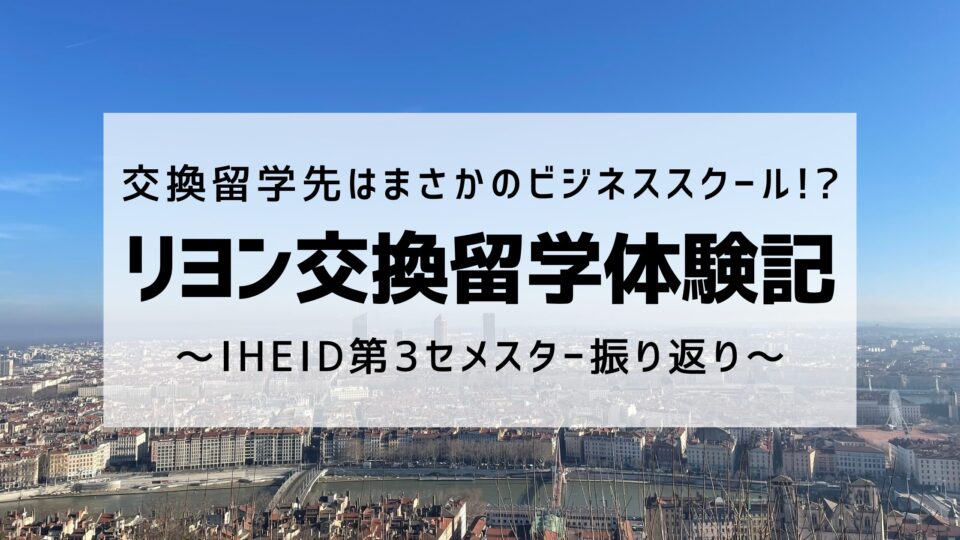
-1.png)
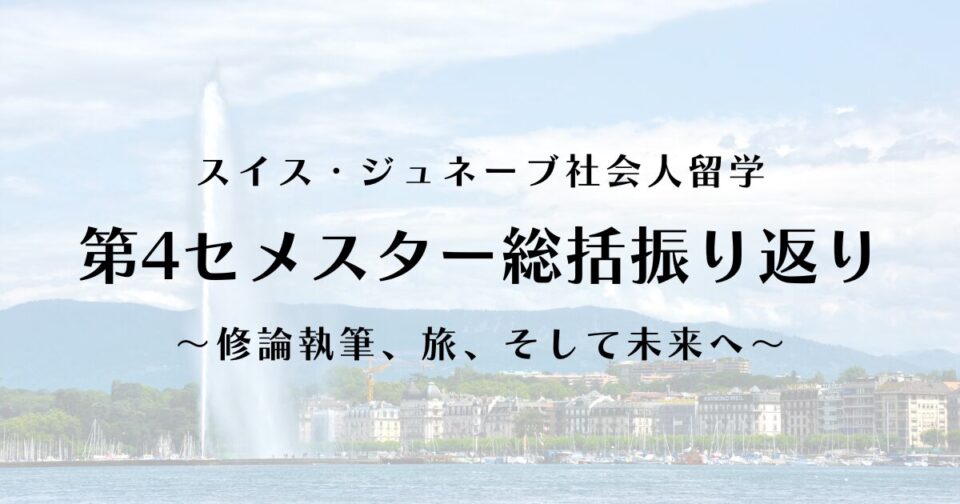

コメント