社会人としてキャリアを積み重ね、ある程度の安定を手に入れたあと、すべてを手放して海外留学に挑戦することは、勇気だけでは踏み出せない、大きな決断でした。
年齢、キャリア、経済的不安、そして家族への思い。いくつもの現実的な葛藤が重なり、一歩を踏み出すたびに、自分の選択を何度も問い直す日々が続きました。
今、私はジュネーブでの授業をすべて受け終え、修士論文執筆のために一時帰国しています。日々論文と向き合いながら、ふと立ち止まって、ここに至るまでの道のりを振り返ることが増えました。
なぜ、あのとき留学を決意したのか。なぜ、誰にも保証されない未来に飛び込もうとしたのか。
そして今、改めて自分が感じていることは何か。
これまでも折に触れてこれまでの振り返りを行っていますが、この記事では、改めて留学を決意するまでの葛藤とそこから導き出した小さな気づきについて、今の私の視点から率直に綴りたいと思います。
完璧な準備も、確信もなかった。それでも、不安を抱えたままでも、自分の人生を自分で選び取りたいと思った。
そんな過去の自分へ、そしてこれから新しい一歩を踏み出そうとしている誰かへ、この言葉が届くことを願っています。
キャリアに違和感を覚えた理由
まずは日本でキャリアを積み重ねていく過程で感じた違和感。
不本意な初期配属
大学時代は国際政治や国際協力に関心を持ち、国際法を中心に勉強しました。「世界とつながる仕事がしたい、何か広く社会のためになる仕事がしたい」と思って公務員になりました。
面接でも国際政治や語学のことを熱く語りました。
しかし最初に配属されたのは海外とは全く関係のない部署。専門性が必要な国際部門には新規採用職員が配属されないのは当たり前だと思っていたものの、地域密着型の業務に日々追われる中で自分の理想とのギャップに小さな違和感を覚え始めました。
積み上げられない専門性への苛立ち
公務員のキャリアパスは数年ごとの異動が前提です。どれだけ頑張っても、数年後にはまたゼロからのスタート。
さらに希望する部署への道筋も分かりません。どんなに自己研鑽に励んでも、どれだけ直属の上司に評価されても、今いる事業所から本庁の国際部門へはどうしたら異動できるのか…。
昇任試験に合格しても部署の希望が叶うとは限らない(というかほぼ叶わない)ことは先輩職員を見ていれば分かりました。
配属された部門で頑張れば頑張るほど、自分が積み上げたい専門性ではなく、所属に関する知識だけが積み上がっていく。希望の分野からどんどん遠のいていく。
自律的なキャリアを積み上げることが難しい仕組みに、次第に虚しさと苛立ちを感じるようになりました。
組織に守られる働き方の限界
組織に守られる安心感と引き換えに、自分でキャリアを切り拓く力が育たない。
外から中から心無い言葉を浴びせられても、自分の希望が叶えられなくても、それが当たり前。だって自分がこの仕事を選んだんだから。
ラッキーな同僚は願いが叶って、自分は叶えられない。それは当たり前。自分の実力が足りないのかもしれないし、自分の行動が何かまずかったのかもしれないし。判断材料は自分の手元にはない。
何を改善すれば希望が叶うのか、そもそも叶う可能性があるのか?暗中模索状態。
「このままではいけない」という焦りだけが、静かに心の奥に積もっていきました。
留学以外の選択肢はなかったのか
じゃあどうしたら良いのか?色々と考えながらも時間だけが過ぎていく日々。
日本型雇用への違和感と絶望
国内企業への転職は、そもそも選択肢にはありませんでした。なぜなら、公務員として働く中で、日本型雇用の限界を痛感していたからです。
組織の都合でキャリアが左右されること、自分の専門性や意思とは関係なく異動が繰り返されること。終身雇用の保証と引き換えに自分の人生を組織に差し出すという契約が本質にあること。この構造からは、どんな企業に転職したとしても根本的に逃れられないと感じていました。
私はただ自分の人生を自分で切り開きたいだけ。終身雇用なんて最初から望んでいません。
「もう二度と日本型雇用の枠組みの中で働きたくない」という気持ちが強まっていきました。
異動や自己啓発の限界
異動希望も出しましたし、庁内公募にも挑戦しました。
ただし希望はなかなか通らず、組織の硬直性を目の当たりにするたびに「この環境では限界がある」と痛感しました。
自分の望む環境に少しでも近づくため、英語も必死に勉強しました。フランス語も中国語も勉強しましたし、試験を受けて資格も取りました。社会人セミナーにも自費で参加しました。ヴァイオリンを習ったりもしましたね。でも、今自分のいる部署では意味がない。さらに英語が使えることで逆に「調子に乗っている」と思われる始末。非常に悔しい思いをしました。
当時は転職は当たり前ではなかったため、スキルが使えるところに転職するという発想はありませんし、前述のような日本型雇用の限界がある時点で論外。この構造から逃れるための道筋が全く見えません。
結果として、筆者は職場で「単なる海外好き」というキャラになりました。
資格取得も検討しましたが、日本国内でしか通用しないものが多く、自分が目指す「国際的なキャリア」にはつながらないと感じました。
日本型雇用への恨み言は大体この記事で発散した気がします。
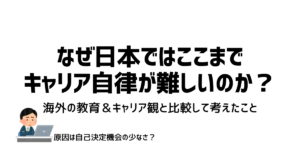
留学に踏み切れなかった理由と不安
国際機関で働くには、修士号以上がほぼ必須。「いずれ留学が必要になる」という現実は、ずっと頭のどこかでわかっていました。それに留学すれば、その土地で働く選択肢が増えます。海外就職が叶うかもしれない。
ただ、それを実行に移すタイミングを見極めるのが怖かった。そんな弱さとも、向き合わざるを得ませんでした。
自分に対する自信のなさ
本当に自分に、海外で通用するだけの力があるのか。未知の環境で、英語で授業を受け、議論に食らいついていけるのか。そう自問するたび、「できるわけがない」という心の声が耳元でささやきました。
年齢やキャリア以前に、一番のハードルは自分自身を信じきれなかったことだったのかもしれません。
周りに留学経験者が少なかった孤独感
私の周囲には、社会人になってから留学に挑戦した人はほとんどいませんでした。そもそも私の分野では学部卒業時点で大学院に進学する人も少なかったですし、留学なんてさらに少なかったです。
「普通はこのままキャリアを積み上げるものだ」「今さら留学なんてリスクが大きい」
そんな空気感の中で、孤独に決断を下さなければならなかったことが、想像以上に重くのしかかっていました。
そんななかで考えていた卒業後のキャリア戦略はこちらの記事に。

留学資金への現実的な不安
希望の留学先は国際機関の本部が集まるヨーロッパ。
何度か旅行することで物価の高さを肌で感じまとまった金額が必要なことは分かっていましたし、ある程度の貯金があったとはいえ、欧米と比較して給与の安い日本で蓄えられる額には限界があるのも事実。
ジュネーブやパリのような物価の高い都市で生活しながら学ぶことを考えると、資金面での不安は尽きません。
「もし資金が尽きたらどうするのだろう」
「途中で立ち行かなくなったら、誰が助けてくれるのだろう」
漠然とした経済的リスクが、常に頭の片隅に居座り続けていました。

外国人留学生に日本政府が多大な資金援助をしていると知ったときは、かなり腹が立った記憶があります。八つ当たりですね…。
決断を後押ししたもの
時間だけが過ぎていくなかで、大きな転機が訪れました。
シンガポール駐在で見た「自分で選ぶ人生」
ひたすらヨーロッパを思うなかで、やっと巡ってきたチャンスはシンガポールでした。
この打診を断ったら海外駐在の話は消滅する可能性を考えると「希望してきたヨーロッパではないので断ります」とは言えない。ヨーロッパに配属された同僚を尻目に応諾しました。自分はラッキーだと自分に言い聞かせながら。
ただしこの決断が非常に良い刺激を与えてくれました。ある意味ヨーロッパ以上かもしれません。
当時シンガポールは香港の凋落もあってアジアの金融ハブとして世界中の注目を集めるようになっており、ヨーロッパにはない熱気のようなものがありました。日本の芸能人が移住し始めていた時期でもありましたね。
そして、そこで出会った人たちは、年齢や過去に縛られることなく自らの意志でキャリアを切り拓いていました。
組織に頼らず自分の力で道を作り出し、世界中で自分の可能性を試していた彼ら。マルチリンガルは当たり前でハードワークも厭わないけれど、仕事一辺倒ではなく人生そのものも楽しんでいる。日本のように疲弊しながら働いたりする人は本当に少ない。その生き方に心から憧れを抱きました。
「こんなふうに、自分の人生を自分で選べるんだ」という驚きと、「自分で選ぶということを大切にしたい、というこれまでの自分の感覚は間違っていなかった」という確信。
ずっと心に描きながらも、自分がそこで生きることを半ば諦めていた世界がそこにはありました。
強烈な感動とともに、静かな決意が芽生えていきました。
他人に人生を預ける怖さに気づいた
公務員時代、配属も異動もすべて上司や組織の判断。自分の意思でキャリアをコントロールする感覚はほとんどありませんでした。努力や熱意とは無関係に「誰かの都合」で人生が決まっていく怖さ。
でも「それが当たり前」と受け入れる人に囲まれると、「おかしいと思うこと自体がおかしい」という感覚になってきます。
このままでは、自分の人生を自分で生きたとは到底言えない。そんな焦りと危機感は日増しに膨らんでいきました。
完璧な準備を待ってもチャンスは来ない
思えば、シンガポールでも何もかも完璧に計画どおりにいくことはありませんでした。むしろ想定外の出来事にどう対応するかがキャリアにとって決定的に重要。
完璧な準備を待っているうちに、チャンスは静かに、しかし確実に遠ざかっていく。それだけは明らかでした。
今ならある程度資金もあるし、東南アジアという成長著しいエリアに関する最新の知見もある。もし日本に戻ってしまったら、シンガポールや東南アジアの知識まず確実に生かせないし、英語力もきっと衰えてしまう。そしてそこで生活していた日々は単なる「楽しかった思い出」になってしまうかもしれない。それは絶対に嫌だ。
ならば、不安を抱えたままでも動くしかない。完璧じゃなくても踏み出した者だけが、新しい世界を手にできるのだ。
特に全てが不安定だったコロナ禍を経て、そう確信することができました。
覚悟と準備
留学を決断した際のマインドセットについても振り返りたいと思います。
留学費用はざっくりとしか計算しなかった
駐在を経てある程度の資金ができたので、駐在中に蓄えた貯金と退職金を頼りに「何とかなるだろう」とかなり大まかな資金計画を立てました。
もちろん、ジュネーブの物価の高さや為替リスク、突発的な出費への不安もありました。でも、細かく計算すればするほど、「やめた方がいい理由」ばかりが目についてしまう。
ある程度の目処が立った段階で、「あとは現地で対応する」と腹をくくることにしました。
失敗リスクを受け入れる覚悟
留学してもうまくいかないかもしれない。キャリアが思い通りに進まないかもしれない。
それでも、自分で選んだ結果ならすべて受け入れる。たとえ失敗しても、「挑戦しなかった後悔」よりはずっとましだと思えるようになっていました。
それに、日本は失敗を許さない社会であることは痛いほど感じていましたし、自分の人生を自分で選んで失敗するという経験も積ませてほしかった。この経験が自分にとって非常に重要なことは感覚的に分かっていました。
あとはこれまで色々と経験してきて、「何が起きても意外と大丈夫」という根拠がない楽観的な考え方をすることもできるようになりました。
怖さが完全に消えたわけではありません。でも、その怖さすら引き受ける覚悟がようやく持てたのです。
挑戦しなかった後悔の方が怖かった
もし動かずにいたら…。
数年後、あるいは老後に、「あのとき挑戦していれば」と後悔する自分が、簡単に想像できました。
たとえ道半ばで挫折したとしても、挑戦したという事実だけは必ず自分を支えてくれる。そんな確信が私を前に押し出してくれました。
留学準備の実際のスケジュールなどはこちらの記事で整理しています。

(これまでの)留学生活を振り返って
理想と現実のギャップに直面
ジュネーブでの生活は、決して華やかなものではありませんでした。
物価の高さに怯え、節約しながら生きる毎日。学業も英語での議論についていくのに必死でした。
そこには日本のような若者だからといって下に見るような文化はありません。自分よりも一回り若い同級生に何度も助けられましたし、知識量の差や問題意識の持ち方にショックを受けたこともたくさんありました。
日本でも良い大学を卒業してキャリアを積んできたから、何とかなるだろう。そんな甘い期待は一瞬で潰え、期待していた「国際都市での刺激的な生活」と現実とのギャップに、何度も心が折れそうになりました。
孤独と不安との闘い
異国の地で、一から人間関係を築くのは容易ではありませんでした。世代や文化の違いを感じる中で、孤独に耐える日々。世代や国籍が違えばノリも全く違います。
眠れない夜に、日本にいる両親に電話をかけたこともありました。ストレスからかつて治ったはずの皮膚の病気が再発したこともありました。
シンガポールでも一人暮らしをしていたため海外で孤独でも耐えられると思っていましたが、思えばシンガポールで働いていた環境は日本人が多く毎日日本語を使えたし、日常的に話せる相手もいました。アジア食もあった。そのような環境がいかにメンタルの安定につながっていたかをここで思い知ることになりました。
思ったよりも日本人環境やアジアの文化に助けられていたという事実に、勝手に自分はヨーロッパの方が合っていると考えていた筆者は愕然としたのです。
それでも、「自分で選んだ道だから」と何度も自分に言い聞かせながら前に進みました。
それでも選んでよかった理由
たとえ順風満帆ではなかったとしても、私はこの道を選んで本当によかったと思っています。
挑戦しなかった後悔よりも、挑戦して得た経験の方が、私にとっては何倍も大きな意味を持っていました。
新しく得た経験や知識は過去を振り返る良いきっかけになりましたし、振り返るための時間も与えてくれました。シンガポールに渡航したり、かつて一緒に働いた同僚と再会したりすることで、改めてこれまでに積み上げてきたものは無駄ではなかったと確信することができました。
たとえ道半ばで転んだとしても、自分で選び、自分で歩いた道は、必ず自分を支えてくれる。
今は、心からそう思っています。
日常生活で感じていたことはこちらの記事に書いていました。
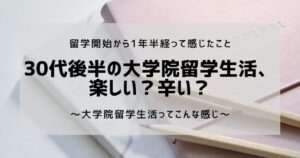
まとめ
挑戦には、いつだって不安とリスクがつきまといます。それでも、「完璧なタイミング」が訪れることはありません。年齢、資金、スキル…。不安要素を数え上げれば、動かない理由はいくらでも作れる。
でも、そうして動かずにいたら、人生はあっという間に過ぎてしまう。
留学を決意したとき、私はすべてに自信があったわけではありませんでした。むしろ、不安の方が何倍も大きかった。それでも、挑戦しなかった後悔だけは絶対にしたくなかった。
結果がどうであれ、「自分で選び、自分で責任を持って歩いた」という事実は、未来の自分を必ず支えてくれる。
今、不安や迷いの中にいる人がいるなら、私は声を大にして伝えたい。完璧なタイミングを待たなくてもいい。不安を抱えたままでもいい。大切なのは、「自分の意志で、自分の人生を選び取ること」。
私もこれから先、何度も迷い、立ち止まることがあると思います。現に今だって修士論文やら将来のキャリアやらに迷ってばっかりです。
それでも、自分で選んだこの道を、一歩一歩進んでいきたいと思います。
以上です。
-1.png)
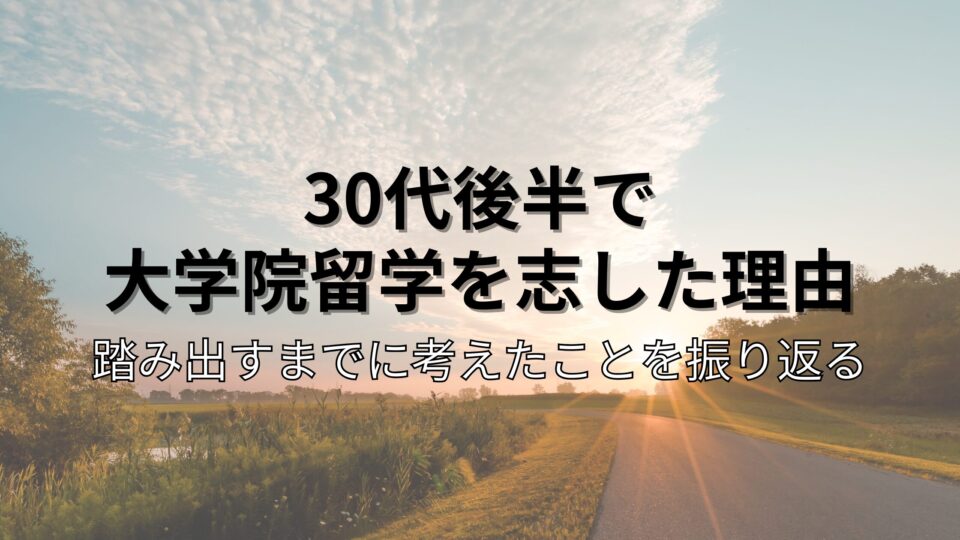
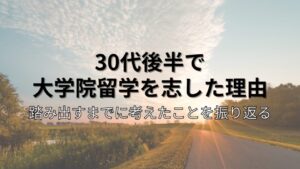
コメント