海外留学でどうしても気になるのが、授業中の発言や課題といった場面で日本人留学生が英語力不足によりかなり損をしているように思える点(特に議論への参加が重要視される授業では致命傷になりかねない)。
授業中に積極的に発言するかどうかについては確かに文化的背景が関係しているとは思いますが、英語と全く異なる言語を母語としている国から来ている学生も普通にディスカッションに参加しているので、言い訳にはなりません。
振り返ってみると、実際筆者自身もIELTSやTOEICなどで目標のスコアがなかなか取れずに悔しい思いをしたことが何度もありますし、スピーキングやライティングは今でも得意ではありません。
今回はなぜこのような状況が発生してしまうのか考えてみました。
学校教育を悪者にするのは単純すぎる
日本人が英語を使えない原因のひとつとして良く挙げられる学校教育の悪さ。
確かに中学校・高校・大学(最近は小学校から)と相当の期間英語を学んでいるのにも関わらず英語が話せる日本人が極端に少ないことを考えると、ここに大きな原因がありそう。
「英語を使う前提で教えていない」という批判も多いですね。
問題が全くないとは言わないけれど
確かに日本の英語教育は英語を実世界で使う前提にはなっていないように感じますし、どちらかと言うと受験に合格するためのカリキュラムといった印象です。
その結果以下のような弊害が生まれていると感じています。
- 訳出(英訳・和訳)を重視するあまり、英語を英語で理解するための訓練が不足する
- 発音を軽視することで、意思疎通が困難になるレベルのなまりが放置される
- 正確さを重視しすぎることで、間違いを過剰に恐れるようになる
- 英語で教え(られ)ないので、授業で実際に英語を使う機会が少ない
(後述のように)日本において「英語を使えること」よりも「良い大学に入ること」が蓋然性の高い成功条件になるのであれば、そうなるのも致し方ないのかもしれません。

有名大学を卒業する方が英語が使えるよりも良いポジションに就く可能性が高ければ、どちらを優先するかは明らか。
そして受験に合格することが目的になると、受験生を振り落とすために大学が入学試験で課す細かい文法問題や難解な長文読解への対応がメインになりやすいという点はあると思います。
そして日本で良く見られるペーパー一発勝負の受験方式の場合、他の受験生が解けないような難しい問題を正答することよりも、他の受験生が皆正解するような簡単な問題を落とさないことが重要になります(高校の成績や志望動機が見られる受験方式であればこのような現象は生じない)。同じ理由でライティングやスピーキングのようなアウトプット力は受験では求められないので後回しになります。
細部に注意を向けることが肝要なため、受験科目全般が完璧主義&減点方式の指導スタイルになってしまうのは当然の帰結です。

実際に役立つかどうかは別としても、受験勉強のための詰め込みによってボキャブラリーが大幅に強化されたのも事実です。
公立学校の英語教員の大半が英語を満足に話せなくても英語教師で居られるのは、授業中に英語話者と話すことよりも、学習内容の習得に重きを置いているからと考えれば納得。
もちろん英語教師の英語力が高ければ言うことはありませんが、求められる英語力に達していない事実だけを議論の中心に据えてとやかく言うのは、生徒・学生の英語力向上という点では的外れと言わざるを得ません。英語ネイティブを連れて来れば皆ペラペラという図式が成立しないのをみれば明らかです。
なお学校教育がコミュニケーションの側面を無視してきたかと言えば全くそのようなことはなく、公立の学校には以前からALTのような外国人教員はいましたし、近年はより「使える英語」を目指す流れもあり、会話力を鍛える場が全くなかったかといえばそうでもありません。
筆者の学生時代を思い出すと、英語が純粋に好きな学生はそのような授業に積極的に参加したり英語クラブに入ったりしていたので、英語力を鍛える機会は作ろうと思えば割と作れる環境だったとも言えます。
そもそも外国語習得に必要な時間はどのくらい?
日本語と英語の言語間距離(文法構造や発音など言語を構成する諸々の要素)は遠いため、日本人が英語を習得するためには3,000時間弱かかると言われています。これはハイレベルな英語力を付けるための時間なので、要求レベルを下げれば必要な時間は少なくなります。
一方で、英語との言語間距離が比較的近い言語(ヨーロッパ諸語など)を母語とする場合は、この何分の一かの時間で英語を習得することが可能であると言われています。

言語間距離の近いはずのフランス語話者でも英語が使えないケースもあるので、あくまで理論的にはという話。
もし英語学習の機会を学校の授業だけと仮定すると、週に数コマの英語の授業を数年受けただけでは到底十分な時間には達しません。
外国語は学校英語「だけ」で十分であるべき?
まずそもそも教育機関(義務教育&高等教育)は語学学校ではありません。英語以外にも学ぶべきことがたくさんあります。そうすると、英語を習得するために必要な時間を確保するのはかなり難しいですし、そもそも求められていません。
学校だけでは英語取得に必要な時間を捻出するのは不可能なため、英語ができない理由を日本の学校教育に求めるのは間違いといえるでしょう。
日本人には英語学習の動機がない
上述の学校教育を踏まえると英語の習得には学校教育以外のトレーニングが必要という話になりますし、ある程度時間をかければ皆ある程度のレベルに到達できるとも言えます。
つまりトレーニングを積みつつ年齢を重ねれば英語力は上がっているはずですが、相当時間かけているのに英語が使えるようにならない人もたくさんいます。つまり、英語の学習密度が低いという仮説を立てることができます。
英語の学習密度が低くなる背景としては、そもそも日本人には英語が要らないのでトレーニングをする必要がないという日本の現状がありそうです。
英語ができなくても生活できる
日本で生きている限り、英語でないと生活できないという状況はまず訪れません。仕事も買い物といった生活のあらゆるシーンで日本語が使えますし、高等教育も日本語で受けることができます。
また外国のニュースについても日本語に翻訳された情報を得ることが可能です。一部日本語で提供されていない情報もありますが、必要に応じて翻訳ツールを利用すれば問題なし。
さらに国によっては出稼ぎを奨励しているところもありますし、観光業が国の主要産業となっており外国人観光客を相手にしなければいけない場合もあり、その場合は生活するために英語が必要になりますが、日本は状況が違います。大半の日本人は海外旅行に行くのでもなければ英語を求められることにはなりません。
インバウンド客が増えれば観光地では英語を含めた外国語対応ができないと困るというシチュエーションが発生しそうですが、そうでなければ別に英語が出来なくても問題ありません。
英語ができなくても学歴が手に入る
大学受験では英語を読んだり聞いたりする「インプット能力」は対象になっても、話したり書いたりする「アウトプット能力」は対象にならないことが多いです。
インプット能力を測る際は一つの正答を設定することが可能な一方、アウトプット能力を測る試験では正答がそれこそ無限にあるため、採点者に高い技量が求められると同時に多少主観も入るから公平性を損なう恐れがあるからですね。
日本のペーパー一発勝負方式では志望理由書や高校の成績といった他の項目での挽回が難しいことを考えると、公平性の担保にここまで注力するのは当たり前なのかもしれません。
つまり必要なのは英語の試験で良い成績を挙げることであって、英語が運用できることではありません。前述の学校教育と目的が一致するので、試験で問われる英語力(リーディングやリスニングが中心)に時間を割くようになり、試験で問われないスピーキングやライティングについては、時間の無駄なので取り組まなくなります。
文法の知識や語彙力は積みあがっていきますが、トレーニングが必要なスピーキングやライティングについては手つかずのままなので、アウトプット能力はほぼ伸びません。でも英語で学業をするわけではないので問題なし。
英語ができなくても昇進・昇給できる
英語ができることはキャリアにプラスに働く可能性があるのは間違いありません。
英語の運用能力が高ければ、外資系に就職できたり、日系企業であっても英語を必要とする部署や海外駐在に選ばれる可能性が高まるかもしれません。日系企業の海外駐在であれば国内勤務では得られないような手当が付いて手取りが増えることが期待できますね。
ただし生涯賃金に直結してくる昇進・昇給の機会において英語力が考慮されるかというと、その基準になるのはあくまで仕事上の成果や関連するスキルであり、海外勤務が前提にでもなっていない限りは英語力はあれば尚可というレベルであることがほとんど。役職によっては英語力は全く求められません。
つまり、英語が出来なくても昇進したり収入を上げたりすることが可能です。
また日系企業であれば異動制度で人員を移転させることが可能なので、例えば所属している部門が海外に移転したり外資系に買収されるなどで将来的に業務に英語力が必要になる場合であっても、それだけではリストラにならず英語力が不要な部署に異動になるだけで済むことも考えられます。
英語ができなくても海外で働ける(※日本企業の駐在員限定)
最も高い英語力が求められそうなシチュエーションが海外勤務。日本企業に勤務する場合、取りうる選択肢は現地採用か駐在員がメジャーです。
特に駐在員は日本の雇用制度が変化しつつある現在においても待遇は現地採用に比べて圧倒的に良く、日本企業に在籍したまま出向するので簡単にはリストラされないという安定性があるので非常に魅力的です。
そのような好待遇を得るためには英語力がカギを握っている気もしますが、日本企業では「海外駐在員を選定する権限を持つ社員に実力を認められる」ことの方がはるかに重要なので、ただ英語力を上げても選ばれるとは限りません。

どんなに英語力が高くても社内で駐在員候補の人材プールに入っていなければ海外勤務の可能性は非常に低いです。
英語が多少苦手であっても、優秀であることを示せるスキルや実績がある方が海外駐在のチャンスを得られる確率が高まります。
日本企業が語学力を海外駐在の要件として重要視していないことは、大企業の海外事業所に日本語ができる現地スタッフが配置されていたり、企業の負担で語学研修が受けられることもあることを考えると分かりやすいです。
またもしそのような制度が存在しない場合であっても、日本では得られない手当など様々なメリットが受けられることも多いので、そのような好待遇が語学力を上げるモチベーションアップにつながります。
つまり、海外勤務を目指す場合であっても、日本企業で働くことを前提とすると英語の優先度はあまり高くないと言えます。
生存できるから強い動機付けは生まれにくい
上述の4点から、日本人が日本で生きている限り英語によるコミュニケーション能力はほぼ不要であり、英語ができることによる特別なメリットがないことが分かります。
つまり日本人には英語を学習するための内的動機付けがほぼ存在しないことが分かります。
内的動機付けがないので、英語学習のゴール(どの程度使えるようになりたいのか)や手法(どの技能に注力するのか)も選べません。
そのため、モチベーションは以下のようなフワフワした感じになってしまいます。
- リスキリングブーム到来で何か学ばないといけない気がするので、とりあえず英語を学習してみる
- 特にアテはないけれど、将来的に役に立ちそうだから
- 特定業界を考えているわけではないけれど、TOEICスコアを上げれば自分の市場価値も上がりそうだから
上記のような軽い動機しかないと、結果として英語学習にどれだけ時間をかけようと使えるレベルにならないのは当たり前なのかもしれません。
文化的な要因
前の項目では英語学習に際し内的な動機付けが不足することで英語学習が満足に成果を挙げられなくなるということについて考察しました。しかし、日本における英語学習者の全員が内的な動機付けが不足しているとは言えません。モチベーション高く頑張っているのに成果が出ずに、途中で嫌になってしまうこともよくあります。
では学習機会を自分で作るほどモチベーションの高い学習者であっても、思うように能力が向上しないのはなぜなのでしょうか?
日本におけるコミュニケーションスタイルが理由になりそうです。
ハイコンテクスト文化
日本のコミュニケーションスタイルを特徴づけるのが、個よりも集団を重要視し共通の文脈を意識するというハイコンテクスト文化。ハイコンテクスト文化では、言語によるコミュニケーションを多用することはなく、その場の雰囲気から相手の意図を汲み取ることが求められます。
共通の文脈を構築する必要があることから、高い同質性を保とうとするのも特徴的です。
また長期的な信頼関係が何より重要であると考えるため、相手の気分を害したり関係構築に支障をきたす恐れのある衝突をとにかく避けようとします。
一方で英語圏はほぼ例外なくローコンテクスト文化。こちらは相手の心情よりも事実や論理を重視するため、直接的な言語コミュニケーションを好みます。同質性が低いことも多く共通の文脈が存在しないため、察することを求めるのは困難です。
上記の文化的背景から英語の表現は直接的なものになりがちであり、日本式のコミュニケーションを前提とする場で英語を使うと、英語には日本語に完璧に対応する表現が存在しないため、ちぐはぐな感じのコミュニケーションになってしまいます。

英語を直接和訳するとおかしな状況になってしまうことが多いです。
カタカナ語と和製英語
日本人は外国(特に西洋)をカッコイイ・最先端と思いがち。
そのため外来語を日本語に訳すのではなくカタカナ語として用いたり、ゴロの良い単語を組み合わせたり削ったりして英語圏には存在しないボキャブラリー(いわゆる和製英語)を作ったりします。
そして多くの場合、日本人が発音しやすいよう英語にしかない発音を簡略化したり、本来複数形で用いられる単語を単数形にしたりします。企業のキャッチコピーや商品名にはこのパターンが良く見られます。
柔軟なのは良いことですが、問題はこれらを英語と誤認してコミュニケーションに使ってしまう結果、齟齬が生じたり、正しい語彙を学習する必要があるために学び直す手間が増えてしまうこと。
未学習の語彙であれば学習するだけで済みますが、和製英語の場合、既にその用法が頭に染みついてしまっていると、和製英語としての意味を捉え直してから本来の意味を学習するというステップが必要になります。

「クレーム」とか「メリット・デメリット」とか、うっかり使ってしまいそうになりますが通じません。
カタカナ語を多用する一方で、聞き慣れない発音を笑うような風潮も。正しくても嘲笑の的になってしまうのですからいたたまれません。いくら正確な発音を知っていてもカタカナ語のように発音することになってしまいます。
完璧主義
もう一つの語学学習の壁が日本人に多い完璧主義。
語学学習にはミスを繰り返しつつ少しずつ習得していくプロセスが不可欠ですが、間違いを恐れて使用頻度を減らす(行動量が減る)ことは、目の前の貴重な機会を自ら潰していることになります。
間違いを恐れずに使っていけば必ず上達するはずなのですが、日本人は大抵文法偏重の教育を受けているためか、細かいミスを指摘したがる人や他人のミスを嘲笑うタイプの人が一定数いることもあって、「間違えてはいけない」「完璧でないといけない」という強迫観念を抱きがちなのが難しいところ。
この表現がネイティブに通じるか、この発音はネイティブに近いか、ということも日本人はよく気にしていますね。英語の発音なんて世界中にそれこそ人の数だけあるんですが…。
英語警察のように細かい間違いを指摘していても全く建設的ではなく生産性もありません。当然英語の運用能力なんて上がらないですよね…。

大学院の授業では内容の方が重要!発言意図が伝わればOKです。文法に多少間違いがあっても誰も気にしません。
じゃあどうすれば良いのか?
適切な目標を設定する
英語に限らず言語学習は結局のところ目標設定が全てだと思います。つまり、何のためにやりたいの?というところ。
「仕事で英語を使いたい」と言っても、「今まさに特定の分野で英語を使う必要がある」パターンと、「いつか英語を使って働きたい」パターンでは、目指す場所が全く違います。まずは自分のニーズを考えるのが先決。

筆者は海外大学院合格が目標だったので、志望校の求めるIELTS/TOEFLスコアが自然に越えるべき基準になりました。
もし現段階でそのあたりが明確でなければ「今の人生に英語はいらない」ということなので、手近なところから始めてみるか、いっそ英語学習をしない・辞めてみるのも手かもしれません。
適切な環境を作る
筆者の場合、日本人(英語警察)に文法チェックをされるのが嫌だったので、マンツーマンレッスンのある英会話教室に行ったり、IELTSの問題集を解いたりしていました。
正直海外大学院留学中の今でも英語力の不足は感じますが、自分の話したい・書きたい想いを汲み取ってくれる場所なので、発言内容に注力することができ、結果として留学開始時よりもさらに英語力が向上しているのを感じます。

英語学習時とは比較にならない量のリーディングやディスカッションを日々こなすのが良いトレーニングになっています。
「失敗したくない」「恥をかきたくない」と考えていると緊張して動けなくなってしまいますが、例えば大学院の授業で「自分はこう思う」「自分はこうしたい」ということを発言するという点を中心に据えると、最適な表現が思いつかないときには別の語彙で言いたいことを表現したり、ジェスチャーを使って表現したりと勝手に努力できるようになります。

自己実現しているので苦しくても楽しいです。
語学学習の果てに何をしたいかを考えてその環境や似た環境に飛び込んでみるのも、良いモチベーションになるのでおすすめです!例えば以下のような感じ。
- 海外旅行で使いたい!→ランゲージエクスチェンジに参加する、旅行イベントに行ってみる、海外旅行に行ってみる
- 外国人の友達作りがしたい!→言語交換アプリを使ってみる
- 留学で使いたい!→MOOCSやCourseraで授業を体験してみる、実際に留学してみる
まとめ
今回は「日本人はなぜ英語が使えないのか?」という疑問について、自分なりの分析をしてみました。
それぞれの項目を総合すると、日本人には英語を話す動機がなく、動機があったとしても文化的な障壁がその動機を弱めたり学習機会を奪っているという現状が見えてきたように思います。つまり、モチベーションだけでは無理なので、適切な環境に自分を置く必要があるということ。学校教育に頼り切らない自己研鑽が欠かせません。
「手軽にペラペラ」はやっぱり存在しないということですね…。
これだけ多くの障害を乗り越えるためには、付け焼刃ではない動機と適切な環境を整えられるだけの労力や(状況によっては)財力が必要。これからの英語と日本人の関係は以下のタイプに2分化してきそう。
- 英語は使わなくてOK。もし必要なら翻訳ツールがあれば用を足せる。
- 業務遂行に英語を使う。翻訳ツールだけでは足りないので本物の英語力が必要。
近年のリスキリングブームで身につけたいスキルの上位に入る英語力ですが、自分が後者のタイプ(業務遂行でバリバリ英語を使う)に入ると断言できる人以外は、中途半端なレベルにしか到達できず結局無意味に終わりそうです。
以上です。
-1.png)
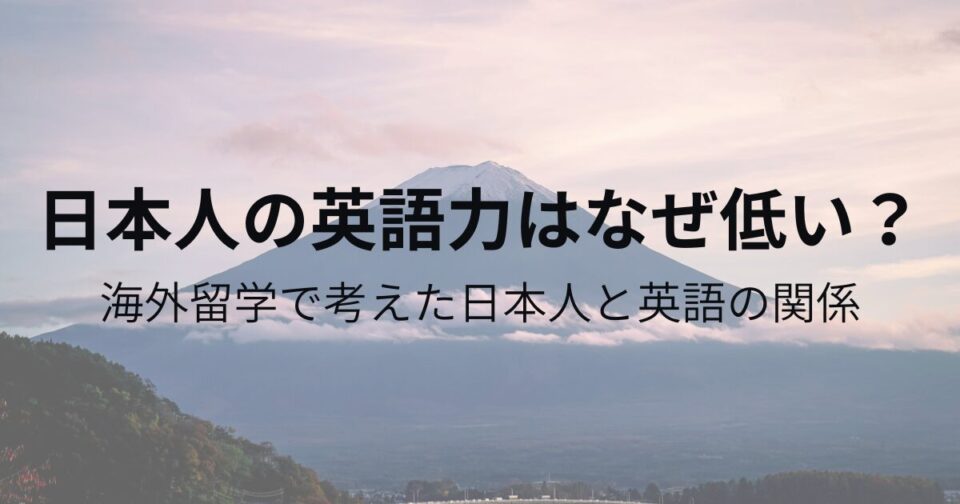
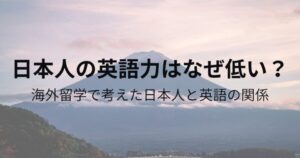
コメント