イスタンブールといえば、ヨーロッパとオリエンタルな雰囲気が混じり合う街並みが魅力的な都市。
アルファベットで書かれた看板はどこかヨーロッパのようで、とてもオシャレに見えます。
もっとも、書かれているのはすべてトルコ語なので、私にはほとんど読めないのですが…。
そんな街を歩いていると、美容室の看板に「KUAFÖR」、切符売り場に「BİLET」と書かれているのを見かけ、不思議な既視感を覚えました。あれ? フランス語の coiffeur(美容室)や billet(切符)にそっくりでは?偶然?
気になって調べてみるとビックリ。
実はこれらはすべてフランス語からトルコ語に入った借用語だったのです。
さらに調べてみると、他にもフランス語由来のトルコ語が数多くあることが分かりました。
この記事では、イスタンブールで見かけたフランス語由来のトルコ語を紹介しながら、なぜこんなにもフランス語が多いのか、その歴史的背景を探っていきます。
イスタンブールで見つけたフランス語
街中で見かけたフランス語由来の単語
イスタンブールの街角を歩いていると、本当にあちこちでフランス語に出会います。ここでは、実際に私が撮った看板や表示をいくつか紹介します。
- ASANSÖR(ascenseur = エレベーター)
ホテルや公共施設のエレベーターには必ずこの表示。
フランス語を学んだ人なら、すぐに「あっ」と気づくはずです。

- BİLET(billet = 切符) + GİŞE(guichet = 窓口)
鉄道駅や博物館のチケット売り場で目にする言葉。
看板に「Bilet Gişesi」とあれば、まさに「切符窓口」を意味します。

- MÜZE(musée = 博物館) + MAĞAZA(magasin = 店)
博物館の売店には「Müze Mağazası」という表示。実はこの両方がフランス語由来。
トルコ語に定着してしまっているのが面白いです。

- KUAFÖR(coiffeur = 美容室)
街を歩けば必ず目に入る美容室の看板。発音もつづりもフランス語そっくりです。

他にもまだある!フランス語由来のトルコ語
ここまで紹介したもの以外にも、街中でよく目にするフランス語由来の単語があります。
- OTOBÜS(autobus = バス)
バス停や車体に大きく書かれているので、旅行者なら必ず目にする言葉。語源はフランス語の autobus。 - GAR(gare = 駅)
大都市の鉄道駅に掲げられる看板。「Sirkeci Garı」「Haydarpaşa Garı」など、駅名と一緒に使われます。 - ŞOFÖR(chauffeur = 運転手)
バス会社やタクシー関連の注意書きに登場。読み方もほぼフランス語そのままです。 - MAKYAJ(maquillage = 化粧)
コスメショップや広告でよく見かける単語。女性誌の見出しにも普通に登場します。 - FİLTRE(filtre = フィルター)
「filtre kahve(フィルターコーヒー)」「filtre sigara(フィルター付きタバコ)」などでおなじみ。日常に溶け込んだ借用語です。kahveのような非フランス語由来の単語とセットで使われるのも面白いところ。
トルコでフランス語が流行っている?
カフェやソムリエなど、日本語にも定着しているフランス語はあります。
しかしトルコ語におけるフランス語の存在感は、その比ではありません。街角の看板や日常語の中に、まるで自国語のようにフランス語が溶け込んでいるのです。
どうやら単なる流行語や一時的な借用ではなく、もっと大きな理由がありそうです。
実は、19世紀から20世紀初頭にかけて、オスマン帝国から共和国へと移行する時代に、フランス語は政治・文化の面で特別な役割を果たしていました。
その歴史的な背景については、次の章で詳しく見ていきます。
トルコ語にフランス語からの借用語が多い理由
19世紀〜20世紀初頭:国際語としてのフランス語
19世紀から20世紀初頭にかけて、フランス語は国際語として特別な地位を持っていました。ヨーロッパ諸国間の外交や条約文書、国際会議はフランス語で行われ、オスマン帝国もその流れに倣いました。
この背景には、16世紀以来フランスに与えられてきたカピチュレーション(治外法権や通商特権)も関係しています。フランスはオスマン帝国内で特権的な地位を持ち、商業や外交で深く関わっていたため、自然にフランス語が「欧州列強とやり取りする実用言語」となったのです。
1850年代以降、オスマン帝国外務省はフランス語を補助言語として使用し、主要な改革文書もフランス語版が作成されました。1839年のギュルハネ勅書や1856年の改革勅書はその代表で、とくに1856年の改革勅書(イスラーハット・フェルマーニ)はフランス語での公表が重視されていました。
国際連盟(1920年設立)では英語とフランス語が並列の公用語となりましたが、それでも当初はフランス語が優越的な位置を占め、セーヴル条約(1920)のように正文をフランス語版に基づくとする条約も存在しました。
オスマン帝国末期と共和国初期の西洋化
19世紀後半、オスマン帝国は国家としての近代化を迫られ、西洋を積極的にモデルとしました。
特にフランスは文化的手本として大きな影響を与えました。法律や教育、都市インフラの整備などでフランス式の制度や概念が導入され、それに伴い言葉も一緒に輸入されていきました。
イスタンブールやイズミルでは19世紀後半からフランス語の新聞・雑誌が数多く刊行され、非ムスリム住民や商人の間で共通語として用いられました。報道機関の記事によると、オスマン帝国後期には400以上の仏語定期刊行物が発行され、その66%は完全にフランス語で書かれていたといいます。
第一次世界大戦後も仏語メディアは存続し、初期共和国時代にも使用され続けました。
建築様式にもその影響が色濃く表れています。イスタンブールのドルマバフチェ宮殿(1843〜1856年建設)は、バロックやロココ、新古典主義といったヨーロッパの様式を取り入れた豪華な建物です。宮殿は単なる権力の象徴ではなく、「西欧列強に並ぶ近代国家である」という自己表現でもありました。
こうした欧化の空気の中で、フランス語は都市生活や文化の象徴として人々の目に触れ、耳に届くようになっていきました。
ラテン文字改革とフランス語借用語の定着
共和国成立後もこの傾向は続きました。アタテュルクのもとで進められた西洋化政策は、教育や都市文化を一新し、フランス語由来の語彙を「近代的で洗練されたもの」として定着させる大きな後押しとなりました。
1928年には共和国は大規模な文字改革によって、それまで使われていたアラビア文字を廃止し、ラテン文字を導入。この改革によって識字率は大幅に改善し、公共空間における文字表記が一気に刷新されました。
このときの改革の対象は主に表記体系であり語彙レベルの借用語そのものを排除するものではありませんでしたが、アラビア語表記よりも借用語の表記法がはっきりしたことで外来語を受け容れる素地が出来上がりました。
フランス語の語彙が増えたのはこの後。20世紀の用語改革(特に1930年代以降の語彙純化運動)ではアラビア語やペルシア語由来語の置き換えが進められましたが、フランス語を含む西洋語由来語には新語が多かったため、相対的に割合が増加することになりました。
こうして日常会話の中にまでフランス語が自然に定着しました。
「国際語=英語」というのは現代の感覚です。ですが、19世紀から20世紀初頭にかけての国際社会では事情が大きく異なっていました。
- 外交の標準語はフランス語
ウィーン会議(1815)以降、国際条約や会議はフランス語が基本。オスマン帝国の勅書や憲法もフランス語版が存在し、外務省では実務言語としてフランス語が使われていました。 - 英語が台頭するのは第一次世界大戦後
国際連盟(1920年設立)ではじめて「英語とフランス語」が並列の公用語となり、その後しだいに英語の存在感が増していきます。
当時のトルコにとってフランス語を借用するのは、単なる流行や嗜好ではなく、国際社会の常識に沿ったごく自然な選択だったのです。
日本と比較すると見えてくる違い
翻訳の日本vs借用語のトルコ
19世紀後半、明治維新期の日本と同じく、オスマン帝国からトルコ共和国へと移行する過程でも、「西欧の概念」を取り入れる試みが行われました。
ただし両国のアプローチは大きく異なります。
日本では、西欧の新しい概念を翻訳語として創出しました。たとえば「liberté → 自由」「économie → 経済」「société → 社会」など、今日の日本語に欠かせない基本語彙はこの時代に生まれた造語です。
物品名や固有名詞のように翻訳が難しいものはカタカナや音写漢字で表記し、それ以外はできる限り「漢字による新語」として定着させました。
一方、トルコでは新しい概念や制度を表す言葉をそのまま借用する傾向が見られました。たとえば「committee → komite」「billet → bilet」「gare → gar」といった形です。
共和国期にはラテン文字改革が行われ、こうした借用語が新しい表記体系の中で「正規の語彙」として定着していきました。
つまり、日本語は「自国語の体系に組み込む翻訳路線」、トルコ語は「外来語を音と綴りごと取り込む借用路線」という、対照的な道をたどったと言えます。
言葉の残り方に表れる近代化の道筋
こうした違いは単なる言語の癖ではなく、近代化の進め方の違いを反映しているようにも見えます。
日本は、天皇制を継承しながら近代国家を築きました。そのため「自由」「経済」「社会」といった翻訳語を創出し、自国語の体系を保ったうえで新しい概念を吸収する方向に進みました。
翻訳語は、いまや外来語に見えないほど自然に日本語に根づいています。
一方のトルコは、オスマン帝国との断絶を強く意識して共和国を出発させました。ラテン文字改革や語彙純化運動が行われたにもかかわらず、フランス語の借用語は「近代的で洗練された響き」を帯びたまま残りました。
イスタンブールからアンカラへの遷都と同じく、過去との距離を取ろうとする姿勢の象徴と見ることもできるでしょう。
もちろん、翻訳語や借用語の定着には知識人の活動や教育制度、外国文化の威信など多様な要因が影響しています。
それでも、両国の歩んだ近代化の道筋と、言葉の残り方が響き合っている点は興味深い対照だと言えます。
ちょっとユニークな借用語の例
借用語の中には、その国ならではの意味合いに変化して定着したものもあります。
たとえばトルコ語の「フィルターコーヒー(filtre kahve)」は、フランス語のfiltreとトルコ語のkahveを組み合わせた表現です。日本語の「シュークリーム(chou cream)」も同じように、フランス語のchou(シュー生地)と英語の cream を掛け合わせた和製表現です。
どちらも本来のフランス語圏では通じにくい言葉ですが、それぞれの国で独自の文化とともに定着しています。

ちなみにシュークリームはフランス語だと「chou à la crème」、英語だと「cream puff」と呼びます。へぇー。
こうした「借用+現地化」の言葉は、単なる外来語ではなく、その国の生活習慣や嗜好と深く結びついた文化の断片でもあるのです。
まとめ:街角のフランス語から見える国際史
ここまで見てきたように、借用語は単なる雑学ではありません。
トルコ語に残るフランス語は、かつてフランス語が「国際語」として力を持っていた時代の痕跡であり、「近代化」のプロセスの名残りと言うこともできそうです。
そして、日本とトルコを並べてみると、同じ「近代化」のプロセスでも翻訳語と借用語という異なる道を歩んできたことが見えてきます。小さな違和感を調べてみるだけで、言葉の背景に広がる国際史が見えてくるのです。
街角で耳にする何気ない言葉の中に、トルコの近代化の歴史が刻まれている…そう考えると、日常語彙がちょっと違って聞こえてくる気がします。
学術的な裏付けがあるわけではありませんが、外国語を学んでいるとこんなアナロジーに行きつくことがあります。 旅や文化理解に彩りを添えてくれますね。
個人的には、かつて国際連盟の本部が置かれ、フランス語が国際語として使われていたジュネーヴとのつながりを強く感じました。
私が学んだIHEID(ジュネーヴ国際・開発研究大学院)はもともと国際連盟職員を養成するために設立された教育機関で、今でも英語とフランス語の両方が主な言語として使われています。
そうした環境に身を置いていたからこそ、街角の借用語や国際語の歴史に、不思議な「空気の濃さ」を感じるのかもしれません。
以上です。
-1.png)
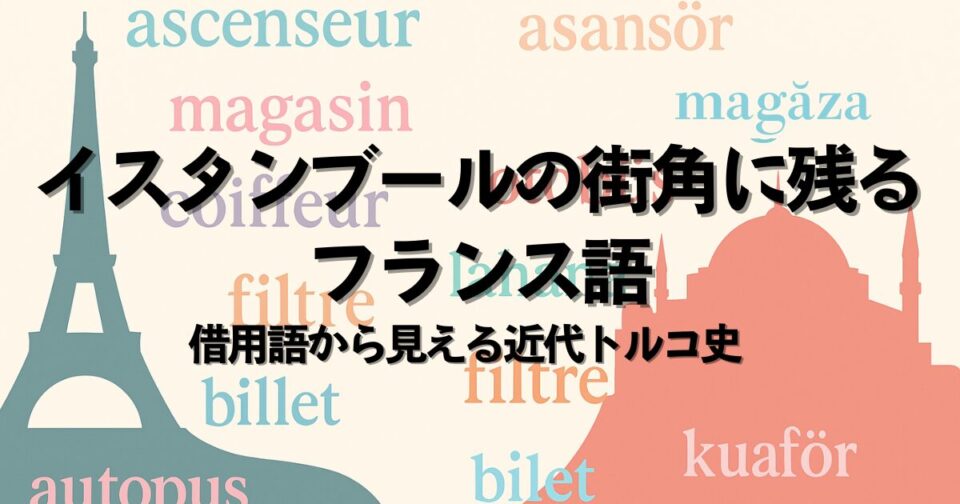
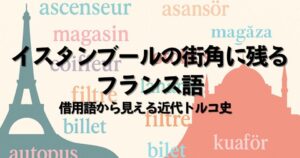
コメント