日本で社会人としてある程度のキャリアを築いた後、思うところがあって30代後半で海外大学院に挑むという選択した筆者。
後悔のないようじっくりと長い時間を掛けてちゃんと考えて決めた留学ではありましたが、留学が開始してからも、「本当にやり切れるのかな?」「途中でお金が尽きたらどうしよう」「卒業後はどうなるのかな?」など、年齢以外にも様々な不安に襲われることが多かったです。
先日、そんな大学院を無事に修了することができました。
それも(自分としては)悪くない成績で。
本記事では、大学院留学を終えた今、学び・生活・葛藤を振り返りながら、年齢を重ねてからの留学の厳しさ、そして年齢を重ねたからこそ見えた世界を整理し、これから挑む人に伝えたいメッセージを綴りたいと思います。
一歩を踏み出そうか迷っている誰かにとって参考になれば。
そして、あの頃の自分を静かにねぎらう意味も込めて。
大学院留学で得たもの

大学院留学で得たものは、やはりキャリア展望の広がり。具体的なポジションに手が届く感覚が得られたとともに、ある意味での図太さや語学力を含む生活力が向上したという点も大きな収穫でした。
なかにはミッドキャリアで留学したからこそ経験できたこともありました。
キャリアの選択肢が増えた
日本ではゼネラリスト的な「広く浅く」のスキルを身に着けてきた筆者でしたが、大学院での学びを通じて、自分が進める専門性の幅がぐっと広がった感覚があります。
特にジュネーヴでは日本で働いていた頃には想像もしていなかった国際機関の実情や多国籍・多言語の環境に触れることができて、世の中には本当にいろんな人がいるなあと素直に思ったことを覚えています。
キャリアパスどころか考え方も住環境もバラバラ。
順調に進んできた人も紆余曲折あった人も、なんだかんだ言ってキャリアへの不安を抱えている。
「最初はすごい人がいっぱいいる!自分には無理!」という感覚だけが先行していましたが、留学が中盤に差し掛かり終盤に向かっていくなかで、次第に「みんな多かれ少なかれ葛藤を抱えている」のだ、ということが分かってきました。
また日本では専門性の不足に悩んでいた筆者でしたが、専門性があってもどうにもならないという状況や、専門性の性質によっては逆に道が極端に狭くなってしまうという現実に触れることで、これまで以上に多様な生き方について考えるようになりました。
もちろん多様なキャリアを知ることや修士号を得ることそのものがプラチナチケットになるわけではありません。
ですが、これまでの日本における「ゼネラリスト」のキャリアの積み重ねだけではきっと到達できなかった、国際課題に直結する専門性を身に着けられる「スペシャリスト」の世界への入り口には確かに立つことができたという実感があります。
自信がついた
留学前はとにかく「自分にできるのかな?」という疑問ばかりが浮かんでいた筆者でしたが、留学を通じて自分に自信を持つことができるようになりました(まあ確固たる自信というよりも根拠がない自信も結構あるのですが)。
思い出すのは、学部時代に語学力や金銭面などの理由で留学をためらっていた自分。
シンガポール駐在も、実力で勝ち取ったというよりは「どこかから降ってきた」ような感覚。
英語はある程度できるとはいえ、ネイティブレベルの若者と教室で討論するなんて到底無理だと思っていたし、リーディングも読みこなせる気がしません。
しかもジュネーヴでは生きているだけで貯金がガンガン減っていく。
何度、円安基調や日銀の政策を恨んだことか…。
それでも、人間は簡単には死なないものです(少なくとも死ぬほど恥ずかしい経験を繰り返すくらいでは)。
完璧にできなくても折り合いをつけられる。それが分かりました。
大学院の授業では英語がめちゃくちゃでも誰も笑ったりせず、不明瞭な部分は質問してくれたり、むしろ深掘りしてくれたりします。どんな意見であっても尊重される。
そして、短期的に食べる量を減らしても死なない(笑)。
そんな「意外と自分できるじゃん」「どこでも生きていけそう」という感覚は、これまで囚われていたマインドブロックを取り払い、「できない自分」ばかり見ていた視点を「これもできた」「あれもできた」という肯定的な方向に変えてくれました。
語学力(&生活力)が上がった
留学生活を通じて最も変わったのは、語学力と生活力の向上です。その結果、「どうにかすれば何とかなる」「何とかしようとすれば何とかできる」という感覚をつかむことができました。
膨大なリーディングをこなしたり、ちょっと自信のあった課題に厳しい評価を受けたり、授業中に言いたいことが上手く伝えられなかったり…。語学については実践の機会まみれで、否応なく力が鍛えられます。
教室を出れば、今度はフランス語の世界。日常生活から行政手続きまでほぼすべてがフランス語なので、サバイバル力が自然と上がっていきました。交換留学先にフランスを選び、ジュネーヴでもフランス語生活を継続できたのも大きかったと思います。
生活面でも、以下のような「現実」に直面しました。
- 日曜日になるとバスの本数が激減する
- 自炊しないとすぐに破産するほど物価が高い
- 娯楽がほとんどなく、外の楽しみに頼らない生活を強いられる
もちろん想定はしていましたが、やっぱり情報として知っているだけでは足りません。
実際に体験してみて「自分はどう思うのか」「耐えられるのか」を初めて実感することになりました。

この経験をするまでは、自分がここまで都市志向だという自覚は全くありませんでした。
結果的に「これまでの生活がどれだけ物質的に恵まれていたか」を思い知ると同時に、国や地域ごとに生活スタイルがなぜここまで違うのかを考えるようになりました。
そして「自分が本当に身を置きたい世界はどこか」「自分にとって生活インフラの優先順位は何か」を意識する習慣ができたのです。
人脈が広がり、国際機関や海外就職のリアルを知ることができた
大学院に在籍することで、多彩なクラスメートや教授陣と交流する機会を得ました。
さらに事前にキャリアを積んでいたおかげでジュネーヴやヨーロッパで働く人々にもアクセスしやすく、ミッドキャリア特有の事情や厳しさなど、生々しい話を直接聞ける機会も多かったです。
交換留学先のリヨンでも同様。むしろビジネススクールという環境もあり、同年代の大学教授とフランクに話すことができ、教授法やフランスの大学院が抱える問題点まで議論する場面もありました。職業人生活とか生き方とかについて話すなんて、この年齢で留学しない限りはできないと思います。
同時に、雲の上の存在だった国際機関職員は、実際に話してみると同じようにキャリアに悩む仲間でもあることが分かって、親しみを覚えました。歩んだ道筋は全く違うものの、共感できる部分も多く、かつて日本で公務員を目指していた頃に職員が眩しく見えた感覚を思い出しつつ、その憧れが更新されていく不思議な感覚も味わいました。
こうして華やかに見えるキャリアの裏側にある葛藤も知ることができ、自分のキャリアを考える上でより現実的な視点が持てるようになりました。
これらの人脈はジュネーヴを離れても途切れるものではなく、今後も自分次第で学びの場として広がり続けると感じています。
想像していたのと違ったこと
大学院留学では、あまり聞かれないギャップや想像と異なる現実にも遭遇することになりました。
この項目では、そんな「あれ?思っていたのと違う?」と感じたことを何点かご紹介します。
ヨーロッパ中心的な空気
留学前は「国連のヨーロッパ本部が置かれているジュネーヴ」「学生の大半が留学生」という条件から、プログラムは非常に国際的だろうとイメージしていました。
実際、学生の出身国は多彩です。アジア圏からの留学生も多く、国際機関に関心を持つ学生が集まるため、雰囲気はリベラルで国際的。ただし実態は、中国人留学生が大半を占め、東南アジアや中東からの学生はごく少数派でした。これは、ビジネススクールにインド人学生が多くいたのと対照的です。
しかし、学業面では国際性や多様性にやや疑問符が付く場面も。
例えば、授業前に課されるリーディングの内容や教授の見方がヨーロッパやアメリカの視点に偏っていると感じることが多々ありました。授業やフォーラムなどではグローバルサウス、AI、ガザ問題、ウクライナ紛争など最新のトピックも扱われますが、その解釈や議論の軸足もどうしてもヨーロッパ的になりがち。
もちろん学術という面からはリーディングに欧米発の古典や資料が多く含まれるのがある程度仕方ない点は理解していますが、それにしても理論展開や教授の関心がヨーロッパ出身の学生に親和的に働いている印象を受けました。
自分を含めた非欧米出身の学生が発言しても、しばしば周囲の学生や教授が「?」という表情を浮かべ、議論がなかなか広がらない場面もありました(例えば日本の雇用法制とか歴史に関連するような話題。ノーマークなのは分かるのですが)。
「本当の意味でグローバル」「中立的」というのは、やはり理想であって現実は難しいのだな、と痛感しました。
結局は国籍・人種ごとに固まってしまう
海外留学といえば、現地や様々な国籍の友人ができて、ちょっとした文化体験もできる…そんなイメージをほんのり持っていました。シンガポールでは当然のようにアジア人が中心でしたが、今回はスイス。ヨーロッパやアメリカの友達が一気に増えるのでは、と期待していました。
ただ実際には、人種や出身地域ごとに自然とグループができてしまいます。
もちろん国籍を超えて仲良くなることはありますが、完全に混ざり合ってフラットな関係はなかなかできません。さらに属性の異なる集団に積極的に絡みに行く人は意外と少なく、二十歳そこそこの若者でもそうなのはさらに衝撃でした。
やっぱり大事なのは「馬が合うかどうか」や「一緒にいて快適かどうか」。
これはジュネーヴを含め万国共通であることを痛感しました。
また、様々な国籍の学生がいるなかでも、中国人学生やインド人学生が常につるんでいたのが印象的でした。
日本人はそもそも少なく私自身もそこまで一緒に行動することはなかったため、余計にそう見えたのかもしれませんが。
結局のところ、思っていたほど「親しい友達ができた」とは言えないのが正直な感想。
夢を見過ぎず、自分のステージに集中すべき。そう思うようになりました。
若者の成熟度は意外と普通
アジアにいたときは「海外(特に欧米)の若者=早熟で自立している」という先入観がありました。
確かに修士課程や博士課程に進んでいる若者は考えが非常にしっかりしており、問題意識も非常に高い優秀な学生ばかり。
さすがにわざわざハイレベルな教育機関に学びに来るだけはある、といった感じです。
ただ実際に一緒に学ぶと、考え方や行動が年相応な側面も見えてきました。
明らかな机上の空論や理想論を声高に語っていたり、議論の内容が浅かったり、責任感が不足しているように見えたり。日本の若者とそこまで大差ないところが見えて親近感を覚えたりもしました(自分の黒歴史もちょっと思い出したのは内緒)。
一方で、日本と大きく異なるのが、年上だというだけではリスペクトされたり距離感が生じたりはしないこと。フラットに意見をぶつけ合える自由さはあったのは、授業などで考えを深めるには良い環境でした。
とはいえその分、30代後半の自分にとっては「軽んじられている」と感じる場面もあり、正直イラッとしたことも結構ありました。
結果的に幻想は崩れましたが、同時に「同じ人間」という当たり前の事実を肌で感じられたのは貴重でした。
楽しかったこと・辛かったこと
まずは楽しかったことから。
学ぶって面白い
留学で最も楽しかったのは、やはり「学ぶこと」そのもの。
社会人経験を経てからの勉強では、論文に書かれた理論とこれまでの実務経験が結びつき、点と点が繋がって線になるような感覚を何度も味わいました。
若いときと比べると理解力や吸収力は多少落ちているかもしれませんが、事例の蓄積や現場感覚で補うことができましたし、課題やプレゼンでは経験があるからこそむしろアイデアをスムーズに出せる場面も多かったです。
ジュネーヴという土地の利点を活かして、UNHCRなど国際機関の研究に取り組んだり、WHO会議の関連イベントに参加できたのも貴重な体験でした。現地でなければ得られない刺激です。
また、分野によっては「新しい知識なのにどこかで聞いたことがある」と感じることもありました。
キャリアを起点に新しいことを学び、そこからさらに発想を広げていく過程は非常に面白かったです。
授業で得た知識が自分の経験と結びつき、理解が深まっていく感覚は格別でした。
憧れのヨーロッパ生活
もう一つ楽しかったのは、ずっと憧れていたヨーロッパでの暮らし。
週末の旅行や街並み、カフェ文化や美術館めぐり…。留学前にも何度もヨーロッパを旅行で訪れていましたが、やはり旅行者としての滞在と「住む」こととでは感覚がまったく違いました。
短期滞在のときはお土産として買っていたジャムやバターも、こちらでは日常使いに。スーパーでの自炊、トラムやバスでの通学といった生活の一つひとつが、アジアとはまるで違う文化を味わう時間になりました。
また、季節ごとの日照時間の大きな変化のように、短期滞在では気づけない季節の移ろいを感じられたのも貴重な体験です。
海外暮らしの解放感以上に、「ずっと来たかった環境に実際に身を置いている」という不思議な感覚を味わえたことを、今でも鮮明に覚えています。
続いて、辛かったこと。こっちの方が多いかもしれません。笑
物価の高さ
辛かったこととしてまず挙げられるのが、生活費の高さです。
ジュネーヴは家賃をはじめ、あらゆるものが桁違い。日々のやりくりに頭を悩ませました。
それはもう…日本が貧しくなったことを痛感する日々。
銀行の残高がものすごい勢いで減っていくのは、恐怖でしかありませんでした。自分で決めた大学院留学とはいえ、各種手当で潤っていた駐在時代と比べると、寂しい気持ちになることは数えきれません。
最初は面倒だったフランスへの買い出しも、気づけばすっかり日々のルーティンになっていました。
自分ですら大変だったのですから、若くしてジュネーヴに来ている学生たちの苦労は計り知れません。奨学金で賄っているか、あるいは生活を切り詰めているのか…。
自分が同じくらいの年齢のときに何をしていたかを思うと、素直に尊敬してしまいます。
外国語で学ぶ難しさ
授業も課題も日常生活も、当然ながらすべてが外国語。
英語とフランス語が入り混じる環境は初めてだったので、戸惑いの連続でした。
日常生活は何とかこなせても、やはり学業面では苦労が絶えません。理解や表現にハンディがある分、ただ思ったことを話してもほとんど伝わらない。
様々な表現を試したり、具体例を挙げたりと工夫はしましたが、それでも十分に伝わらないことは日常茶飯事でした。
レクチャーも完全に理解できているか自信が持てず、発言するたびに「的外れではないか」と不安になることも。
気にしすぎても仕方ないので意識的に考えすぎないようにしましたが、反応が薄いと落ち込む瞬間もありました。
英語圏出身者は多くないにもかかわらず、皆堂々と発言している。
その姿は本当に素晴らしく、母国語で話せる強みを心底羨ましく感じた場面も多かったです。
とはいえ、クラスで恥をかいたり歯がゆい思いをしたりするのも、いきなり海外転職して失敗するよりはずっとマシ。振り返れば、確実に自分を鍛えてくれた良い訓練の機会だったと思います。
若者とのギャップ
そして地味に堪えたのが、若者との世代ギャップです。
ノリや流行といった分かりやすい違いだけでなく、認識や考え方、知識量の差など、細かい部分でも隔たりを感じることがありました。年齢を理由に遠ざけられることはないものの、その分、居心地の悪さを覚えることも少なくありません。
アジアでは年齢ごとに自然と集団を作りがちで、それはそれで嫌だと思っていたのですが、改めて考えると合理的な面もあったのだと痛感しました。
ジュネーヴではその程度でしたが、リヨンの交換留学中に受けたバドミントンの授業では別の意味で大変でした。20歳そこそこの学生と同じメニューでトレーニングをしたり、課題をこなしたりするのは正直厳しく、先生に相談して出場する試合数を減らしてもらったり、休憩時間を増やしてもらったりしました。
アジア人は実年齢より若く見られるので、きちんと伝えておかないと本当に大変なことになります。
…とはいえ、振り返ってみればこれも良い経験でした。
この年齢で行って良かった?
やっぱり早いに越したことはない
正直に言えば、留学は若ければ若いほど良いと思います。
時間の余裕、柔軟な思考力、体力や順応性―どれをとっても若い方が有利です。
そして就職市場に戻るときのリスクも低く、人生の選択肢も広がりやすい。特に国際機関はコネ社会の側面が強く、若いうちにどこかに入ってしまえば自然に人脈が広がり、その構造の中に入ることができます。
国際機関に入るには専門性が第一だと考えていた自分にとって、「コネが専門性と同じか、それ以上に重要な場面がある」という現実を知ったときはなかなか受け入れられませんでした。コネがあればポジションを作ってもらえることがある…そんな衝撃の事例を見聞きしてショックを受けたこともあります。
ミッドキャリアで外部から国際機関に入るルートの厳しさは、「国連の働き方を知らない」こと以上に「国連の人を知らない」ことにある。そう痛感しました。
さらに制度面でも、JPOやYPPといった年齢制限付きの枠を利用できるのは若者だけ。
やはり早く海外に出ることの重要性を、身をもって知ることになりました。
同じプログラムで学んでいた20代の学生が羨ましく思えた瞬間は、数えきれないほどあります。
日本型雇用をどれだけ経験しても、国際機関で評価される専門性には接続できない。残念ながらこれが現実でした。
もし20代前半の自分にアドバイスできるなら、語学力を徹底的に鍛えたうえで、貸与でもいいから奨学金に片っ端から申し込み、さっさと大学院留学に挑戦しろ、と発破をかけたいですね。
今はトビタテ留学Japanのような制度もあるので、良い時代になったと思います…。
国際機関就職にはほぼ無意味
前述の内容を踏まえて正直に言えば、国際機関を目指して30代後半で修士課程に進むことは、国際機関への就職という選択はほぼ意味をもちません。このルートが意味を持つのは、JPOやYPPの受験資格(遅くても30代前半まで)と職歴(3年くらいの専門職歴)が噛み合う20代後半~30代前半まで、というのが筆者の個人的な結論です。
ミッドキャリアのポジション(経験5年~)は既に国際機関で働いている人が(暗黙的に)対象になっているため、一見役立つ経験を持っていても外部から入るのはほぼ無理です(もちろんそれまでのキャリアや応募する職種によります。特に特殊な技術職はこの限りではありません)。
つまり、ミッドキャリア留学は「これから進みたい方向性を明確にしたり、専門性の強化にはつながる」ものの、いずれにしても「非常に高い採用システムの構造的ハードル」を崩すまでには至りません。
多くのポジションが「修士号取得者」とあわせて「学士号取得+職務経験」を条件にしているのは、単なる経験年数ではなく「そのシステムの内部にいること」を暗に指していたといえるでしょう。
つまり、日本語を母語とする日本人の場合、ほんの一握りの
・国際機関に遅くても20代前半までには関心を持っている
・実際に国際機関に接続できるだけの学歴を積む能力と財力がある(実家が太い)
・国際機関に必要な専門性を積めるフィールドにいる(専門外の経験を積ませる日本型雇用はアウト)
という非常に恵まれた人々でなければ国際機関の正規ポジションを得るのはほぼ不可能、という現実が見えました。
もちろん、学位そのものは無駄にはなりません。国際機関という形式面が気にならないのなら、本質的に何かに貢献する道を目指すことは可能でしょう。しかし、「修士を取れば国際機関に入れる」という単純な話では決してない。むしろ、国際機関というキャリア展望を考えるなら、学位以上に「経験」「ネットワーク」「タイミング」が圧倒的に重要であることを突きつけられました。
空席公募で職を得たというよくある体験談はまさに生存者バイアスのたまものであり、鵜呑みにしてはいけない。彼らの職歴やキャリアを見れば、その時点で既に非凡なことが多いです。
その背後には無数の「敗北者」がいることは想像に難くありません。
分かってはいたものの、自分がその「行けなかった側」にいる、という現実はなかなかに堪えます。でも恨み言を吐いていても何も変わらない。国際機関という方向性は無理そうなことが良く分かったので、これから改めて別のルートを模索していくことになると思います。
でもミッドキャリアだから得られた強みも多かった
とはいえ、30代後半で行ったからこそ得られた強みも確かにありました。
社会人経験と知識の蓄積があることで、学んだ理論をすぐに現実と照らし合わせて理解できたり、課題や議論の場で実例を交えて説得力を持たせられたり。学習の対象が「社会そのもの」であったことも大きいでしょう。
もし自然科学分野を専攻していたら、このように思えたかどうかは正直分かりません。
また、キャリアを積んでいたからこそ、教授や実務家とのネットワークにもアクセスしやすい面もありました。
そこで得られたのは、他ではなかなか聞けない生々しいエピソードや、国際協力の厳しい現実。
若い学生が聞いたら幻滅してしまいそうな話も、キャリアを積んできたからこそ受け止められたのだと思います。
加えて、自分で稼いだお金で留学する責任と自由を実感できたのも大きなポイントでした。
これまでの異動や配置転換のように「誰かにコントロールされている」感覚とは違い、自分で選び取ったという実感は、今後のキャリアを考えるうえでかけがえのない財産になりました。
そして、大学院に行く前にすでにある程度キャリアを積んでいるからこそ、卒業後のキャリアは必ずしも専攻分野に縛られません。
もし国際機関の道が難しくても、キャリアが行き止まりになるわけではない。
そんな「余裕」を持てたことも、ミッドキャリアで留学したからこその安心材料でした。
もしやり直すなら?
自炊をもっと工夫する
ジュネーヴの物価は本当に高く、外食はほとんどできません。
マクドナルドですら10フランほどかかる世界のインパクトは想像以上でした(もちろん財布にもインパクト)。
そのうえで思うのが、最初からもっとアジア食に頼らない自炊に慣れておけば、出費を抑えつつ健康的に過ごせたはずだということです。
お米や豆腐のようなアジア食は恋しくなりますが、やっぱりパンとパスタ中心の生活に慣れることが重要でした。
このコスト感は、卒業間際にアジア食ほぼゼロで数ヵ月フランスに滞在して初めて現実として認識できました。
自分が食にこだわるタイプなのかどうか…。結論としては、徹底的にこだわるタイプでない限り、事情があれば意外と耐えられるのでは?と思います。
炊飯器を買ってジュネーヴで自炊していたときは日本と変わらない食生活でしたが、フランス滞在中はお米が炊けずパン&パスタ生活。それでも何とかなった自分に驚きました。
「自分の食生活はこうあるべき!」という思い込みは、意外と強いのかもしれない。そう感じました。
もしやり直せるなら、お米とかアジア食はある程度封印してまずはヨーロッパ食で頑張る!みたいな戦略を立てるかもしれません。
無理に若者に合わせない
最初は「せっかくだから若い学生たちと一緒に過ごさなければ」と思っていましたが、今振り返ると、無理に合わせる必要はなかったかも。
もちろん人によりますが、筆者にとってはかなり厳しかった。
前述のとおり何もかも違いすぎて、努力しても空回りばかり。
きっと「外国人の友達に囲まれて充実した留学!」という、どこかで刷り込まれたイメージを無意識に再現しようとしていたのでしょう。日本にはそういう題材の漫画や映画も多いですし…。
結局「頑張る必要がない」と気づいたのは、留学も後半に入ってから。
スタートラインが違ううえに、「年齢を気にする文化」と「年齢を気にしない文化」の溝は、おそらく前者に属する人間(つまり自分)にしか見えない、という事実に思い至ったとき、こちら側だけ努力する必要はない、という結論に至りました。
そんな風に割り切っていても、心のどこかで「その口のきき方は何?」とか「本当なら君の上司でもおかしくないよ?」と考えてしまう…何というアジア脳。そんな思考を抱えながら若いテンションで頑張り続けるのは、一方的に精神をすり減らすだけで、得られるものは何もありません。
そう気づいてからは、気乗りしないお付き合いはスッパリやめました。
そして思い起こすと、むしろ同年代やちょっと上の世代の社会人経験者と過ごす時間の方が居心地が良く、学びも多かったように思います。
無理をする人間関係は長く続かない。
日本やシンガポールで散々学んだはずなのに、ヨーロッパに来てすっかり忘れていた教訓でした。
もしやり直せるなら、頑張って輪に入ろうとせず、もっと自然体で構えていたと思います。
それでも、意外と孤独にはならない気がしますし。
就活をもっと早めに
就職活動の開始時期にも、少し後悔が残っています。
留学中は「せっかく来たのだから学業に集中したい」と考えて、就活は後回しにしていました。けれど、応募だけでももう少し早めに始めておけばよかったと思います。
学業との両立を心配していたのですが、今振り返れば「そんなにすぐ決まらないから大丈夫」と当時の自分に言いたい気分です。この点については情報不足もありました。たとえば「正規ポジションに就職した場合は修論のスケジュールが調整できる」といったことを知らなかったのです。
ミッドキャリアの学生は少なく、流通している情報が圧倒的に不足しているので、自分から積極的に取りにいかなければならなかったと痛感しました。
また、国際機関や欧州での就職に時間がかかることは分かっていましたが、最初から就職を想定していたことを考えると、1年目から本腰を入れて動いていてもよかったと思います。そうしていれば、インターンシップが自分に合わないことももっと早く気づけて、応募件数を効率化できたかもしれません。
とはいえ在学中から就活に取り組めたのは事実で、結果的にそこまで大きな後悔ではありません。
けれど「もう少し早く始めればよかった」という気持ちはやはり残ります。
今の気持ち
自分で行動し、成し遂げた達成感
まず感じているのが、自分で決断し、自分の力で行動し、最後までやり遂げた達成感です。
ずっとやってみたかったけれど若い頃にはできなかったことを、30代後半になってようやく実現できた。その事実は、この先のキャリアや人生において、何よりの支えになるはずだと思います。
今もアプライ作業は続いていますが、CVを書き直すたびに「これまでの経験が形になった」という小さな満足感が積み重なり、現実はままならなくても確かな自信へと変わりつつあります。
「終わった」感覚と空白
卒業証書を受け取った瞬間の解放感は大きかったものの、そのあとに訪れたのはむしろ空白でした。
「終わった」という感覚とともに、日々を埋めていた課題や試験がなくなり、急に手持ち無沙汰に。ヨーロッパの風景も日本の風景も少しだけ違って見えて、燃え尽き感に近い心境になることもあります。
ジュネーヴで過ごした日々が本当に現実だったのか、それとも夢だったのか…そんな不思議な感覚にとらわれることさえあります。
けれど、この「空白」は次に進むための余白でもあるのだろうと、時間が経つにつれて思うようになりました。
駐在帰国との違い
ただし、喪失感を強く感じたシンガポール駐在からの本帰国のときと違い、今回は「やり切った」という感覚が強く残っています。
駐在はあくまで与えられた任務を果たす時間でしたが、大学院留学は自分で選び、自分の意思で掴みに行ったもの。駐在が終わると元いた場所に戻るか、せいぜい同業種への転職にとどまることが多く、「終わってしまった」という感覚になりがちです。
一方、留学では自分で選んだ専門性が積み上がっていくため、むしろ選択肢が広がった実感があります。
卒業生コミュニティに入れることもあり、「まだまだこれから」という気持ちを抱けるのも大きな違いです。
だからこそ、積み重ねた学びや経験が「自分に蓄積された」とはっきり感じられ、次のステージに向けて背中を押してくれています。

まとめ
30代後半での大学院留学は、想像以上に大変で、想像以上に得るものも大きな経験でした。
理想が崩壊したり、逆に現実が理想を超えてきたり。これまで抱いたことのない感情に出会い、やったことのなかった行動に挑戦し、本当に色々なことを学ぶことができました。
このブログを始めたことも、気が付けば留学を形として残す一つの目的になっていました。
学びの楽しさやヨーロッパでの暮らしはかけがえのないものであり、一方で物価や言語、世代差といった壁にも直面し、これまで以上に世界のリアルが身近になったように感じています。
もっと若ければ…とつい思うこともありますが、やっぱり留学の年齢そのものに正解・不正解はないのでしょう。自分の人生をある程度かけることに納得できれば、それはきっと意味があることだと思います(投資した時間や金額を考えると、これからはサンクコストバイアスとの戦いが待っていそうですが…笑)。
留学は一度きりのイベントではなく、その後のキャリアや生活に形を変えて続いていくもの。留学中はそれまでのキャリアや知識それぞれの「点」が結びついて「線」になる過程を味わいましたが、これからのキャリアでは、きっと留学が新しい「点」になり、見たことのない「線」が出来上がっていくことでしょう。
今回の経験を「これからどう活かしていくか」は、これからの人生で自分に問い続けていくことになると思います。
結局は全て自分次第、ということですね。
この留学がこれからのキャリアや人生をどこに連れて行ってくれるのか、今から楽しみにしています。
以上です。
各セメスターの振り返り記事はこちらです。
・第1セメスター(ジュネーヴ)中間
・第1セメスター(ジュネーヴ)総括
・第2セメスター(ジュネーヴ)総括
・第3セメスター(リヨン交換留学)総括
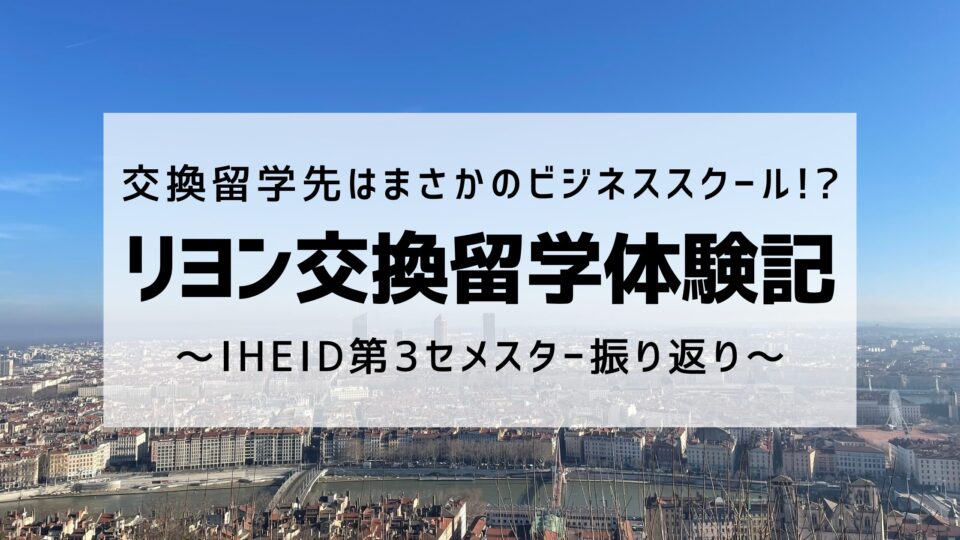
・第4セメスター(ジュネーヴ)総括
-1.png)
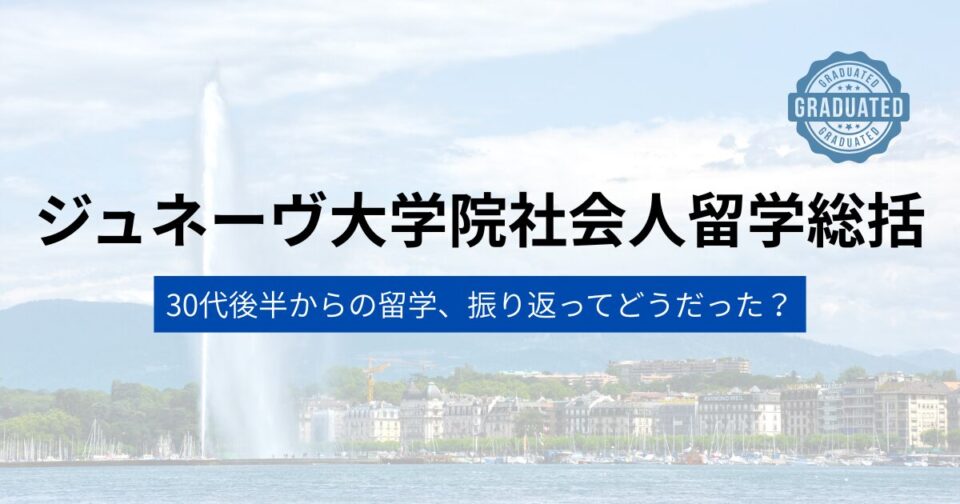

コメント
コメント一覧 (4件)
こんにちは、2011年にIHEID卒業し、国際機関で働いたものの何でもかんでも欧米のダブルスタンダードが嫌になって現在ロシアモスクワで金融業に従事するものです
2年間を振り返っての記事、本当に同感したところが沢山ありました。IHEIDって欧米中心過ぎな視点が多すぎますよね。在学中本当にうんざりしたことが沢山ありました。私の頃は1フラン90円だったので、今留学は本当に大変だったと思います。
御卒業後は進路はどちらに進みましたでしょうか?11月から一時帰国しますのでもしお時間合えばぜひ都内でお話しできれば幸いです。同じ時期に博士留学していた友人も招きたいと思います(彼女も私と同じ意見です)
https://note.com/mikitsuda
コメントありがとうございます!同じIHEIDご卒業生の方からのご感想、とても嬉しく拝読しました。おっしゃる通り、欧米中心的な視点には私も違和感を覚える場面が多く、共感していただけたことは大変心強いです。
ご質問いただいた進路については、現在は求職活動を進めつつ、執筆やブログ運営などにも取り組んでおります。
都内でのお誘いについてもお気遣いありがとうございます。ただ現状はなかなか予定が合わず、直接お会いするのは難しそうです。今後も記事を通じて交流できれば幸いです。
ヨーロッパ中心主義な授業内容は私も非常にがっかりでしたし、教授のアジア蔑視的な発言で私も嫌になったこと何度もありました。たしかに同じ地域で固まってしまいますよね、でもそれはそれでよかったかなと思っています。私がいたころはもっとヨーロッパ中心主義で、学生から批判がありまだ最近は緩和されたとは聞きますが、10年近くたっても変わっていないのは仕方ないですよね。
私の方はモスクワでドイツ人の方と同窓会支部長をしておりますが、ウクライナ情勢もありスイス大使館からのゴーサインがなかなか出ず、頻繁に同窓会ができないのがネックです。こんな時こそ国籍超えてロシアの政府機関で勤務される方やわれわれ外国人で民間企業の方と積極的に同窓会出来ればそれこそいいシナジーになると思うのですが。
miki.tsuda@大学院のメールでお返事いただければ幸いです!
ご経験を共有いただき、ありがとうございます。10年経っても状況が変わっていないのはなかなかもどかしいものがありますね…。
同窓会活動のお話も大変興味深く伺いました。なかなか難しい情勢なのは当方も感じているところです。
現状ブログを経由しての個別のやり取りは控えておりますが、また機会があれば同窓会などを通じて交流できれば嬉しく思います。