近年、世界の様々な場所でみられる気候変動の影響。
そのなかでも特に深刻で“命の危険を伴う災害”と化しつつあるのが、欧州の猛暑です。
多くの産業が気候変動対策(気候変動の防止と適応)に取り組んでいますが、コスト、文化的背景、社会制度など様々な要因が重なり、十分な対応が取られているとは言い難い状況です。
中でも宿泊業は旅行者の健康や安全に直結する事業であり、宿泊先は旅の体験を大きく左右するだけでなく、災害リスクが高まるほど命を守る“シェルター”としての役割が重要になります。
その危険負担を巡る議論は、伝統的なホテルのみならず、Airbnbをはじめとする仲介プラットフォームにも及びますが、こうしたプラットフォームの責任範囲はいまだ曖昧。旅行者がリスクを一方的に負わされるケースも少なくありません。
気候変動がもたらすリスクの責任は一体誰が、どの程度負うべきなのでしょうか?
その地域の気候変動対策を担う政府?
施設を実際に運用する宿泊事業者や民泊オーナー?
それとも旅行者と宿泊施設のマッチングを担うAirbnbのようなグローバル・プラットフォーム?
本記事では、Airbnbトラブルの実例や各国での議論を手がかりに、“責任の空白”が生まれる仕組みと、気候変動時代の新たな消費者リスクについて分析します。
本記事の出発点になった筆者のAirbnbトラブル体験記はこちらのリンクからどうぞ(2回シリーズです)。
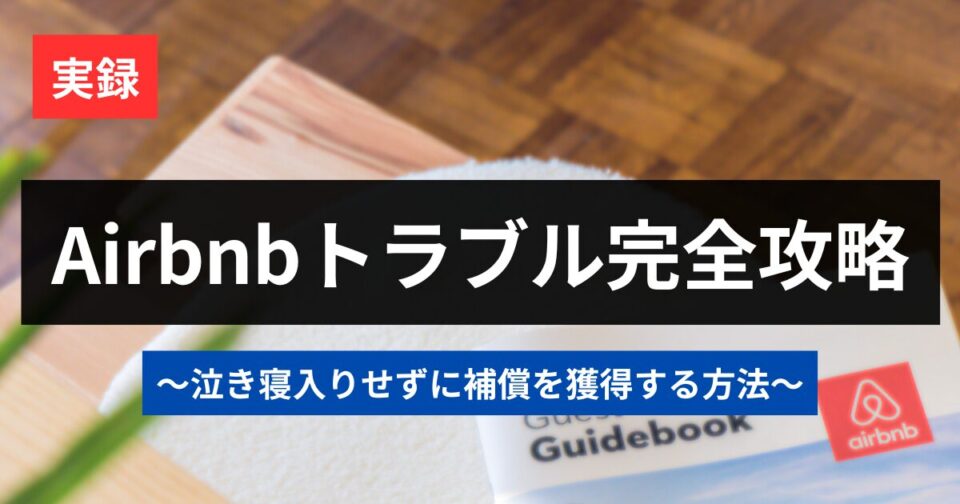
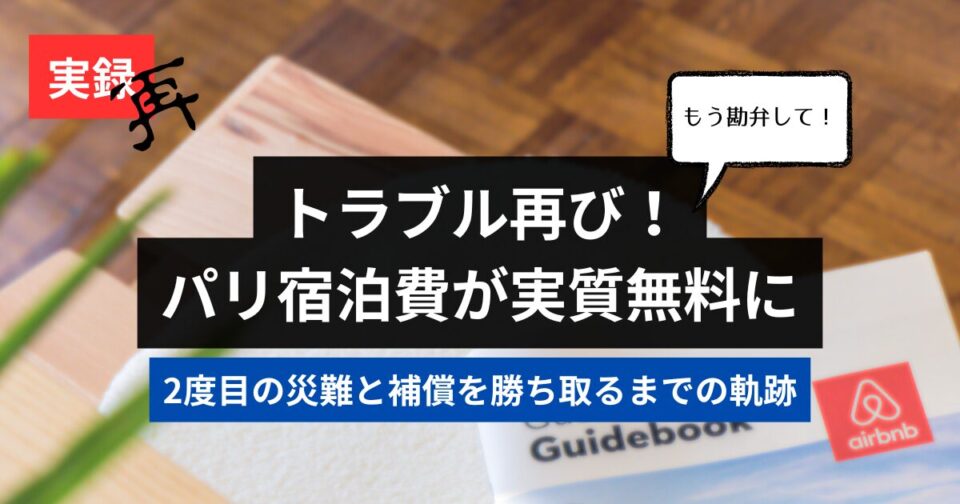
気候変動がもたらす観光業の「新たなリスク構造」
気候変動は環境問題の枠を超えて様々な影響をもたらしており、様々な事業が対応の必要性に迫られています。
この項目では、プラットフォームの責任について検討するためのベースとして、まずフランス・パリの気候変動対策や現状についてまとめ、そのうえで気候変動が事業にもたらす新たなリスクについて整理します。
猛暑とライフスタイルの変化
近年の欧州では、気候変動に起因する猛暑が「災害」としての様相を強めています。
2022年と2023年のヨーロッパ熱波では、フランスやスペイン、イタリアを中心に数万人規模の熱中症被害が報告され、公共交通機関の停止や電力供給の逼迫など都市インフラにも深刻な影響を与えました。

この異常気象は、日常生活だけでなく、欧州特有のレジャー文化にも大きな変化を迫っています。
これまで人々は夏になると避暑地に旅行したり、地中海沿岸のビーチでバカンスを楽しむのが定番でした。しかし、近年の極端な暑さは「楽しむ」レベルを超え、旅行者や住民の健康や生命に直接リスクを及ぼす状況を生んでいます。
観光業、とりわけ宿泊業にとって、この変化は深刻です。施設の冷房強化や断熱改修、非常時の対応体制整備など、これまで想定されていなかった「気候変動への適応コスト」が不可避になりつつあります。
観光ピークである7〜8月の猛暑が恒常化すれば、事業の安定性や収益性そのものが揺らぎかねません。
ヨーロッパの気候変動対策
EU全体としては長年、気候変動の「緩和(Mitigation)」、つまり温室効果ガス削減を最優先に政策を進めてきました。しかし、2022年・2023年の記録的な熱波を経て、「適応(Adaptation)」の必要性が急速に認識されるようになっています。近年では、熱中症被害の増加や都市インフラへの影響を背景に、都市レベルでの対策強化が進められています。
例えばフランス・パリ市では、2019年以降に猛暑対策計画を策定し、公共施設への冷房設置や、学校・図書館を「クーリングセンター」として開放する施策、街路樹の大規模植樹など、都市全体の温度を下げるための「Cool Islands」戦略が導入されています(→Climate Xの該当記事)。ただし、既存の宿泊施設や民泊に対しては、冷房設置の法的義務化や補助制度が未整備であり、対応は各オーナーやホテルチェーンの自主判断に委ねられているのが実情です。
さらにEU域内では、エネルギー消費削減を重視する文化的背景から、冷房利用を抑制する価値観が根強く存在します。冷房設備を一律に義務化すると脱炭素目標と衝突する懸念があり、都市ごとの対応は慎重な調整が続いています。
ヨーロッパで猛暑への対応が遅れる理由
ヨーロッパで猛暑への対応が遅れる理由には、根本的な建物の構造が影響しています。
欧州は基本的に寒冷地のため、多くの国々が長年にわたり断熱性を重視する「冬の寒さに対抗するための建築様式」を維持してきました。フランスにおいても古い石造りの建物が都市の中心部に多数残っており、断熱性は高い一方で通風性や冷房設備に乏しい住宅・施設が多く見られます。
さらに建物の構造以外でも、景観保護のための厳しい規制が猛暑対策を難しくしています。
例えばパリでは、歴史的景観の保護を重視するABF(Architectes des Bâtiments de France、「景観保護機関」とも)が、建物外観から見える形でのエアコン室外機の設置を原則禁止しており、特にオスマン様式のファサードが多い地区では新設が難しい状況です。
もちろんきちんとした手続きを踏めば室外機をファサードやバルコニー面にファサードに設置することは可能ですが、市への事前届出(déclaration préalable)が必要で、かつ集合住宅では建物管理組合の承認も求められるなど、手続きも煩雑。しかもこれらの手続きに不備があると、最悪罰金や設置の強制撤去につながるリスクがあります。
このような事情から、多く住民が移動式エアコン、窓用エアコン、扇風機、シャッターなどの室内対応に頼るという現状が見られます。

宿泊施設の構造的課題とリスク構造:迫られる対応と新たなコスト
観光業全体としても、気候変動の影響が「想定外の突発リスク」から「経営に直結する恒常リスク」へと変わりつつある中で、適応投資は避けられない時代に入りつつあります。
しかしながら観光業に目を転じると、ヨーロッパでは、ホテル・民泊ともに猛暑対策が標準化されておらず、以下の要因からエアコンの設置も進んでいません。
- 建物改修:古い石造建築や歴史的建物は断熱性が高い一方で通風が悪く、現代的な冷房設備を後付けするには大規模な工事が必要になる。
- 冷房導入:屋外機の設置規制や電力インフラの制約があり、特に都市中心部では冷房設備の整備に追加コストや許認可が伴う。
- 断熱強化・遮熱対策:屋根材や窓の入れ替え、遮光設備の追加など、熱波による屋内温度上昇を防ぐための建築改善投資が求められる。
現状は観光業に打撃を与えるほどの猛暑は年に数日間だけなのでエアコンや冷房設備を導入することによって付加価値を付けるか、その分料金を下げるか、という戦略的な料金設定に留まっています。
ただし今後、気候変動が進行し猛暑の影響がさらに強まれば、冷房・断熱を含む安全対策の標準化は「旅行者から選ばれるための付加価値」ではなく、「宿泊事業を継続するための必須条件」となっていくでしょう。
民泊特有のリスク
宿泊施設と同様のリスクにさらされているのが、Airbnbなどの民泊事業。
民泊は旅行者にとって手頃でローカルな体験を提供する一方で、ホテルと比べて安全基準や緊急対応に関する規制が緩く、気候変動がもたらすリスクに対して特有の脆弱性を抱えているのが現実です。
まず、法制度の側面です。ホテル業界は多くの国で消防法や建築基準法、衛生管理規制などの厳格なルールに従って運営されており、熱波や停電、火災といった緊急時には一定水準の安全性が確保されています。
これに対し、民泊は「個人の住宅を短期賃貸する」という前提で法規制が後追いとなることが多く、許可自体を認めない国や地域も少なくありません。物件が個人宅であったり、所有者が遠方に居ることも多いため、もしものときの避難計画や緊急時の連絡体制が整っていないケースもあります。
さらに設備の不備が発生するようなことがあれば、民泊の場合、事態はより深刻になります。
ホテルであれば別の部屋を案内したり、代替宿泊施設の手配などの義務がサービス約款などに応じて発生することになりますが、個人宅を利用する民泊では、住宅の所有者は宿泊業を主な業としない人であることも多く、代わりに案内できるような他の物件や部屋がないことが多いため、対応も後手に回りがちです。
結果として利用者は、代替宿泊地を探す、設備の復旧を試みるなど自力で問題に対処することとなり、大きな負担を強いられます。
こうした民泊特有のリスクは、気候変動によって極端な高温が日常化する中で、旅行者の生命・健康に直接影響を及ぼす重大な要因となりつつあります。
それにもかかわらず、民泊を仲介するプラットフォームが安全基準を統一的に定める動きは限定的で、責任の所在があいまいなまま放置されているのが現状です。
こうした中、フランスでは住宅逼迫問題と短期賃貸市場の急拡大を受け、2024年末に「Airbnb法」が成立しました。
この法律は、2025年までに観光用賃貸住宅がエネルギー効率「F」ランク以上を満たすことを義務づけ、2028年には「E」、2034年には「A〜D」ランクへ段階的に引き上げる内容となっています。(Airbnb法に関する記事リンク)ただし、この基準は建物全体の断熱性や省エネ性能を対象としており、冷房設置義務とは直接的に結びついていません。
結果として、オーバーツーリズム問題も絡み、旅行者は「命を守るための快適性(安全な室温環境)」と「環境保護・省エネ目標」の間で、しばしばジレンマを抱える状況に置かれています。
責任の所在をめぐる理論枠組み
こうした状況では、民泊の利用者が被害を受けても、責任の所在が不明確なまま放置されがちです。この曖昧さを整理し、誰がどこまで責任を負うべきかを考えるうえで、以下の理論的な枠組みが重要な手がかりとなります。
CSR・予防原則・安全確保義務の整理
責任の所在を整理するためには、まず「企業の社会的責任(CSR)」や「予防原則」「安全確保義務」といった、企業行動やリスク管理に関わる基本的な考え方を押さえる必要があります。
企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility: CSR)は、単なる法令遵守にとどまらず、社会や環境への負の影響を最小限に抑える義務を含みます。特に気候変動や災害リスクが顕在化する状況では、企業が「予見可能な危険から顧客を守る努力をする」ことがCSRの中核となります。
観光産業のCSRがSDGsに貢献する可能性については既にいくつかの研究で示唆されており、今後更に産業としての姿勢が問われることになりそうです(Montañés-Del Río et al. 2025; Arici et al. 2025)。
ここで重要となるのが予防原則(Precautionary Principle)です。1992年の地球サミットで示されたリオ宣言の原則15に基づき「重大・不可逆的被害が予想される場合、科学的確証が不十分でも予防措置を講じるべき」とされるこの考え方は、EUを含む国際環境法や政策に広く組み込まれています。
国連グローバルコンパクトも、企業に対して「環境問題に対して予防的アプローチを支持すること」を原則として挙げており、CSR の国際的枠組みとしても採用されています(→国連の該当ページ)。観光業においても、熱波による健康被害が繰り返し報告されている以上、宿泊事業者や仲介プラットフォームには事前の安全対策を取る道義的責任があります。
また、安全確保義務(Duty of Care)の観点からも、事業者は顧客が予見できないリスクを軽減するための措置を講じる必要があります。これは法律で定められた最低限の安全基準だけでなく、実際のリスクに即した柔軟な対応を含みます。たとえば、猛暑時の冷房設置や避難案内の提供は、法的義務がなくても「安全確保義務」の一部として期待される行為です。
気候変動が宿泊業に新たなリスクをもたらす中、CSR、予防原則、安全確保義務はいずれも「旅行者の生命・健康を守る責任」を基礎づける枠組みといえます。にもかかわらず、これらの原則が民泊や仲介プラットフォームに十分に浸透していないことが、後続で述べる“責任の空白”の温床となっています。
- Montañés-Del Río, Miguel Ángel, Vanessa Rodríguez-Cornejo, Paula Isabel Rodríguez-Castro, and Jesús Herrera-Madueño. 2025. “The Implementation of Corporate Social Responsibility Policies in the Tourism Industry and Sustainable Development Goals: A Review of Progress, Challenges, and Opportunities.” Sustainability 17 (13): 6044. https://doi.org/10.3390/su17136044.
- Arici, Hasan Evrim, Mehmet Bahri Saydam, Alptekin Sökmen, and Nagihan Cakmakoglu Arici. 2025. “Corporate Social Responsibility in Hospitality and Tourism: A Systematic Review.” The Service Industries Journal 45 (7–8): 721–750. https://doi.org/10.1080/02642069.2024.2345299.
プラットフォーム経済における“責任の空白”
Airbnbなどのプラットフォーム型ビジネスは、従来の宿泊業とは異なる責任構造を持っています。民泊のトラブルが起きた際、「誰が責任を負うのか」が明確になりにくいのは、このビジネスモデルに固有の特徴があるためです。
仲介者モデルによる責任分散と安全確保義務の形骸化
本来、宿泊サービスを提供する事業者には「利用者の安全確保義務」が課されるべきですが、仲介者モデルではその義務をホストに丸投げできる構造があります。
プラットフォームは、法律上は「宿泊施設の提供者」ではなく「取引の仲介者」と位置づけられることが多く、宿泊施設の安全や快適性に関して直接の義務を負わないケースが一般的です。
このため、設備不備や緊急時の安全確保に問題が発生しても、ホストとプラットフォームの間で責任が押し付け合われ、利用者が宙づりになる事態がしばしば見られます。
規制の後追いと法制度のグレーゾーンによる予防原則の欠如
予防原則の観点からは、「危険が想定される場合は規制や安全対策を先回りして整備すべき」ですが、民泊は法整備が追いつかず、極端な暑さや災害時の避難経路などのリスク管理が未整備なまま放置されがち。
民泊は新しい形態の宿泊サービスであるため、既存のホテル業法や建築基準法の枠組みから外れやすく、法的責任が明文化されない「グレーゾーン」にあります。
その結果、各国や自治体で規制の適用範囲が異なり、統一的な安全基準が存在しないまま運用されることも少なくありません。
プラットフォームの“免責ポリシー”の存在とCSRの回避
企業の社会的責任(CSR)の観点では、仲介業者であっても自社が提供するサービスの安全性や利用者保護に対して一定の責任を負うべきです。
しかし、現実には利用規約で責任を回避し、トラブル時の補償も任意的対応にとどまることが多く、結果として利用者は自らのリスク負担を前提とした契約を結ばされているのが現状。
なおプラットフォーム側で保険制度や保護制度をうたっている場合もありますが、その適用範囲や運用基準は必ずしも明確ではなく、実際にトラブルが起きた際には利用者が期待した補償を受けられないケースも見られます。
このように、プラットフォーム経済では、取引を仲介する事業者が「市場を支配する立場」にありながら、従来型の宿泊業者が負ってきた安全・衛生・緊急対応の責任を回避できる構造が存在しています。
これが“責任の空白”と呼ばれる問題の根幹です。
日本でも社会問題化している“責任の空白”
この状況は、宿泊予約サイトの利用が定着している日本も例外ではありません。近年、日本国内でもAgodaなど海外デジタルプラットフォーム(宿泊予約サイトは特に海外OTAと呼ばれることがあります)の利用に関するトラブル相談が急増しています。実際、消費生活センターに寄せられる旅行関係の苦情相談の約10%が海外OTAに関するものです。
問題は、Booking.comやAgodaのような海外プラットフォームを利用する場合、宿泊契約や旅客運送契約はホテルや航空会社との間で成立するという点です。
日本の旅行業法は日本国内に事業所を持たない海外事業者には適用されず、トラブルが発生しても同法による保護を受けられません。
さらに、民事訴訟という手段も費用や手間の面で現実的ではなく、消費者は事後対応をOTAの“善意”に頼らざるを得ないのが実情です。その結果、泣き寝入りを強いられるケースが後を絶ちません。
こうした事態を受け、観光庁も2015年に「オンライン旅行取引の表示等に関するガイドライン」を策定しましたが、望ましい表示のあり方を示すにとどまり、実効的な救済手段は提示されていません。
このように、仲介型プラットフォームが取引を支配しながら責任を回避できる構造は、日本でも変わらず存在しています。たとえ国内旅行であっても、海外プラットフォームを利用する限り、“責任の空白”に巻き込まれるリスクは誰にでも起こり得るのです。
日本経済新聞「海外業者から消費者守れ 弁護士 鈴木尉久氏」(2025年8月4日付朝刊)
記事リンク:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250804&ng=DGKKZO90407240R00C25A8TCS000
(※有料会員限定記事)
自己責任論と消費者保護原則の対立
プラットフォーム経済における民泊サービスは、利用規約を通じてリスクを利用者側に転嫁するビジネスモデルを基盤としています。宿泊施設に不備があった場合でも、「最終的な選択とリスクは利用者が負う」といった自己責任論に立脚した条項がしばしば設けられています。
しかし、こうした規約内容は消費者保護法や競争法の原則と衝突する余地があります。
多くの国や地域の消費者法は、サービス提供者と利用者との間に情報の非対称性や交渉力の格差が存在することを前提に、契約条項の一方的・不当な免責を制限しています。特に安全性に関わる部分で事業者が責任を回避する条項は、利用者の生命・健康を守る観点からEUの不当条項指令(Directive 93/13/EEC)などで無効とされる可能性が高い分野です。国連の消費者保護ガイドラインも、事業者が消費者に対し安全で公正な条件を提供する責務を負うことを明確にしています(UNCTAD 2016)。
こうした状況に対し、各国の消費者保護当局や消費者団体は、プラットフォーム型サービスにおける不当条項の是正や、被害事例の調停・救済を行う重要な役割を担っています。しかし、OECD(2022)の報告書が指摘するように、国際的な越境サービスでは法解釈や管轄が国ごとに異なり、手続きにも時間がかかるため、利用者が速やかに十分な救済を得られないケースが多いのが現状です。
さらに構造的な問題として、プラットフォームがあいまいな規約を制定していても、その運用方法が正される機会がないことが挙げられます。
例えば、トラブルの当事者であれば利用規約の正当性を法的に争うことができるかもしれませんが、現実には、旅行中に発生したトラブルの解決や代替宿泊先の確保、追加費用の立替対応など、目先の緊急対応がどうしても優先されます。しかも大抵の場合その問題が解決すれば満足するので、規約の内容自体を精査し不当条項を争うケースはほとんどありません。
その結果、規約の正当性が問われる機会は極めて限られ、多くのケースで不透明な規約が温存され続ける構造が生まれています。
- European Union. Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on Unfair Terms in Consumer Contracts. Official Journal L 095, 21/04/1993, p. 29–34.
- European Union. Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on Consumer Rights. Official Journal L 304, 22/11/2011, p. 64–88.
- OECD. 2022. Report on the Implementation of the OECD Recommendation on Consumer Protection in E‑commerce. Paris: OECD Publishing, p. 36.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). United Nations Guidelines for Consumer Protection. New York and Geneva: United Nations, 2016.
Airbnb事例が示す“責任の空白”の具体像
前章では、プラットフォーム型ビジネスに内在する「責任の空白」という構造を整理しました。
しかし、この抽象的な構造は、実際の現場ではどのような形で利用者に影響を及ぼすのでしょうか。
ここでは、私自身が2025年夏にパリで体験したAirbnbトラブルをもとに、理論編で挙げた問題がどのように現実化し、どこに“責任の空白”が露呈するのかを検証します。
この体験では、エアコンの故障や安全確保の不備から始まり、強制キャンセル、荷物の勝手な移動、冷蔵保管が必要な薬剤の破棄、さらには補償制度の不透明さと不十分さに直面しました。旅行者にとっては、ただ滞在場所が確保できないだけではなく、健康や安全を直撃する切実な問題です。にもかかわらず、プラットフォーム側の対応は一貫して不明瞭で、誰がどの責任を負うのかが最後まではっきりしないまま終わりました。
以下では、この実体験を手がかりに、「補償制度」「緊急対応」「決定権と責任の所在」という三つの観点から、Airbnbが抱える構造的な問題を整理します。
補償制度の限界と透明性の欠如
Airbnbは、予期せぬトラブルが生じたときにゲストやホストを保護するための補償制度を整備しています。
代表的なものは「AirCover」と「問題解決センター」です。
AirCoverは保険に似た仕組みで、ホスト用には家財破損や責任保険、ゲスト用には宿泊先の問題が解決しない場合の代替宿泊や返金手続きをサポートするサービスがあります。また、金銭的な解決が必要な場合には、当事者間で調整を行い、合意できないときにAirbnbが介入する「問題解決センター」が用意されています。
一見すると充実した制度に見えますが、実際の運用には大きな課題があります。
たとえば、ホスト用AirCoverには補償上限額が明記されているのに対し、ゲスト用には基準が明文化されておらず、ケースごとの補償額はAirbnb側の裁量に委ねられています。さらに「問題解決センター」では、実際の損害額に関わらず請求可能な金額が制限され、必要経費を全額請求できないケースが多く見られます。
今回の事例でも、ホテル代、交通費、衣類の購入費、冷蔵保存薬剤の再購入費など複数の損害が発生しましたが、当初Airbnbが提示した補償額は宿泊料を基準にした一部補填にとどまりました。なぜ全額補償が認められないのか、どのような計算式や規定が適用されたのかについては最後まで明確な説明がなく、根拠を尋ねても回答は曖昧なままでした。
本来、補償制度は利用者保護の最後の砦であり、安心して利用できる環境を担保する役割を持つはずです。しかし、現状の運用は透明性を欠き、CSRや安全確保義務の観点から見ても形骸化しており、結果として利用者に一方的なリスク負担を強いる構造が温存されているのが実態です。
緊急代替手段の欠如と安全確保の不在
Airbnbの仕組みには、トラブル発生時に即座にゲストを保護するための実効的な緊急代替手段がほとんど存在しません。
今回の事例でも、猛暑の最中にエアコンが故障した際、Airbnbから提示されたのは「代替宿泊先を自分で探すように」との指示だけでした。しかも補償額は100ユーロと、パリで当日予約できる宿泊先をカバーするには到底足りない金額。深夜のトラブル対応としては、現実性を欠く内容でした。
さらに、冷蔵保存が必要な薬剤を一時的に失い、健康被害が発生しかねない状況に陥ったにもかかわらず、Airbnb側は事前に薬剤の存在を伝えていた事実を考慮せず、緊急性に応じた対応を行いませんでした。その後の補償においても、現地での再購入に必要な実費ではなく、日本で購入した際の金額を根拠に一方的に提示するなど、実情を無視した対応が続きました。
本来、宿泊サービスの提供者には、安全確保義務に基づき、災害や設備不備など予期せぬ事態が発生した場合にゲストを保護し、代替手段を迅速に提供する責任があります。しかし、プラットフォームが「仲介者」という立場を盾に責任を分散させる(一部ホストに転嫁する)ことで、この義務が実効的に果たされない構造が放置されています。
この事例は、民泊業界全体が予防原則を欠いたまま急拡大している現状を象徴しています。猛暑や災害時のリスク対策、避難経路や医薬品管理といった基本的な安全対策すら整備されないまま運用されていることは、プラットフォーム経済の制度的欠陥を浮き彫りにしています。
強制キャンセルや荷物移動の合理性不明瞭化
Airbnbのトラブル対応では、宿泊予約の強制キャンセルや荷物の移動といった重大な決定が、誰の判断で行われ、誰が責任を負うのかが極めて不透明です。
今回の事例では、設備トラブルに関する交渉を行っている最中にAirbnb側が通知なしに予約を一方的にキャンセルし、宿泊先を失う結果となりました。さらに、本人の同意を得ないまま荷物が屋外倉庫へ移動され、冷蔵保管が必要な医薬品が常温放置されるという事態も発生しました。これらはゲストの安全や財産に直結する重大な対応にもかかわらず、事前説明や同意取得はほとんどなく、事後的にメッセージで知らされるだけでした。
問題は、誰が決定権を持ち、どの基準で判断しているのかが明らかにされないことです。Airbnbは「ホストの判断」と「プラットフォームの規約上の対応」とを使い分け、責任の所在をあいまいにします。結果として、ゲストは損害が生じても補償先を特定できず、交渉の矛先を失いがちです。
本来、宿泊サービスにおける予約キャンセルや荷物の取り扱いは、契約上明確なルールがあるべき領域です。安全確保義務の観点からも、第三者による荷物移動や宿泊先喪失は、本人の同意なしに行うべきではありません。にもかかわらず、プラットフォーム経済では、仲介業者が「判断権限はホスト」「執行はプラットフォーム」という二重構造を利用し、責任を回避する余地を残しています。
このような不透明な意思決定プロセスは、消費者保護の観点からも大きな問題です。強制キャンセルや荷物移動のルールが曖昧なまま運用されることで、利用者は自身の権利を適切に主張できず、最終的にリスクを一方的に負担させられる構造が温存されています。
今回の事例を通じて明らかになったのは、Airbnbというプラットフォーム型ビジネスにおける責任の空白が、単発のトラブルやホスト個人の問題にとどまらない構造的な課題であるという点です。
補償制度は透明性を欠き、実損害を反映しないまま部分補償にとどまる。緊急時の代替手段や安全確保の仕組みは不十分で、予防原則が無視されている。さらに、強制キャンセルや荷物移動といった重大な決定においても、誰が責任を負うのかが曖昧なまま処理される。
これらはいずれも、プラットフォームが仲介者を名乗りながら市場を支配し、安全確保義務やCSRの責任を回避できる構造から生じています。この責任の空白は、個別のケースをいくら交渉や通報で解決しても根本的には埋まらず、制度設計そのものの見直しが必要であることを示しています。
気候変動適応責任の再構築に向けて
前章で見てきたように、Airbnbの事例は単なる一企業の不手際ではなく、プラットフォーム経済全体に存在する「責任の空白」を示す典型例です。
気候変動の影響が拡大し、猛暑や災害が宿泊業を直撃する中、利用者の安全を確保できないまま放置される現状は、もはや個別トラブルでは済まされません。
ここでは、国際的な潮流や制度設計の新たな方向性、そして観光業全体の投資不足という3つの観点から、気候変動適応責任を再構築する必要性を考えます。
企業責任を強化する国際的潮流
欧州では、EUが導入したデジタルサービス法(Digital Services Act, DSA)により、従来の「仲介者免責」に一部制限が加えられ、オンラインプラットフォームには安全確保義務、重大リスクに関する透明性報告義務、消費者保護・違法コンテンツ対策の強化といった新たな要件が課されるようになっています(DSA 第2章~第4章)。
この動きは、「プラットフォームだから責任を追わない」という従来のスタンスを転換する方向にあり、今後はAirbnbなどの観光業プラットフォームにおいても、実質的支配力を有する企業としての責任が問われる時代が来ると考えられます。
- European Union. 2022. Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act). Official Journal L 277: Jan. 27–102.
リスク分担の新モデルの模索
現行の民泊サービスは、リスクを利用者とホストに過剰に押し付ける構造になっています。エアコン故障や災害時に代替宿泊が自動的に手配される仕組みがないことは、その象徴的な例です。
今後必要なのは、予防原則に基づき、あらかじめ想定されるリスクに対して責任の所在と救済策を制度化することです。たとえば、以下のような新モデルが考えられます。
- 緊急時の自動代替宿泊制度:宿泊施設の利用が不可能になった際、プラットフォームが即時に代替宿泊先を確保し、移動費用も含めて責任を持つよう、明文規定を設ける。
- 強制保険制度の導入:プラットフォームがホストと利用者双方をカバーする第三者の提供する強制保険を設け、実損害を迅速かつ公平に補償できるようにする。
こうした仕組みを組み込むことで、責任の空白を埋め、被害を未然に防ぐことが可能となります。
観光業における“適応投資”の不足と必要性
気候変動リスクが高まるなか、多くの宿泊施設やプラットフォームは、猛暑対策や災害時の安全インフラ整備といった適応投資を後回しにしています。その理由には、短期的なコスト回避や「想定外」として責任を免れる余地があることが挙げられます。
しかし、適応投資を怠ることで、利用者の健康被害、緊急避難時の混乱、公共機関による救援コストなど、社会全体のコストが増大していきます。本来、企業はCSRの観点からも、こうした長期的リスクに備える投資を行う責任があります。
観光業は今後、単なる「快適な宿泊サービスの提供」から、「気候変動時代の安全・健康リスクを管理する社会インフラ」としての役割を果たす方向に転換する必要があるでしょう。
排出量削減責任の空白と観光プラットフォームの限界
さらに、気候変動の緩和に関連する排出量管理についても、観光業界、とりわけ仲介型プラットフォームでは責任分担が曖昧なままです。
宿泊時のCO₂排出量は、主に建物のエネルギー効率や利用電力の種類、移動手段によって左右されます。しかし、民泊の場合はホストが個別に物件を運営しており、プラットフォーム企業はあくまで仲介者の立場にとどまるため、現行の仕組みでは、プラットフォームがホストに排出削減対策を義務付ける規制的枠組みは確認されていません(Airbnb Sustainability Report 2023)。
EUでは大企業に対してサステナビリティ情報の開示義務(Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRDなど)が強化されつつありますが、Scope 3(バリューチェーン全体の排出量)については計測が困難なこともあり、義務化は部分的です。結果として、AirbnbやBooking.comのような企業は、自社の事業運営による直接排出(Scope 1・2)の削減や、ラベル付けによるサステナブル宿泊施設の見える化といった自主的取り組みに留まっています。
つまり、適応投資だけでなく、排出量削減の面でも「誰が責任を負うのか」が曖昧なまま。プラットフォームが強制力を持ってホストにエネルギー効率改善や再生可能エネルギー導入を促す枠組みはなく、旅行者が自分の宿泊による排出量を把握・コントロールする仕組みも未整備です。
この責任空白が続く限り、観光業全体としての脱炭素化や気候変動リスクへの備えは後手に回り、社会的コストが増大し続ける可能性があります。
参考までに、Airbnbが公表している温室効果ガス排出量のスコープ別内訳を示します。データからは、同社の排出の大部分がサプライチェーン由来(Scope 3)であることがわかります。
| Scope | 含まれる排出源 | Airbnbにおける現状・割合(最新) |
|---|---|---|
| Scope 1 | 企業が直接所有・管理する排出(例:オフィスの燃料) | 約1,300 tCO₂e(企業排出の0.3%未満) |
| Scope 2 | 購入電力などによる間接排出 | 約6,060 tCO₂e。2021年以降グローバルオフィスで100%再生可能電力調達済み |
| Scope 3 | サプライチェーン、事業旅行、従業員通勤など全15カテゴリの排出 | 全排出量約98%を占め、2023年は約396,000 tCO₂e;特に「購入品・サービス」が主で約92%を占有 |
※直近の情報によれば、Airbnbではサプライヤー主体のScope 3排出を 2030年までに付加価値単位($1M売上)当たりで55%削減する目標を掲げています(→関連記事)。
気候変動はもはや観光業にとって「外部要因」ではなく、事業存続を左右する根本的なリスクとなっています。にもかかわらず、現行のプラットフォーム型ビジネスは、責任を分散させることで緊急時対応や安全確保を後回しにし、さらには排出量削減やリスク適応への投資も不十分なまま運営されています。
今後、国際規制の強化や予防原則に基づく制度設計が進めば、企業が「仲介者だから」という理由で責任を回避する余地は徐々に狭まっていくでしょう。
プラットフォーム企業も含めた観光業界全体が、利用者の安全と持続可能性を両立させる方向に舵を切れるかどうか―これが、ポスト気候危機時代の競争力を左右する分水嶺となるはずです。
まとめ
Airbnbを含む宿泊プラットフォームは、仲介者モデルを盾に「安全確保義務」や「補償責任」を分散させ、結果的に利用者をリスクの最前線に立たせています。こうした責任の空白は、OECDが指摘する「国境をまたぐ消費者保護の課題」(OECD 2022)とも重なり、気候変動時代における課題をさらに複雑にしています。
猛暑や災害リスクに対して十分な備えをしないまま観光サービスが拡大すれば、被害は個人や地域社会に跳ね返り、社会的コストは増大し続けるでしょう。
今後は、プラットフォームやホストが予防原則に基づいて安全確保義務を果たす仕組みを整えることが不可欠です。
同時に利用者もまた、自らの選択でリスクや環境負荷を減らすことができます。例えば、事前に宿泊先の気候リスク対応を確認する、鉄道や低排出交通手段を選ぶ、環境負荷の少ない宿泊施設を利用する、過剰冷暖房を避けるといった行動が挙げられます。
さらに、問題のある施設やプラットフォーム対応を可視化し、制度改善を促す声を上げることも、持続可能な観光業への重要な一歩です。
観光はもはや単なる消費活動ではなく、社会のレジリエンスを左右する行為のひとつになっています。安全と持続可能性を両立させるために、企業・規制当局・利用者の三者がそれぞれの責任を果たすことが、今まさに問われているのです。
以上です。
-1.png)
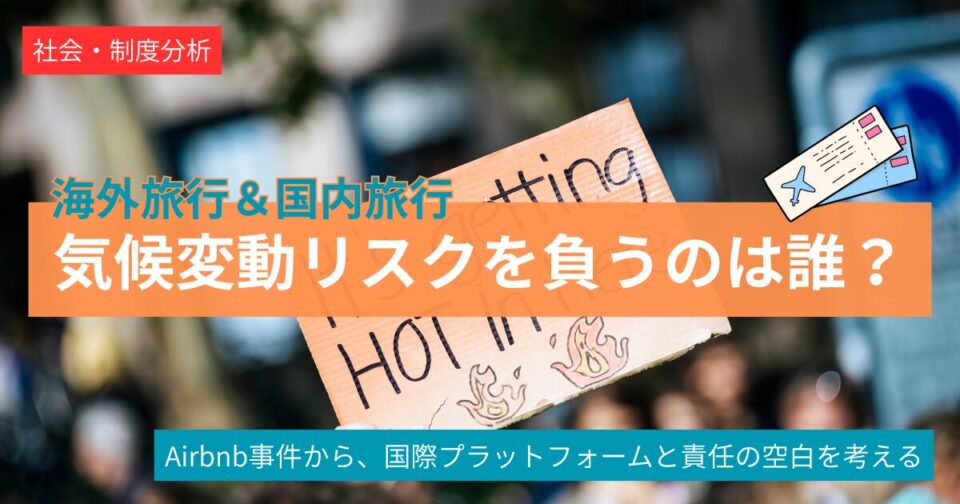
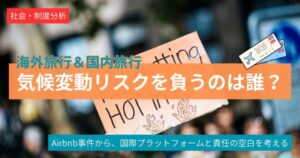
コメント