さまざまな国で暮らす人々と話す中で、まだ自分の知らない人生の可能性があることに気づきました。
特に印象的だったのは、海外で働く人たちの姿です。彼らは日本の会社員より短い時間で働きながら、家族との時間や長期休暇をしっかり確保しています。しかも給与水準は日本より高いことも多く、心に余裕があるように見えました。
また、公務員であっても自分のブランドを持ったり、副業に取り組んだりと、キャリアを主体的に選び取る人が多い。そんな姿からは「人生を自分のものにしている」という充実感が伝わってきます。
一方で日本で働く人々の多くは、生き方やキャリアを「選ぶ」というより「諦めて従う」側面が強いように感じます。よく耳にするのは「レールを外れたら終わり」という言葉。
なぜ私たちはそこまで「レールを外れること」を恐れるのでしょうか。
そして、一度外れてしまうと本当にやり直しは難しいのでしょうか。
この記事では、その理由を考えていきたいと思います。
レールから外れることを許さない「唯一の正解」思考
日本社会で「レールを外れること」が怖いと感じられる大きな理由のひとつは、正解は一つしかないという価値観です。
学校教育から企業文化に至るまで、「正しい答え」に従うことが当然視され、少しでも外れた行動は間違いとして扱われがちです。これが、人生のレールを外れることへの強い不安につながっています。
日本の教育で養われる正解思考
日本の教育は、思考力や自分なりの答えを導き出す力よりも、知識を覚えて唯一の正解にたどり着く方法を学ぶことを重視してきました。
学校で高評価を得るには「学んだ内容をそのまま再現すること」が求められます。異なる道筋で正解にたどり着いても評価されず、場合によっては減点や「恥をかかされる」といった体験を伴います。
こうした経験を重ねるうちに、生徒は「答えを自分で持つことは許されない」「どこかにある唯一絶対の答えに辿り着かないといけない」と感じるようになります。
答えは常に外部に存在し、それを正確に当てることが安全で正しい─そんな思考が刷り込まれていくのです。
さらに、学校や企業は偏差値やランキングで序列化されます。上位に位置すること自体が「正解」とされ、そこに到達できれば人生がある程度約束されると信じられました。そして、いわゆる「良い学校から良い企業へ」という一本道が、社会的なレールとして当然視されてきました。
近年ではSNSの普及により、容姿や生活スタイルといった私的な領域にまで「あり・なし」のジャッジが持ち込まれています。そこには必ず「社会的にあるべき姿」「社会的な正義」が存在し、個人が自分で考えた答えよりも「社会が決めた誰でも納得できる答え」を探す傾向がますます強まります。
こうした環境では、人は「答えは常に自分の外にあり、それを探し当てるのが正しい」と信じ込むようになります。やがて「自分で考えて答えを持つこと」を放棄し(もしくは諦め)、正解は必ず社会や他者が決めるものだという感覚が強く刷り込まれていきます。
徹底した横並び・平等主義思考
社会が「唯一の正解」を用意している背景には、格差の発生を防ぎたいという意識があります。
あらかじめ決められた正解以外の答えは認められないため、結果は「できたか」「できなかったか」の二択。
みんなが「ある程度できる=平均的」であることが最も望ましいとされ、その中では「できる人が評価される」よりも「できない人が劣っている」と見なされがち。「遅れている人に合わせる」という発想はこのような構造から出発しているかもしれません。
また日本では特に「年齢」が重視されます。落第や原級留置はほとんどなく、習熟度に関係なく学年は進みます。
就職も同じ年齢で一斉に行われ、伝統的な企業では年功序列によって年齢とともに昇給していきます。
こうして能力やライフステージ、考え方が似通った集団が形成され、「同期」という強い連帯意識が生まれます。
その集団内で共有される価値観が「正解」となり、従わざるを得ない強力な同調圧力を生み出すのです。
この「正解」が本当に正しいかどうかは問題ではありません。従っていれば安心・安全が得られる一方で、自分なりの考えが集団のそれと異なれば修正を迫られることになります。
結果として、「自分の人生の責任を自分で取る」という発想は育ちにくくなります。
小括
このように、日本社会では「唯一の正解」に従うことが当然視されます。教育によって「答えは常に外にある」と刷り込まれ、横並びを重視する文化によって「平均から外れないこと」が最も望ましいとされてきました。
この2つの仕組みは、「自分で考えるよりも決められた正解に従うほうが安全だ」という感覚を強く根づかせます。
その結果、正解を外れること(すなわちレールを外れること)は「極めて危険な行為」とされます。「その先は自分ではコントロールできない」「答えを導くなんて不可能」「みんなと違うのは怖い」といった感覚が重なり合い、レールを外れること自体に強い恐怖心を抱くようになるのです。
自分の意思よりも他人・社会の意思が優先
日本社会のもう一つの特徴は、「自分の考え」と「他人の考え」の境界があいまいになりやすいことです。
教育や職場で重視されるのは「相手の気持ちを推し量ること」「集団の空気を読むこと」であり、その結果、人は無意識に「自分の意思よりも他人や社会の意思を優先する」ようになります。
このような環境では、自分の信念に従って行動すること自体が難しくなります。つまり「レールを外れる」という選択肢が、最初から取りにくいのです。
ここでは、その具体的な仕組みを見ていきます。
他人視点の内在化を強制する教育
本来、人にはそれぞれの意思があり、他人の考えを正確に把握することは容易ではありません。
しかし日本の教育では「他人の気持ちになって考えなさい」という指導が繰り返されます。これはトレーニングとして一定の効果を持ち、相手の立場を推し量れる(あるいはそう思い込む)人を育てます。
その結果、人は行動する前に「相手はどう思うだろう?」と考えるクセを自然と身につけます。共同体を維持するうえでは有効ですが、一方でリスクもあります。
他人の視点を内在化することが行き過ぎると、自分の意思と他人の意思の境界があいまいになります。
相手の気持ちや場の雰囲気を尊重しすぎて、自分の考えを主張できなくなるのです。
「多少損をしても場が丸く収まればいい」という発想は、その典型例でしょう。
高い同質性を志向する社会
日本では「他人と自分は同じ指標で測れる」という前提が強く刷り込まれています。そのため、ほんの些細な差でも気になりやすく、比較できない要素まで無理にこじつけて比べようとします。
もともと人間は他者と比較したがる生き物ですが、日本社会は思想や価値観の振れ幅が小さいため「自分と同じだろう」「この年齢ならこうだろう」といった共通基準が当てはまりやすい環境です。
結果として、過度に単純化された比較やレッテル貼りが横行します。
その典型が「偏差値」です。同質性の高い集団の中での位置取りにすぎないものが、あたかも人生の成功や失敗を決める絶対的な指標のように扱われています。そして人々はそのような基準をありがたがり、やがて「この数字こそが人間の価値を示す」と信じ込むようになります。
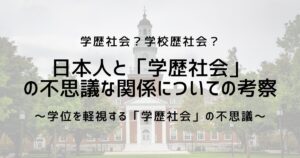
比較が本来持つべき役割は、違いを認めて個性を伸ばすことです。しかし実際には「できない部分」に注目する傾向が強くなり、「自分で達成した喜び」よりも「他人と同等にできない劣等感」の方が前面に出てしまいます。
その結果、「何がどの程度できれば人に認められるのか」という問いばかりを重視し、ますます「正解を探して穴を埋める」思考に傾いていきます。
比較による嫉妬・不平不満を増幅させる社会環境
同質性の高い社会では、「自分」と「他人」の境界があいまいになりやすくなります。
人種や国籍のような大きな違いがあれば比較そのものが意味を持たなくなりますが、似通った属性の人同士では無意識に比較してしまうのです。
例えば社会階級がまったく違えば気にしないようなことも、近い属性であれば「自分も同じ機会を得られたかもしれない」「努力すれば同じステージに立てるはずだ」という期待を生みます。その期待が満たされないと、強い嫉妬や不満につながっていきます。
こうした嫉妬や不平不満は、自分が本来どうしたいのかという願望を簡単に上書きしてしまいます。しかも他人基準で生じる感情は、自分の現状に関係なく湧いてきます。
その結果、人生を自分でコントロールするよりも「他人に勝つこと」が優先され、やがて自分の根本的な欲求さえ見失うようになっていきます。
スキル不信と錯覚資産の多さ
日本社会は比較を好むため、本来の実力やスキルとは無関係の「錯覚資産」が大きな力を持ってきました。
例えば:
- 偏差値や大学ブランド → 高ければ頭が良いとされるが、実際の業務遂行力や専門性とは直結しない。
- TOEICスコア → 高得点でも英語で仕事や生活ができるとは限らない。
- 資格 → 国家資格は別として、民間資格の多くは実務でほとんど意味を持たない。
これらは本来の能力を示すものではありませんが、差別化の基準として重視されるため、持っていないと不安に感じたり、必要以上に取得を求められたりします。
こうして「他人と比べて劣ってはいけない」「みんなが頑張っていることを自分もできなければ評価されない」という図式が生まれます。結果として、本来自分の目標に使うべき時間やリソースが、社会的ステータスを満たすために吸い上げられてしまいます。
さらに問題なのは、これらの錯覚資産が「地頭」「コミュニケーション能力」といった抽象的な資質と結びつき、半ば人格そのものと同一視される点です。実際には、英語力が必要なら面接で英語を使えばよく、TOEICの点数だけで判断するのはナンセンスです。
加えて、日本の高等教育の成果が産業界に十分に認められていないこともあり、個人の専門性よりも「チームでどう振る舞えるか」が重視されがちです。結果として、せっかく持っている強みや希望する分野があっても、他人の思惑によって歪められていくことが半ば前提になっています。

小括
ここまで見てきたように、日本社会では教育や文化を通じて「他人や社会の視点」を内在化する仕組みが徹底されています。同質性の高い集団での比較や嫉妬、そして偏差値や資格といった錯覚資産によって、人は自分の本来の欲求や強みを見失いやすくなります。
その結果、努力や時間といったリソースも、自分の目標のためではなく「社会的に正解とされる基準を満たすこと」に吸い上げられていきます。
このような環境では、自分の信念を軸に生きることは難しく、レールを自らの意思で外れるという選択肢は現実的には取りにくいものとなってしまうのです。
失敗を許さない不寛容な社会
日本社会では「他人と同じことをしている限り安全」という感覚が強く共有されています。
逆に、人と違うことを選び、そこで失敗した場合には「自己責任」とみなされ、社会や制度からの支援はほとんど期待できません。
さらに、人と違う行動をとる人は成功しても失敗しても周囲から強い視線を浴びます。失敗すれば「それ見たことか」と叩かれ、成功しても「何か裏があるに違いない」と粗探しされる。多数派を基準にした「正義」が強く働く社会では、ほんの些細な違いでさえ糾弾の対象になるのです。
ここでは「人と違うことをして失敗するとどう扱われるのか」「なぜ日本社会がここまで正義中毒になるのか」を見ていきます。
人と違うことをして失敗するのは自己責任
日本では、進んで人と違う道を選ぶこと自体が想定されていません。
学校教育で学ぶのは「間違えないための方法」であり、他人と同じスタンダードの人生を送るために役立つ知識や振る舞い。
「どこかにある唯一無二の正解に辿り着く方法」を学ぶことが重視され、「自ら答えを探し出したり、生み出したりする訓練」はあまり行われません。そのようなシチュエーションは例外であり、想定外だからです。
例外を想定しない点は制度設計も同じです。
セーフティーネットは「他人と同じことができない人」を支援するためのものであり、「他人と違うことに挑戦した結果の失敗」には用意されていないことがほとんど。たとえば会社員を解雇された人を守る制度は整っていますが、リスクを取って起業し失敗した人を助ける仕組みはほとんど整備されていません。
会社員は「他人と同じ」範囲に入りますが、起業は「他人と違う」選択肢だからです。
さらに厳しいのは周囲の視線です。失敗した人に対しては「それ見たことか」「だから止めたのに」と言葉を投げかけ、まるで失敗を待ち望んでいたかのように叩く。
成功した場合ですら、「粗探し」をしたり「自分とは違う」と理由を探して安心しようとする人が少なくありません。
このように、日本社会では「人と違うことを選ぶ=守られない」「失敗すれば自己責任」という前提が強固に存在し、挑戦そのものをためらわせる仕組みができあがっているのです。
他人の言動が許せない正義中毒
人と違う行動は、多かれ少なかれ目立ちます。同質性の高い日本社会では、その傾向はいっそう強くなります。
目の届く範囲に「他人と違うことをする人」が現れると、自分に直接関係がなくても一言言いたくなる。こうした心理の背景には「多数派こそが正義である」という強い思い込みがあります。そして「正義」を代弁するとき、人々は容赦を知りません。
厄介なのは、叩かれる対象が必ずしも犯罪や明確な悪ではないことです。同質性が高いために、ほんの些細な違いでも「異質」とみなされ、正義や倫理の名の下に糾弾されてしまうのです。個人的な選択や生き方でさえ、容易に槍玉に挙げられます。
ここまでくるともはや「何をしても叩かれる」社会だといえるでしょう。その中で多数派と異なる行動を取るには、並大抵ではない勇気が求められるのです。
小括
このように、日本社会では「人と違うことを選ぶ」こと自体が想定されていません。制度は失敗した挑戦を守らず、周囲の視線は失敗者を待ち構えていたかのように叩きます。
たとえ成功しても「粗探し」や「特別扱いだ」という形で攻撃されることが少なくありません。
つまり、人と違う行動は成功しても失敗しても極端にリスクが大きく、どちらに転んでも嘲笑や批判がセットになってきます。
これは思い切った挑戦に限らず、他人と少しだけ違う場合にも成立してしまう点が非常に厄介で、小さなチャレンジですらも阻害する要因になります。
このような環境では、誰もが「挑戦するより、黙ってレールに従った方が安全だ」と考えるようになります。レールを外れることは、社会全体からの承認を失うばかりでなく、失敗すれば「一発アウト」。自己責任で全てを背負わされるかもしれない危険な行為なのです。
組織への依存を前提とした社会システム
ここまで見てきたのは「精神的なしばり」や「周囲の目」によって、人がレールを外れにくくなる(レールから外れることに恐怖を覚えるようになる)仕組みでした。
しかし問題はそれだけではありません。日本の社会制度そのものが「組織に依存し続けること」を前提に設計されているからです。
ここでは、その仕組みを具体的に見ていきます。
自立よりも従順さを求める日本の学校教育
日本の学校教育は、個人として生きる力を鍛えるよりも、組織に従順な人材を育てる方向に傾いています。求められるのは「教師の命令に口答えしない」「周囲と同じように行動する」といった、工場労働者として必要とされる素養です。
一方で、「自分の意見を理路整然と述べる」「異なる考えを持つ相手と議論して折り合う」といった訓練はほとんど行われません。ディベートの授業がしばしば“ただのケンカ”に終わってしまうのは、このリテラシーが社会全体に不足している証拠でしょう。
ヨーロッパでは家庭でも学校でも政治や社会について議論することが日常的で、対立しても険悪にはならないといいます。対立を避けること自体が教育目標とされる日本との違いは鮮明です。
その結果、日本では「異なる意見に向き合っても心を守る」「自分の譲れないラインを明確にする」「必要なら法的手段で争う」といった力が身につきません。人と違う行動をとって叩かれたとき、冷静に対処できず、感情的に反応したり自分を追い詰めてしまったりする。これでは個人として生き抜く力を養うことは難しいのです。
組織依存を強める金融リテラシーの欠如
現代社会で「個人として生きる力」として欠かせないのは、お金に関する知識です。
しかし日本の学校教育で教えられるのは「税金は社会の基盤として重要」という一般論にとどまり、資産をどう守るか、税金や社会保険料がどのように給与から引かれているのか、といった実務的な内容はほとんど扱われません。
その結果、社会に出た多くの人は、給与から税金や保険料が自動的に天引きされる仕組みに慣れ、「考えても無駄」と感じるようになります。これは徴税側にとっては効率的で便利ですが、労働者にとっては「お金の仕組みを知らないまま依存して働き続ける」ことにつながります。
加えて、企業や経営者にとっても従業員の金融リテラシーは高い必要がありません。たとえ税金や詐欺で財産を失っても「自己責任」と片付けられ、むしろ経済的に弱った分だけ組織への依存度は高まります。
まさに「知識を与えない方が都合がいい」構造があるのです。
こうして多くの人は、自分の財布にどれだけの人が手を突っ込んでいるかに気づかないまま働き続けます。一方で、もしレールを外れて独立しようとすれば、この管理をすべて自分の責任で担わなければなりません。金融教育が不足している世代にとっては、これは非常に高いハードルです。
自分の給与明細の仕組みも理解せず、会社の作り方や節税の方法にも無頓着なままでは、個人としての自立は難しい。金融リテラシーの欠如は、まさに「組織に依存せざるを得ない構造」を強化しているのです。
寄り道も立ち止まりも許されない社会
日本社会では、キャリアの「寄り道」や「立ち止まり」が強くネガティブに捉えられます。
大学受験では高校卒業と同時に大学に入る「現役合格」、就職では大学卒業と同時に働き始める「新卒一括採用」が理想とされ、それを外れると「浪人」「既卒」といったレッテルを貼られます。
就職や転職でも空白期間はマイナス評価となり、まるでペナルティのように扱われます。
その結果、学生は「自分の人生を探求する」よりも「企業を研究し、選考に受かる」ことを優先しがちです。
真面目な人ほど、自分が何をしたいかを考える時間を削り、限られた経験をもとに有名企業に無理やり興味を合わせる。
結果としてミスマッチや早期離職を招きやすくなります。
社会人になってからも事情は変わりません。業務に全ての体力と時間を注ぎ込む制度設計のもとでは、勤務時間外に自分のスキルを磨く余力はほとんど残りません。
さらに会社都合の異動や転勤によって、自分の努力が報われる保証も薄い。
これが「勉強しても報われない」「どうせ活かせない」という諦めを生みます。
本来なら、キャリアの途中で立ち止まり、自分を見つめ直したり、新しいスキルを身につけたりする時間が必要です。しかし日本ではそれが「空白」と見なされ、評価を下げる要因になってしまう。
結果として多くの人が自分のやりたいことを見失い、ただレールの上を走り続けるしかなくなってしまうのです。
副業禁止がキャリアの自立を封じる
近年、副業は「スキル不足を補う手段」「低賃金を補填する収入源」として注目されるようになってきました。しかしいまだに包括的に副業を禁止する企業は少なくありません。
企業が副業を嫌うのは、従業員が「個として自立可能」になるのを防ぎたいからです。副業でスキルや収入を得れば、自社に依存せず交渉力を持つようになり、最悪の場合は転職してしまうかもしれません。企業にとっては、従業員が自立しない方が管理しやすいのです。
もちろん、本業だけで十分にスキルや収入を得られる場合には市場価値も自然に高まります。しかし、専門性が育ちにくい人事制度のまま副業を禁じられてしまえば、年齢とともに市場価値は下がる一方。結果として従業員は、その企業にしがみ付く以外の選択肢を持てなくなってしまいます。
企業にとっては人材を囲い込める都合のよい仕組みですが、個人にとっては「キャリアの自立」を阻む大きな壁。レールを外れる力は養われないまま、依存だけが強まっていくのです。
やり直しの道筋を欠いた日本社会
欧米のジョブ型雇用社会では、転職や失業は「想定内」の出来事です。労働市場の出入りが激しい分、政府が手厚いセーフティーネットや職業訓練を整備し、教育費用も公的に支援されます。
労働者が一度つまずいても再挑戦できる制度が組み込まれているからこそ、失敗しても「次がある」と思えるのです。
一方、日本社会は真逆です。そもそも「解雇」や「キャリアのやり直し」を前提にしていないため、制度そのものが十分に整備されてきませんでした。スキル不足の社員は異動や研修で吸収され、終身雇用や年功序列の仕組みの中で「辞めさせない」ことが常態化していたからです。
結果として、政府も自治体も「再挑戦のための仕組み」を育ててこなかったのです。

そのため近年改革が進みつつあるとはいえ、失業給付の制約や「103万円の壁」といった制度上の歪みは残り、労働者が思い切って挑戦しようとするインセンティブは弱いままです。
こうした環境では、せっかく努力してスキルを磨いても活かせる場がなかったり、挑戦が失敗に終われば即座にキャリアが行き止まりになったりします。まさに「やり直しの道筋を欠いた社会」。

一度のつまずきが致命傷になりかねないからこそ、人々はますますレールから外れることを恐れるのです。
小括
このように、日本社会の制度は「個人として自立する力」を育てるのではなく、「組織に依存し続けること」を前提に設計されています。
教育は従順さを重視し、金融リテラシーは与えられず、寄り道や立ち止まりは罰せられる。副業も制限され、再挑戦の仕組みも欠如している…まさに自分の力で生きる道を塞ぐシステムです。
こうして制度が徹底的にキャリアの自律を阻害してくると同時に社会的なプレッシャーで精神まで縛ってくるのだから、もはや素晴らしいとしか言えません。
日本社会は、絶対に脱線しないように、かなりしっかりとしたレールを敷いてくれているということですね!
まとめ
見てきたように、日本社会では「人と違うことは悪い」という刷り込み、他人との比較に基づく承認欲求、挑戦を評価しない制度、そして個人として自立する力を奪う仕組みが重なり合っています。
精神的な縛りと制度的な縛りがセットになっているため、人々は「レールを外れる=危険」と本能的に感じるようになってしまうのです。
とはいえ、社会のせいにしていても何も変わりません。
大切なのは、
- 何が問題なのか
- 自分にとっての障害が何なのか
を認識し、自分の範囲で少しずつ「外れる練習」をすること。
異業種交流や読書で視野を広げたり、SNSから距離を取って自分の時間を確保したり、金融やスキルの勉強を始めたり…ほんの小さな一歩でも、自分の「生きる力」を鍛えることにつながります。
そして、もしレールを外れてしまったとしても悲観する必要はありません。レールとは誰かが「正解」と定義した道にすぎず、自分に合わなければ降りてもいいのです。
外の世界には、これまで想像もしなかった新しい道や幸せが存在しています。

筆者は30代後半で大学院留学をして、改めてやりたいことや叶えたい夢について考える機会を得ることができましたし、日本では見えなかった様々な可能性を垣間見ることもできました。
強固なレールの上で生きることも一つの選択肢。でも、自分の人生を自分で作っていく覚悟を決めた人間は、想像以上に強い。
「レールから外れること」こそ、本当の意味での自由と可能性の始まりなのかもしれません。
-1.png)
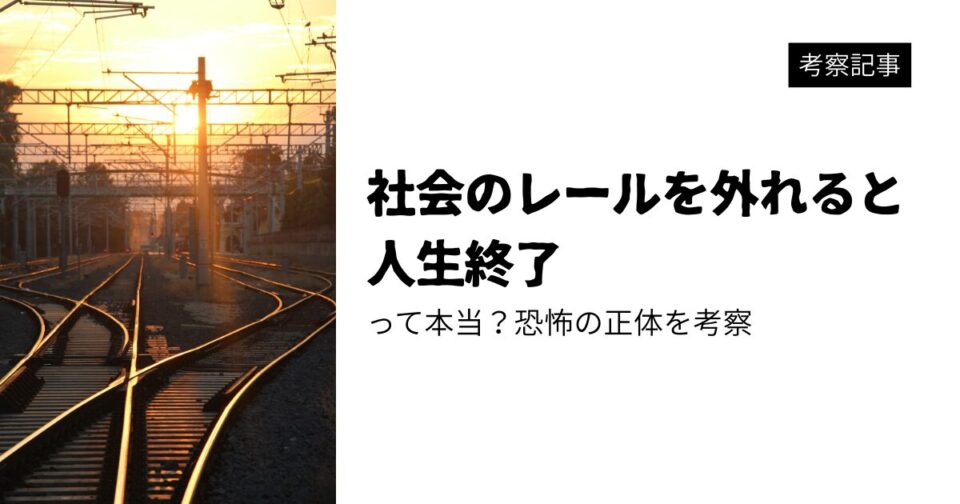
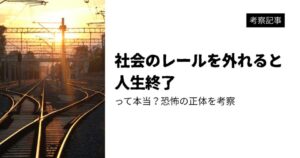
コメント