YouTubeやSNSに海外情報があふれる現代。
古今東西あらゆる旅や海外生活の話題が日々共有されていますが、なかでもパリやフランスに関するトピックには、他の地域とは少し異なる現象が見られます。
たとえば、「見るものすべてが美しいパリ!」「クロワッサン最高!」といった大絶賛系の旅動画がある一方で、「憧れが崩壊した」「パリは汚くて不快」「フランスはもうダメ」といったガッカリ系のコンテンツも少なくありません。
ここまで人によって印象が極端に異なる都市は、世界でもそう多くはないのではないでしょうか。
本記事では、こうした評価の振れ幅が激しいパリ/フランスという対象について、「パリ症候群」と呼ばれる現象と、近年よく聞く「フランスはもう終わっている(オワコン)」という言説を取り上げ、なぜそのような現象が生まれるのか? その背後にはどんな構造があるのか?を、自分なりに考察していきます。
先に結論を述べてしまうと、
「パリ症候群」と「フランスオワコン論」は、一見正反対のようでいて、実は思想的に同じ根っこを持っており、
そこから透けて見えるのは「日本人の過剰な自意識」と、それを支える「無知」と「内向き姿勢」ではないか
というのが、私の見立てです。
パリ症候群とは何か?
まずはすっかり有名になったパリ症候群から取り上げます。
夢の都、パリ
「フランス」と聞いて、多くの日本人がまず思い浮かべるのは、おしゃれな街並み、美しいファッション、洗練された食文化、そして芸術の香りが漂う歴史ある建築群ではないでしょうか。
中でもパリは、まさにその象徴として語られ、「一度は訪れてみたい街」の定番として名前が挙がります。卒業旅行やハネムーンの行き先としても、常に高い人気を誇っていますよね。
この「夢の都・パリ」というイメージは、映画や雑誌、ブランド広告、あるいは中学・高校の教科書を通じて、私たちの中に無意識のうちに刷り込まれてきました。エッフェル塔、セーヌ川、ルーヴル美術館、カフェのテラス席で読書をするパリジェンヌ。そうした光景は、現実というよりも「パリらしさ」という記号として、私たちの脳内にインストールされているのです。

2000年代には映画「アメリ(原題:Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain)」がヒットしましたし、近年ではNetflixで「エミリー、パリへ行く(原題:Emily in Paris)」が大流行していますね。
しかし、そうした幻想を抱いたまま実際にパリを訪れた旅行者が直面するのは、期待とは少し異なる現実です。
さまざまなバックグラウンドを持つ移民がたむろするエリアの淀んだ空気、スリや物乞いと警察が攻防を繰り広げるメトロ、英語を話さない不機嫌な店員、道端にあふれるゴミ、旅行の予定を大きく狂わせるデモやストライキによる混乱…。いずれも観光パンフレットでは積極的には描かれない「現実のパリ」です。
パリ症候群という現象
こうした「理想と現実のギャップ」にショックを受け、極端な場合には精神的に不調をきたす日本人観光客がいることが知られるようになりました。これが、「パリ症候群」と呼ばれる現象です。
この言葉は、1990年代にフランスの精神科医が日本人患者に共通する傾向を指摘したことをきっかけに広まりました。正式な医学用語ではありませんが、観光や短期滞在の際に理想と現実の落差から強いストレスや不安を感じ、場合によっては幻覚や妄想などの症状にまで至るケースがあると言われています。
いわゆる異文化適応の過程で多かれ少なかれ見られる反応ではありますが、特に当時の「裕福な家庭に育った20代〜30代の女性」に多く見られたことでも注目を集めました。
もちろん、すべての日本人観光客がこうした症状を経験するわけではありませんし、近年ではこの症候群自体を揶揄するような風潮すら見られます。
けれど、ここで本質的に重要なのは、症状の有無ではありません。「幻想と現実の落差」が人を深く揺さぶる構造が存在しているという事実こそが、私たちにとって考えるべきテーマなのです。
フランスへの「幻滅」:フランスはオワコン?
波乱とサプライズの連続だったパリ五輪を経て、「憧れのパリ」は、「醜い時代遅れの国」という印象へと、一気に転落していきました。
パリ五輪で反転した世論
2024年のパリ五輪では、当初「花の都での華やかな大会」に対する期待が高まりましたが、開催直前からの一連のトラブルが世論の急転を招きました。波乱とサプライズの連続だったパリ五輪を経て、「憧れのパリ」は、「醜い時代遅れの国」という印象へと、一気に転落していきました。
たとえば以下のような、あまり好ましいとは言えない出来事が続出しました。
- セーヌ川の水質問題:フランス政府は開会前に約14〜16億ユーロをかけて川の汚染対策を実施しましたが、強雨による下水流入などでテストイベントが相次いで中止。複数の選手が体調不良(吐き気、下痢など)を訴え、一部の大会予定も調整を余儀なくされることに…。
- 選手村の食事トラブル:アスリートらは朝食の卵や肉類が不足するなど栄養面でも不満を口にし、「パリ五輪なのにフランスらしくない」「味気ない」という批判が相次ぎました。
- 開会式の演出への賛否:セーヌ川沿いを舞台にした前衛的・芸術寄りな演出は注目を集めたものの、一部では「意味が分からない」「観客を置き去りにしている」と辛辣な反応も起こりました。
これら一連の出来事を受け、SNSや動画コメント上では「パリが想像以上にひどくて驚いた」「フランス終わった」「夢見て損した」という感情的なコメントが急増。YouTuberなどもこぞってフランスをこき下ろす動画を公開し、かつての憧れが一気に幻滅へ振り切ったような世論の様相を呈しました。
さらにこれらの報道の過程でフランスの移民問題を見た視聴者が「日本もいずれこうなる」「移民の受け入れはやめるべき」といったロジックを展開し、全く異なる論点に派生することも。
こうして、「フランスは終わった」という言葉が、冷静な評価というよりも、感情のスローガンのように独り歩きしているように見える場面も少なくありません。
フランスは終わってる?
しかし、ここで改めて問い直してみたいのは、「フランスは終わってる」とは、いったい何を根拠に、どの視点から言っているのか?ということです。
たしかに、フランスには現実の問題が山積しています。ストライキやデモの多発、移民政策をめぐる社会的分断、スリや治安の問題、公共サービスの機能不全、物価の高騰、貧富の格差。観光客が肌で感じるような不安や不便も、実際に存在しています。
けれど、それらをもって「終わっている」と断じてしまうのは、あまりに雑ではないでしょうか。
構造的な問題に冷静に目を向けることと、感情に任せて国全体を否定することは、まったく別の行為です。
実際、フランスに対する批判には、より深い構造的なものも存在します。
たとえば西・中央アフリカの旧植民地では、現在も使用されている通貨CFAフラン(アフリカ金融共同体フラン)が、フランスによる経済的支配の延長とみなされており、「ポスト植民地主義的な搾取の構図」として強く批判されています。
こうした視点に立てば、「フランスは終わってる」という言葉には、単なる観光や印象論を超えた政治的・歴史的な含意もあることがわかります。
…ですが、私たち日本語圏で目にする「オワコン論」の多くは、そこまでの知識や視野を踏まえて発せられているようには見えません。もし社会構造や歴史の根本的な違いに目を向けているのであれば、フランスの問題を単純に日本に置き換えて考えるようなことは起こらないはずですから。
そう考えると、筆者にはむしろ「フランスに期待していたものが得られなかった」「思っていた理想と違った」という落胆の感情が、過剰な否定や嘲笑に変換されているだけに見えるのです。
さらに言い換えれば、「パリ症候群」が「勝手に理想を膨らませて傷つく」現象だとすれば、この「フランスはオワコン」論も、幻想と現実のギャップに耐えきれなかった者たちの、もう一つの反応形とも考えることができそうです。
それは、現実を見ているようでいて、実は「自分が思っていたフランス」の崩壊に対する怒りや失望に過ぎないのかもしれません。
二つの現象の根底:すべては自意識から始まる
「パリ症候群」と「フランスオワコン論」。一見すると正反対に見えるこれらの現象には、実は共通する「ある構造」があります。それは、フランスという「他者」を通じて、自分自身を映し出しているということです。
ここからは、その背後にある「自意識のメカニズム」を考えてみましょう。
勝手に夢見て勝手に幻滅する日本人
冒頭でも触れましたが、ここまで見てきた「パリ症候群」と「フランスオワコン論」は、方向性こそ正反対に見えるものの、どちらも「自分の中で膨らんだフランス像」に強く影響された反応であることが浮かび上がってきます。
「パリはすべてが美しくて、どこを歩いても映画のワンシーンのようだ」と思い込む人がいれば、「フランスはもう終わり。汚くて治安も悪くて、観光地としても価値がない」と切り捨てる人もいる。
しかしどちらにも共通しているのは、実際のフランスを丁寧に観察しようとする姿勢ではなく、すでに「自分の頭の中にあるフランス」を前提に語っているという点です。
しかもその「フランス像」は、必ずしもフランスに固有のものではなく、むしろそこには、日本社会の持つ価値観、文化、自己認識がそのまま投影されていることが少なくありません。
「ヨーロッパは進んでいる」「フランスは自由で洗練されている」…そうした期待は、裏を返せば「日本は遅れていて、不自由でダサい」という対照的な自己認識から生まれているとも言えるのです。
自己認識から出発しているため、現地に触れてその理想像が崩れると今度は「日本ならこんなことは起こらないのに」「日本の方がマシ」「日本人はもっと礼儀正しい」といった優越感にあっさりとすり替わってしまうこともある。
一度は下に見ていた「日本」を持ち出して、落胆した自分を安心させようとする。
こうしてフランスやパリに対する批判は、いつのまにか日本称賛の文脈へとすり替わっていくのです。つまり、フランスやパリの真の姿を語っているようでいて、実はそれらを引き合いに日本について語っている(しばしば無意識に)。それが、幻想にも幻滅にも共通する「自意識の構造」なのです。
では、私たちは一体何を見て、何に傷ついているのでしょうか?
見ているものは「フランス」?それとも「自分自身」?
私たちはフランスを見ているつもりで、実はフランスを見ていないのかもしれません。
たとえば、「フランスは不親切だ」と感じたとき、それは本当に(フランスでは一般的とされる)フランス人の態度を冷静に観察した結果なのでしょうか?それとも、「親切にされたい」「外国でも丁寧に扱われたい」「客商売とはこうあるべきだ」という自分の期待が裏切られたことへの反応なのでしょうか。
そうした問いは、普段あまり明言されることはありません。
また、「フランスは終わってる」と言いたくなる場面にも、「せっかく憧れて来たのに、こんなはずじゃなかった」「日本よりすべてが優れていると思っていたのに、そうではなかった」という落胆や無知(&ときどき優越感)を転嫁する意図が潜んでいる可能性だって、大いにあります。
つまり、フランスに対する評価には、「自分が何を期待し、何に過剰反応しているか」というレンズが常に介在しているのです。そしてそのレンズの存在に気づかないままでは、目の前の現実を冷静に捉えることはできません。
ただ注意したいのは、この構造が旅行や留学に限らず、あらゆる「他者との出会い」において、日常的に陥りがちなものであるという点です。もちろん、対象はフランスに限りません。
さらに、私たちは何かを見るとき、しばしばその対象を見ているのではなく、自分の価値観や願望、あるいは恐れを投影して、反応しているにすぎない。そしてそのことは、日本人に限らずすべての人間に共通する心理でもあります。
だからこそ、「パリ症候群」にしても「オワコン論」にしても、最終的に私たちが向き合うべきなのはフランスではなく、それらを通じて浮かび上がる「自分の見方」や「自分が信じたい自分の姿」そのものなのです。
なぜ「日本人」が「フランス」に?組み合わせの謎
これまで見てきたように、「パリ症候群」や「フランスオワコン論」の根底には、見る者の側の「自意識」が深く関わっていました。
しかしここで立ち止まって考えたいのは、そもそもなぜ日本人がフランスに対してこのような強い幻想と幻滅を抱くのかという点です。
世界には数えきれないほどの国があり、日本人が留学したり旅行したりする国も多岐にわたります。それにもかかわらず、なぜこれほどまでに「日本人×フランス」という組み合わせだけが語られやすく、心を揺さぶる対象になり得るのでしょうか。
本章では、この問いをいくつかの観点から掘り下げてみたいと思います。
進んでいる西欧、遅れているアジア?
そもそも、なぜ(アメリカでもドイツでもなく)フランスなのか?
その背景には、根深い文明観や進歩史観があるのではないでしょうか。
明治以降日本は「近代化=西洋化」と捉え、「脱亜入欧」をスローガンに、西洋の様々な要素を取り入れてきました。
たとえば近代日本が制度設計の上で強く影響を受けたのはドイツ。法律、医学、軍制など、明治政府が国家近代化のモデルとしたのはプロイセン型でした。さらに戦後以降の社会制度や経済運営に目を転じれば、アメリカの影響も非常に大きいとも言えます。
そのなかにフランスに直接影響を受けたものは…正直見当たりません。
おそらく日本がフランスから輸入したのは、制度ではなく、もっと目に見えにくいもの—たとえば「美学」や「知的イメージ」といった、象徴的な意味づけだったのかもしれません。だからこそ、実態とはややズレたまま、フランスは「洗練された文化国家」「個人主義と自由の国」として日本人の中で記号的に機能し続けてきた。

市場に溢れる「フランス人本」がこの事実を物語っているかのようです。以下はほんの一例ですが、本に書いてある要素が全て本当だとするとフランス人がとんでもない超人のように思えてきます…。
こちらはフランス人ライフスタイル本の火付け役になった本(作者はアメリカ人)。
そしてこちらは日本人の著者の書いたフランス式生活様式に関する本。
そう考えれば、「フランス=進んだ西欧、日本=遅れたアジア」という対比構造の中で、フランスが特別な存在として投影されてきた理由もうっすらと見えてきます。
では、なぜその「フランス」に対して、日本人はこれほど強く幻想を抱き、ときに激しく幻滅するのでしょうか?
そこには「自意識の投影のしやすさ」や「裏切られたと感じやすいギャップ」が存在している可能性が高いと考えました。
次は、「日本とフランスの考え方と社会構造の違い」に目を向けてみましょう。
考え方と社会構造の違い
日本とフランスの間には、表面的な制度や文化の違いを超えて、社会の根幹にある考え方や構造そのものに明確な違いが存在します。ここでは特に特徴的なものにフォーカスし、その相違を明らかにします。
ルールの運用:抽象的 vs 具体的
- 日本(抽象的):状況に応じた「空気読み」や「忖度」による柔軟運用。明文化されていなくても「わかるべき」とされることが多い。
- フランス(具体的):制度やルールは具体的に明示されることが前提。誰が見ても同じように読めることが重視される。ただし同じくらい例外や属人的対応も多い。
対立の処理:対話型 vs 衝突型
- 日本(対話型):対立を避ける傾向が強く、表面化させないことに価値を見出す(=和の文化)。戦いを避けることが勝利よりも重んじられる場合も多い。
- フランス(衝突型):対立はむしろ健全な意見表明とされ、むしろ対立することで解決を目指す。ディスカッションやストライキも正当な手段として多く用いられる。
正義の所在:倫理観 vs 権利観
- 日本(倫理観):道徳的な「よきふるまい」が中心。内面の成熟、謙虚さ、忍耐が重視される。正義を声高に叫ぶことは良いこととはみなされない。異なる倫理観を持つ相手には通じないことが多い。
- フランス(権利観):行動の正当性は「法や権利」に基づく。個人の内面より行動の正しさにフォーカス。正義を叫ばない人間は正しくても無視されることも多い。倫理を重視する文化から見ると、わがままに映ることもある。
時間感覚:循環 vs 線的
- 日本(循環):四季の移ろいなどを象徴的に扱い、繰り返しと循環に意味を見出す。長期的な関係性や空気の調和を重視し、「今を乱さない」ことに価値を置く。
- フランス(線的):歴史と革新を行ったり来たりしつつも、「過去→未来」という進歩的直線を志向。将来よりも「今」を楽しむことに注力することが多い。
言語運用:あいまい vs 明示的
- 日本語(あいまい):主語を省略する、断定を避ける、敬語で距離を調整するなど、意味の「余白」が多い。序列に基づく言葉遣いが厳格に定められており、形式を重んじる。
- フランス語(明示的):論理構造や主語・動詞の明示、反論のための前提確認など、構造が明確。こちらも序列により言葉遣いが明確に変化し、その違いも厳格。形式も非常に重要。
責任の所在:非属人性 vs 属人性(制度運用と責任の所在)
- 日本(非属人的):制度や組織は「顔が見えない」運用が原則。たとえば「総務課」「窓口」「係」として対応し、担当者名が伏せられることも多い。責任も組織全体に分散し、責任は個人ではなく組織が負うスタイル。均質的なサービスがウリ。
- フランス(属人的):制度上の枠組みは明示されているが、実際の対応は「誰に当たるか」で大きく変わる。担当者の裁量や解釈が強く、粘り強く食い下がるかどうかで結果が変わることも。人によって説明が違うこともよくある。
集団の構造:見えない序列 vs 明示的ヒエラルキー
- 日本(見えない序列):表面的には非常にフラットだが、その裏では年齢や年次などを基準にした見えない上下関係や「序列」が強く作用する。明示的ヒエラルキーは存在するが、個人間では異なる力学が作用するのが特徴的。
- フランス(明示的ヒエラルキー):ヒエラルキーは制度的に明示されており、それに応じた発言権や待遇がある。それによりポストを超えた付き合いはしにくい傾向があるが、そもそも社会階層が違えば関係を持つことも少ないので問題にはならない。
このように並べてみると、日本とフランスの価値観は正反対と言っていいほど異なることが分かります。
マーケティングやブランディングなどの都合からこれらの点が極端に好意的に解釈されることによって、「自分が持っていないものや理解できないものに対する羨望」の感情が惹起されることは想像に難くないでしょう。
お互いに幻想を投げかけ合う関係性:フランスから見た日本
さらに面白いのが、日本人がフランスに幻想を抱いていたのと同時に、フランスもまた自らの理想像を日本に投影してきた歴史もある点。
実際、フランス人やフランスに関わった人々が抱く日本への憧れや幻想を巡る逸話は枚挙にいとまがありません。
代表的なものは以下のとおり。
- 19世紀のジャポニスム:モネ、ドガ、ヴァン・ゴッホらが浮世絵に魅了され、日本を「近代化に毒されていない美の源泉」として理想化。日本の実情とは異なる「東洋の神秘性」や「未開の美」が、西洋の自己投影として都合よく解釈された面も。
- 禅や武士道への憧れ:現代でもミニマリズムや精神性への憧れとして再燃。実像以上に「哲学の国」として語られる傾向。
- アニメ・マンガを通じた文化受容:ジブリや攻殻機動隊、最近では新海誠作品などが「知的で美しい日本」として広がり、現実の社会問題には触れられにくい。
こうした憧れは好意的ではあるものの、やはり「パリ症候群」に似た構造的な問題をはらんでおり、文化的現実を捉える視点の欠如にもつながっています。実際に日本社会で生活した際に、そのギャップに戸惑い、失望感や疎外感を抱くことも珍しくありません。
他の組み合わせは存在するのか?
もちろん、日本人以外にも「理想化されたイメージ」と現地の現実とのギャップに苦しむ例は、世界各地に存在します。
特に有名なのは、宗教的な聖地で見られる「旅行者症候群」です。なかでも、エルサレム症候群やステンダール症候群は、ある種の幻想が極端な心理的反応を引き起こす代表例とされています。
エルサレム症候群
宗教的に強く理想化された都市エルサレムを訪れた際に、精神状態が急変する現象です。観光客が幻覚や宗教的妄想に陥り、短期間の精神科入院を要するケースも報告されています。年間100件以上の重症例が存在し、なかには精神疾患の診断歴がない旅行者も含まれています。
ステンダール症候群
イタリア・フィレンツェのように、芸術や美に圧倒されたことで、めまいや動悸、錯乱状態を引き起こす現象です。19世紀に作家ステンダールが自身の体験として記録したのが最初とされ、現代でも複数の医療報告が存在します。
宗教とは関係なく、幻想(あるいはステレオタイプ)を投影されやすい都市や国は多数あります。たとえば『エミリー、パリへ行く』に描かれるパリや、理想化された「アメリカン・ドリーム」もその一例でしょう。
しかし、明確に「幻想 → 病的な心理的影響」という因果構造が確認され、精神医学的にも症候群として扱われる例は極めて限られています。
つまり、「パリ症候群」やそれに続く「フランスオワコン論」のような、自己投影と幻滅のサイクルを病理レベルで経験する現象は、今のところ「日本人」と「フランス(特にパリ)」の組み合わせに特に顕著なものと言えそうです。
実際、精神医学的にも「日本人特有の文化構造や社会心理との相性」が背景にあるという見解が定着しており、これは単なる個人差ではなく、社会構造と異文化接触の歪みによる「構造的な現象」と捉えるべきものかもしれません。
ありのままを見るということの難しさ
ここまで見てきたように、日本人とフランスの関係性には、文化や制度の違いを超えた「相互投影」とも呼べる幻想の応酬がありました。これは好意的な意味合いを持つこともありますが、ときに現実とのギャップによって、個人に精神的な混乱や落胆をもたらすこともあります。
では、「現実をそのまま見る」ことは可能なのでしょうか?
実は、それこそが一番難しい営みなのかもしれません。
自分のレンズを意識すること
私たちは常に、自分なりの「レンズ(フィルター)」を通して世界を見ています。それは文化、教育、経験、感情、そして期待によって色づけされたものです。
たとえば「パリは美しい街で、人々は自由で個性的」というイメージも、「日本は礼儀正しく秩序正しい」というイメージも、現地の現実とは限りません。その通りの人もいれば、そこから大きく外れた人だっています。
それはあくまで、誰かの、あるいは自分自身の内面に投影された風景なのです。
自分のレンズに気づかずにいると、現地の文化や社会が「おかしい」「冷たい」「非常識」と映ってしまうことがあります。でも、もしかしたらその違和感の正体は、自分の内側にある「当たり前」や「理想」にあるのかもしれません。
目の前の現実に向き合うこと
理想と現実のギャップに直面したとき、その現実をどう捉えるかは自分次第です。
文化が違えば、価値観も制度も対話の仕方も違います。たとえば、フランスではストライキが「声を上げる正当な手段」であるのに対し、日本では「迷惑行為」として受け止められることもある。そこに善悪はありません。ただ、違うということ。
違いを「理解する」のではなく、「受け止める」。そして、その中でどう生きていくかを問い直すこと。
それが、本当の意味での「異文化理解」の出発点であり、真に相手を受け容れることなのだと思います。
逆パリ症候群も存在するかもしれない
そして最後に注意すべきなのが、過剰なバイアス(ポジティブ・ネガティブ両方)によって、本来は存在するはずの魅力や価値を見逃してしまうこと。
フランスに対して「美しさ」「完璧さ」のイメージを投影すると「人間らしさ」を見逃してしまいますし、「不便」「傲慢」「いい加減」といった印象にフォーカスすると、そこにある「自由さ」に目を向けられなくなることもあります。
ポジティブであれネガティブであれ、「幻想」は私たちの視野を狭めます。だからこそ、好きも嫌いもいったん置いて、目の前の現実をそのまま見つめてみる勇気が必要なのです。
そうすると、自分が思ってもみなかったかたちで「良い部分」が見えてきたり、逆に「どうしても譲れない価値観」に気づくきっかけになるかもしれません。
バイアスを外して現実を見つめることができたなら、フランスやパリが、自分でもよく分からないくらい、どうしようもなく好きになる—そんな「現実を知った上での、ある意味で病的な好意」、いわば逆パリ症候群が発症する人もいるかもしれませんね…。

常にパリのことを考えてしまう。どんなに腹立たしい経験をしても、またパリに行ってしまう。何なら住んでしまう…これって、たぶん「逆パリ症候群」です。フランスあるあるかもしれません。罹患者多そう…。
まとめ:元パリ症候群患者からのメッセージ
かなりとりとめのない記事になってしまいましたが、最後に伝えたいメッセージは以下の3点に集約されるでしょう。
フランスはフランスでしかない
フランスは、美しいです。パリは、やっぱり特別です。
でも同時に、フランスはフランスでしかなくて、そこには現実があり、社会があり、人々がいます。
こちらが好こうが嫌おうが関係なく、ただ、そこに在るのです。
思えば、大学で第二外国語にフランス語を選んだあたりから、筆者自身も「自分の思い描いたフランス」に必死にしがみついていたのだと思います。フランス映画にハマったり、シンガポールでわざわざフランス語を学んだり、馬鹿高いクロワッサンを買ったり…そんなこと、幻想がなければやらないですよね、たぶん。笑
でも実際に住んでみると、腹も立つし、疲れるし、笑うこともあるし、必死に勉強したはずのフランス語が全然通じなくて凹むこともある。それでも、また行ってしまう…。
そうしてようやく、「現実のフランス」と出会えた気がします。
もちろん、現実が全て分かる…なんてことはありません。
というか、永遠に分かることなんてないのでしょう。
でもそれで、いいんです。
だって、自分の生まれた国のことですら、全部知るなんて不可能なんですから。
自意識に集中しても現実は見えない
「こんなはずじゃなかった」
「私はここに来るべきじゃなかったのかも」
そんなふうに感じることも、きっと誰にでもあると思います。
でも、もしかしたらそれは、自分自身の内面にフォーカスしすぎているサインかもしれません。
でも、世界は私たちの自意識を中心には動いていません。
目の前の現実を、自分の期待ではなくそのまま受け取ること。
それができて初めて、「ここにいる意味」が見えてくる気がします。
この辺のことは、筆者はシンガポールで学んだと思います。
過剰な期待を手放して、不満と折り合いをつけて…そんなトレーニングにうってつけの場所でしたから。
好きか嫌いか、合うか合わないか。それぞれ言語化したくなるときもありますが、別に白黒つける必要もありませんし、そのままにしておいても、案外なんとかなります。
自分で考え、学び続けることの大切さ
異国で暮らすこと、旅をすること、違う価値観と出会うこと。
そこにはいつだって「自分の思い通りにならない現実」がつきまといます。
でも、それこそが学びであり、広がりです。
幻想の世界に閉じこもるのでも、誰かを責めるのでもなく、「自分はどう考えるか」「自分はどう生きたいか」を問い続けることが大切なのだと思います。
そしてもしあなたが、ちょっと疲れていても、それでもまたパリに行ってしまう人なら—
もしかしたらあなたも、逆パリ症候群の仲間かもしれませんね。
以上です。
関連記事
海外から日本社会を考察した記事はこちら。

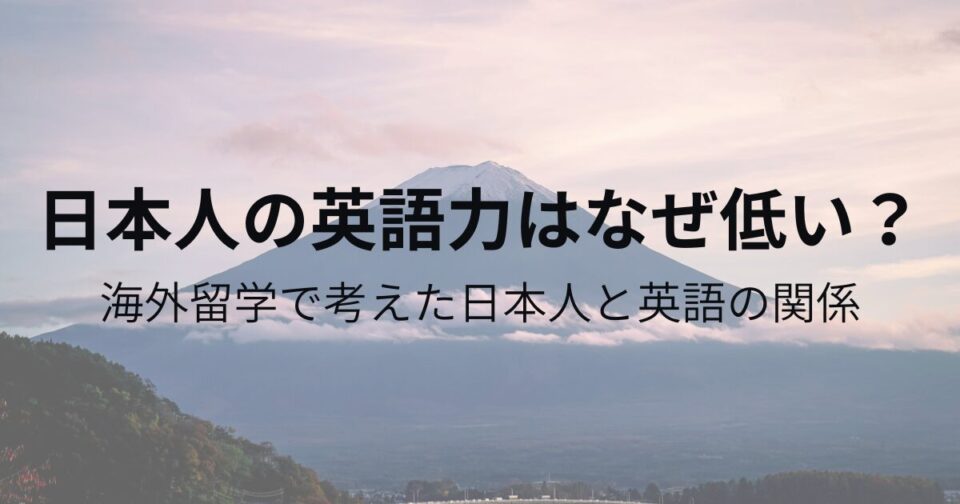
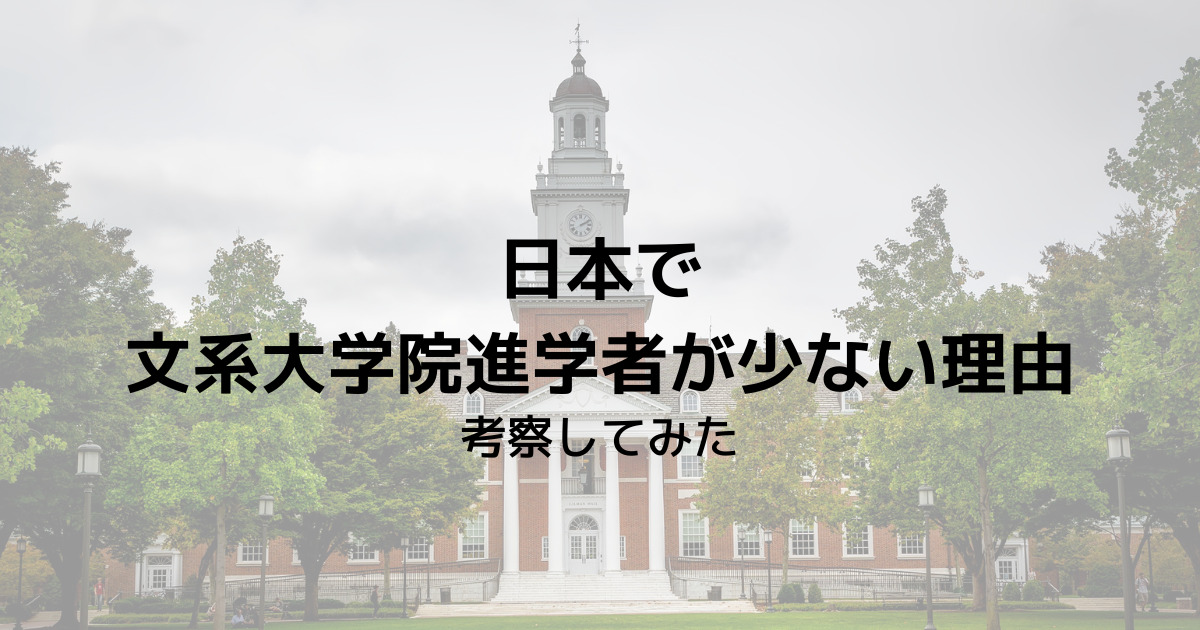
-1.png)
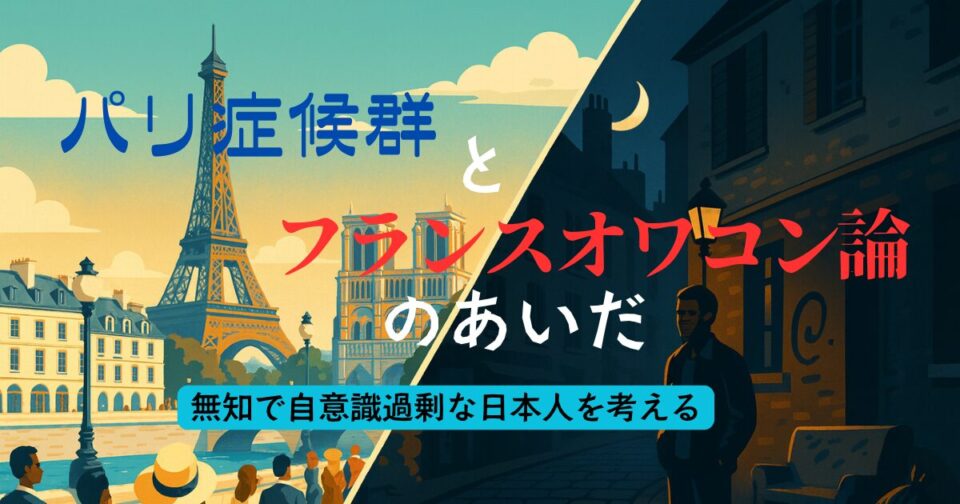

コメント