修士課程の最後に立ちはだかるのが、修士論文。多くの人が通る山場です。
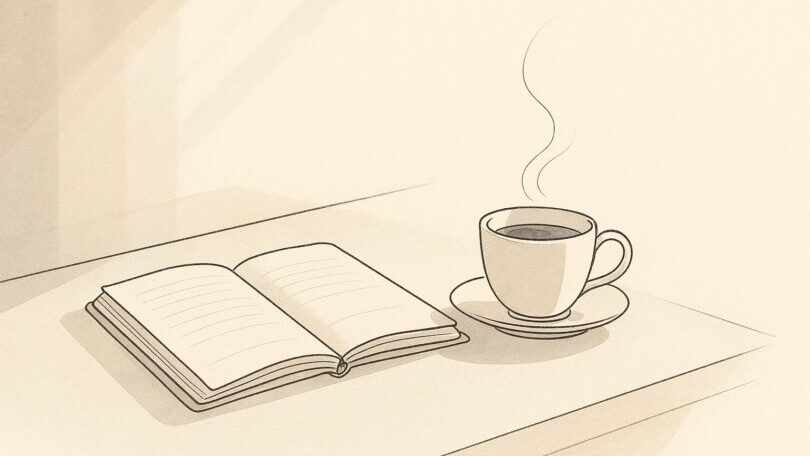
社会人としてのキャリアを経て海外大学院に飛び込んだ私にとって、それはまさに未知の挑戦でした。しかも英語で書き上げなければならないというプレッシャーも加わります。
仕事を離れ、研究という未知の世界に飛び込み、自分でテーマを定め、問いを立て、資料を集め、指導教官と相談しつつ書き上げる。今振り返ると、その過程はまさに「自分自身との対話」そのものでした。
執筆中には、旅先で考えたことや出会った出来事が強く記憶に残っています。卒業後の進路や自分の専門性について深く考えさせられたという点でも、修論は学業以上の意味を持つ経験だったと感じています。
この記事では、私が修士論文を完成させるまでのプロセスを、大学院で学んだ修論の書き方も交えながら振り返ります。
この記事では、私が修士論文を完成させるまでのプロセスを、大学院で学んだ研究の進め方も交えながら振り返ります。社会人留学を考えている方、あるいはこれから(特に海外大学院で)修論に挑む方にとって、少しでもヒントになれば幸いです。
筆者の考える、修論を書く意味
ここでは、筆者なりに「なぜ修論を書くのか」を改めて考えてみたいと思います。
修士課程の集大成として
これは最大にして(人によっては)唯一の理由かもしれませんね。
もちろんプログラムによりますが、修論を書かないと単位がもらえず、修士課程が修了できません。
それまでに学んだことに自分なりの解釈やロジックを加えて新しい価値を作り出す過程は、それまでのある意味受動的な学びを超えて自分の興味を掘り進めていくというプロセス。そこには制限はないものの、自分の名前や指導教官の名前を冠するという点でかなりの責任が生じるともいえます。
これは、組織として動き、責任も組織が負う…という「勤め人」とはまったく異なる責任の概念です。仕事上で修論と似たようなテーマを扱うことがあったとしても、職業的な制限や相手先との関係性によって制限されることが当たり前にあったことを考えると、やっぱり自分で責任を持つということのやりがいは格別です。
絶対的な答えのない実社会に飛び出していく前の準備としてはやっぱりもってこいですし、その実社会でモヤモヤしていた人にとっても、自分の思考を既存の枠から解き放つための一つのトレーニングとして有用かもしれません。
自分が本当に何に興味があるか?を知ることができる
トピックを考える際に実利面(このテーマを選んだことでその後どのようなキャリアに使えるか)も考えましたが、やっぱり自分の興味のあることしか書けないことに思い至りました。
これはブログとちょっと似ているかもしれません。全く興味のないことはどれだけ文章にしようとしてもどうしても内容は浅くなってしまいますし、それ以上に必要以上に探求しようという気も起きないものです。
いくつか考えたテーマで微妙だなと思った内容を軽く分析してみると、やっぱり「今明らかにニーズはありそうだけど、何だか書く気が起きない」とか「これからのキャリアにはきっとプラスになるけれど、どうやったらいいのか皆目見当もつかない」みたいなものばかり。
結局留学前の仕事に近しいトピックを選んだのは、やっぱり「その分野に興味があった」という裏返しでもあるのかなと思いました。ミッドキャリアで大きなキャリアチェンジをしたいのか、それともそれまでのキャリアを発展させたいのか、によっても異なるかもしれませんが、自分の場合は後者だったみたい。
将来に役立つコネクションができる
修論を書く過程で、指導教官や調査先の人々とつながりを作ることができます。
修論の内容やつながり方によっては、その後の職探しの助けになるかもしれません。
これは「何ができるか」よりも「誰を知っているか」が重要な現代社会においてかなり重要なことです。
インターンシップができたり、共同プロジェクトに参画したり…というのは、ただ知っているだけでなく、その人の特性や能力を知っていると証明できることが必須なので、修論はかなり良い状況証拠になり得ます。
また逆に「コネがないから調査対象にリーチできない」という制限を経験することも多いです。
日本では否定的に語られることが多い「コネ」がいかに重要か…修論は現実を知る良い機会といえそうです。
人生の使い方を見直すきっかけになる
働いていると「いつまでに何をする」という短期的な目標やスケジュールに追われることが非常に多くなります。
長期スパンのプロジェクトでも、ある程度工程が決まっていたり、関わる人々の調整が必要だったり、やっぱり細かいタスクの積み重ねになりがち。
一方で、修論を書く時間はかなり性質が異なり、一本の論文を数ヵ月かけて完成させる(しかも授業の単位を取り切っていればその間は修論執筆だけやっていれば良いし、働くか働かないか、どこにいるかすらも自分で選べる)というかなり稀な機会が与えられます。
それまで基本的に途切れなく働いてきた筆者にとっては、この時間はかなり贅沢な反面、身の置き方が分からない、という宙に浮いたような不安な感覚を強く覚えるものでもありました。
ですがどんな状況でも慣れていくもので。人間の適応力ってすごいです。
そうこうしているうちに、「自分の人生の時間をコントロールする感覚」のようなものを長く働くうちに失っていたのかもしれない、ということに気づきました。
これは「自分が本当に何に興味があるのか」にも通じるところですが、「自分が何に価値を感じるか」であったり、「何をしているときが一番幸せを感じるか」のような、ある意味生きる上で当たり前の感覚を取り戻すことができたような気がします。
修論テーマをどう決めたか
修論のテーマは各々の興味のある分野から選ぶことになりますが、ミッドキャリアだと色々と興味の幅が広くて悩むことになったり…。でも指導教官の助けがあって決めることができました。
テーマ・トピックの萌芽
修士課程への進学は、これまでのキャリアを言語化したうえで、より国際的なステージに進むという意識から始まりました。したがって修論のテーマについても、当初から「これまでの経験に関係するもの」にしたいと考えていました。
その意味で、IRPSを選んで良かったのは、アカデミックな色合いが強く、カリキュラムを通じて「修士論文をどう構築していくか」という問いが常に意識されていた点です。実務の世界から初めて本格的なアカデミック領域に足を踏み入れた自分にとって、これは非常に良いガイドになりました。
例えば、第1セメスター開始前の授業では、「修論で研究したいテーマ」と「今後どの授業を通じて学びを深めていくか」を整理する自己分析ポスターの制作が課題として出されました。この課題では、自分の関心のあるトピックについて問いを立て、各セメスターで学びを積み重ねて最終的な答えを導き出すまでの道筋を逆算して示すことが求められました。
このとき筆者は最終的に解きたい問いとして「行政組織の効率化」「地方と国家の協働」「国際機関と自治体の関係」「多層的ガバナンス」に関するものを挙げました。
そのうえでその問いに答えられるだけの知識や経験を身に着けるために描いたルートは、
- 地方公務員としてのバックグラウンドとシンガポールなどで得た知見を出発点とし、
- 第1セメスターでは基礎理論と政策分析の方法を学び、
- 第2セメスターではグローバルガバナンスを中心に研究の基礎となる知識や技術を習得し、
- 第3セメスターで第2セメスターで得たものを深化させ、
- 第4セメスターではそれまでの学びを総動員し、中心的な問いに対する答えを修論としてまとめる
というものでした。
今振り返ると、その後の予定は必ずしもその通りにはならなかったものの、このプロットを描いておいたことが、自分の中の問いを整理し、学期ごとに焦点を定めるうえで大きな支えになりました。
そしてポスターに書き込んだこれらの問いは、最終的に私が取り組むことになったテーマ(行政の専門性を多層的ガバナンスの文脈でどう再定義できるか)の種そのものだったと感じています。
留学生活と迷い
このポスター制作によってその後にどの授業を受講していくかの指針が明確になったため、国際機関について取り扱う授業やPPP(官民連携)など多様な主体の政策形成に関する授業を躊躇なく選択していくことができました。
ただ、実際に修論のテーマを具体的に決める段階になると、思った以上に迷いました。
「ガバナンス」と一口に言っても、国際機関、国家、都市、企業、市民社会…どのレベルを中心に据えるかで研究の方向はまったく変わってきます。さらにトピックも、環境、防災、資源、ジェンダーなど多岐にわたり、どの切り口から入るかを決めるのは容易ではありませんでした。
第2セメスターには、修論執筆の準備としてリサーチメソッドを体系的に学ぶ授業があり、そこで定量・定性の手法を含む具体的な調査設計を学びました。
授業では、修論に近い形式のペーパー執筆や、自分の研究テーマを発表する課題も課されており、この過程で研究の方向性を「都市間比較」という枠組みまで絞り込むことができました。
とはいえ、どの政策領域に焦点を当てるかという点では、なお模索が続きました。
自分がこれまで見てきた行政現場の感覚と、アカデミックな研究としての焦点設定とのあいだには、想像以上に大きなギャップがある…その現実を、ここで改めて実感することになりました。
指導教官とトピック選定
そうこうしているうちに、修論の指導教官(スーパーバイザー)が割り振られ、修論のスケジュールや具体的な内容を詰めていく段階に入りました。指導教官は学科側で指名される形式で、学生が自由に選ぶものではありませんでした(ただ希望があれば選べたみたいです)。
指導教官との面談を重ねるなかで、最終的に「気候変動」に関する都市間比較を行うことに決定しました。
「気候変動」以外にもいくつかトピックの候補はありましたが、最終的にこのテーマを選んだのは、単に国際的にホットな話題だったからではありません。シンガポール駐在時代に、現地の脱炭素政策やサーキュラーエコノミーの取り組みに触れた経験が何となく心に残っており、「気候変動」という候補を聞いたときに直感的にピンときたのです。
当時、偶然触れることになったテーマが、後に自分の研究の方向性を決定づけるとは想像もしていませんでした。
でも今思えば「自分の過去の経験を国際的な文脈の中で再解釈する」という留学そのものの目的と、修論のトピック選定が自然に噛み合った瞬間だったのだと思います。
新しい指導教官と修論の本格開始
修論のトピックが「気候変動」に決まったことを受け、交換留学先のリヨンではサステナビリティ関連の授業を中心に履修しました。ビジネススクールだったこともあり、民間企業の気候変動対応や排出量分析など、ジュネーヴでの授業とはまったく毛色の異なる内容も多く、気候変動に関する知識をより多角的に習得することができました。
そんな中、最初に担当してくれることになっていた指導教官が、なんとサバティカル休暇に入っていることが判明(なんと事前連絡なし)。修論への影響を考慮し、交換留学中ではありましたが新しい指導教官を探すことにしました。
幸い、最初の教官との初期のディスカッションを通じて、ある程度トピックの方向性を固めていたため、指導教官と一時的に連絡が取れなくなっても大きな支障はありませんでしたが、当時はやはり焦りました。
結果として、グローバルガバナンスを専門とする教授に新たに指導教官を引き継いでもらえることになり、一安心。研究の方向性も再確認でき、ようやく修論の土台が整いました。
その後、第3セメスターの終盤からはいよいよ本格的な執筆段階に入り、資料整理や章構成の検討を始めました。
調査・リサーチのプロセス
次に具体的に修論をどのように書いたのか、筆者の例をご紹介します。
問いを立てる
修論を書くにあたっては、まず論文の核となる問い(リサーチ・クエスチョン)を設定する必要があります。
リサーチ・クエスチョンとは、論文で実際に検証できる“問い”のこと。
導き方はいくつかありますが、代表的なのは次の二つです。
- 特定のトピックについて、既存の理論では説明しきれないギャップを見つける。
- 既存研究の問いや仮説を引き継ぎ、別の角度から検証する。
リサーチ・クエスチョンと並んで重要なのが、リサーチ・パズル。
こちらは、クエスチョンを導く前段階にある「説明のつかない現象」や「理論の矛盾」そのものを指します。
一般的には「パズルからクエスチョンへ」という流れが理にかなっていると言われますが、素朴な疑問から背景を探っていくアプローチが向くトピックも多く、必ずしも一律ではありません。
筆者の場合は、単純に「実際の現象に対する素朴な疑問」から出発し、やがて「理論の実証や矛盾を見つけて発展させる」という方向に進んでいきました。少し不器用な例かもしれませんが、その過程こそが学びの醍醐味でもありました。
「純粋に理論を学ぶこと」に特化するか、「現実世界に理論を当てはめて考える」ことにフォーカスするか…その違いは、学業に対する姿勢の差に現れるのかもしれません。筆者の場合、学業に入る前に現実社会で向き合ってきた時間があったことが、研究の進め方や問いの立て方に大きな影響を与えたのは間違いありません。
文献収集とZotero活用
リサーチ・クエスチョンがある程度定まったら、論文構成の検討と文献収集に入ります。
最初は授業で取り上げられた論文を再確認し、そこからGoogle Scholarを使って関連研究を広げていきました。
Google Scholarでは、特定トピックに関する主要文献を検索するだけでなく、引用の多い論文の著者名から派生的に関連論文を探すという方法を多用していました。指導教官からも読むべき文献リストが示され、理論的な部分とケーススタディーの両面から資料を揃えることができました。
その過程で、日本に関するパートでは日本語で書かれた文献が多いことに気づき、指導教官に相談しました。
すると、内容に応じて多言語の文献を参照することが可能であり、むしろ積極的に推奨されていることが分かりました。おかげで、安心して日本語文献を引用することができました。
もちろん、指導教官に内容が伝わらないと執筆上の齟齬が生じるため、内容を適宜翻訳して英語論文内で引用するだけでなく、要点をまとめて指導教官に説明するなど、細かな工夫もしていました。
また、文献管理にはZoteroというソフトウェアを使用していました。オンライン上で論文やレポートを整理できるだけでなく、引用や参考文献リストを自動生成できるため、執筆後半の作業効率が格段に向上しました。
Zoteroの使い方については、修士課程開始直後の図書館オリエンテーションで教わっており、必要なソフトもあらかじめインストール済みだったため、すぐに使い始めることができました。

Zoteroの基本的な使い方や筆者の運用方法については、追って別記事で紹介する予定です。
日本語文献の自動読み込みに苦戦する場面もありましたが、章立てごとにフォルダを分けるなどして整理を工夫しました。修論執筆にあたっては、日本語・英語・フランス語の文献を大量に読む必要がありましたが、既に「読む力」が鍛えられていたこともあり、それほど苦には感じませんでした。
Zoteroのおかげで末尾のビブリオグラフィーも自動生成でき、その分、論文本体の構成や内容の精緻化に集中することができました。
調査方法・ツールの検討
文献と合わせて重要なのがリサーチ対象とその方法。
問題意識自体は経験に基づいているので程度定まっていたものの、どのような手段を使えば科学的に証明することができるのか、具体的にどのように問いに対する自分なりの答えを導くか、そもそも対象の単位(ユニット)をどう設定するのか…というところについては、最後まで悩みました。
リサーチメソッドや統計学についての授業ではサンプリングの方法や統計学的に処理する方法について学びましたが、自分の選んだトピックにそのまま当てはめられるかと言うと、なかなかそこまでは上手くいきません。
さらにテーマを都市間比較に設定したことから、調査対象都市の政策資料や自治体レポートを中心にデータを集めることに。
ですが、特に重要な政策の検討過程についてはそもそも外部に公開されていないことが多く、その内容についての論文もなかなか見つかりません。公開データを取得してみても、都市によってデータの公開状況や書式が大きく異なるため、情報の整合性を取るのに苦労しました。
結局のところ。各自治体の公式資料、国際機関のデータベース、オンライン会議でのインタビューなど取りうる手段を全て検討し、入手可能なデータを既存の理論とどう組み合わせて自分なりの回答を導くかが重要な鍵となりました。
予想外の壁と乗り越え方
執筆作業が進むにつれ、理論で描いていた構造と、実際の都市政策の現場には大きなギャップがあることに気づきました。特に気候変動対策のように領域が広く関係主体も多いテーマでは、都市ごとに優先順位も制度も異なります。そのため「比較」という行為そのものの難しさに直面しました。
結果的に、比較のバランスはやや不均衡になってしまいましたが、指導教官から「記述の薄いパートをシャドウ・ケースとして扱ってはどうか」というアドバイスを受け、何とか全体を整えることができました。このあたりに、質的研究の難しさと限界の一端を感じたように思います。
さらに、英語での論文執筆というハードルも大きく、表現の微妙なニュアンスや引用の整合性を取る作業には予想以上の時間を要しました。特にキーワードの整合性には悩まされ、日常英語では問題ない言葉でも、アカデミックな文脈では意味が異なることが多く、何度も書き直しを重ねました。
非英語圏の研究者が言語面で不利になりやすいという話を以前から耳にしていましたが、実際に体験して初めて「これか…!」と実感することに。同時に、「これを自分が乗り越えないといけないのか」という徒労感のような気持ちに襲われた日もありました。
最終的には、
- 完璧を目指さず、早めに指導教官に助けを求める
- 流れを見失いそうになったら、一度立ち止まって構造を再確認する
- 「博士論文と比べれば軽いんだから大丈夫」と自分に言い聞かせる
という3つを意識したことで、研究を最後までやり遂げることができました。
最終フィードバックでは、言葉選びに関する軽微な指摘がありましたが、それも次の研究への指針として受け止めることにしました。
章立ての決定とスケジュール管理
リサーチの方向性が固まり、必要なデータや文献もそろってくると、いよいよ執筆フェーズに入ります。
ただ、この段階は「資料をそろえる」以上に、構成をどう立てるか・どこまで書き進めるか・どのように修正を繰り返すかといった、思考と作業の両輪が求められるフェーズでした。
章立てと構成の作り方
修論の骨格は、最初に立てたリサーチ・クエスチョンをもとに、
- 背景(問題提起)
- 理論的枠組み
- 方法論
- ケース分析
- 考察と結論
などの項目で肉付けしていきました。
まっさらな状態からだと具体的にどのように書くのか途方に暮れてしまいそうですが、事前にリサーチメソッドの授業で「この論文が社会やこれまでの学問で貢献できることは何か?」という内容を含めた修論の骨子に近いペーパーが課題として課されていたため、自然に章立てを考えることができました。
とはいえ、実際に書き始めてみると、章立ての順序自体はすんなりハマったものの、各章の内容がうまく結びつかなかったり、ボリュームのバランスが崩れたりと、やはり一筋縄ではいきません。
ここまで長い英文を書くのは初めてだったこともあり、どの文献をどこで引用したか分からなくなることも多々ありました。特にZoteroの扱い方をまだ十分に理解していなかった執筆初期は、整理にかなり苦労した記憶があります。
さらに、日本語・英語・フランス語の文献が混在していたことも事態を複雑にしました。
日本語文献を英訳して引用した際に、後から「どの原典だったか」分からなくなることもしばしば。
最終的には、章ごとにファイルを分けて後からつなげる方式を採用し、途中には日本語で簡単なメモや目印を残すなど、「どこまで書いたか」「次に何を書くか」を常に可視化することを意識していました。
スケジュール管理
周囲の学生と違い、インターンなどを並行していなかったこともあり、時間的な余裕は比較的ありました。そのため、修論執筆のスケジュールについては、当初そこまで綿密に計画を立ててはいませんでした。
これまで時間に追われるプロジェクトを数多く担当してきた経験もあり、「せめて学業ではどっしり構えて臨みたい」という思いがどこかにあったのかもしれません。締切を過ぎる可能性は正直ほとんど考えていませんでした。
とはいえ、さすがに完全ノープランというわけにもいかない(指導教官に心配されるのも避けたかった)ので、ざっくりと次のような構想を立て、共有していました。
- 第3セメスターで草稿をまとめ、調査の段取りを決める
- 第4セメスター前半で調査を行う
- 締切直前に全体を仕上げる
お互い大人同士ということもあってか?指導教官から特に細かく干渉されることもなく、比較的自由に進めることができました。トピックがジュネーヴと直接関係のあるテーマではなかったため、旅行しながら執筆していた時期もあるほど。
移動先でもオンライン会議を通じて指導教官と相談できたので、距離のハンデはほとんど感じませんでした。実際に香港滞在中に指導教官と打ち合わせを行ったりしたこともあります。
今は世界のどこからでもジュネーヴの環境に繋がれる…本当に良い時代になったものだと感じた瞬間です。
修論執筆を始める前は、「本当に自分に書き上げられるのかな?」と不安に思ったこともありました。それでも、もともと関心のあるトピックを選んでいたこともあり、執筆で行き詰まる場面は意外にもそれほど多くありませんでした。
適宜方向性を確認しながら、マイペースに筆を進めることができた。
いま振り返ると、あの穏やかな集中の時間が最も充実していたように思います。
書くこと、考えること、触れること
修論執筆は、単に「書く」という作業ではなく、「考える」作業そのものでもありました。
最初は、文章がうまくまとまらなかったり、まとまっているように見えるのにしっくり来なかったりもしましたが、書くうちに自分の理解が整理され、理論と実例の関係が少しずつ明確になっていきました。
冒頭で考えたリサーチ・クエスチョンが出てきた背景(問題意識とか、それまでの経験とか)を改めて深掘りしてみたり、現在自分がいる場所(日本だったり、香港だったり、フランスだったり…)を起点に自分の興味について改めて考えてみたり。論文の上でも(また物理的にも)行きつ戻りつしながら少しずつ言葉を編んでいきました。
日々、新しい何かに触れたり、変わらないものを見たり。
その途上で折に触れて論文に向き合い、自分でも気づいていなかった論理の飛躍や抜けを発見していく。
この繰り返しのプロセスこそが、最終的に修論全体の説得力を支えていたのだと思います。
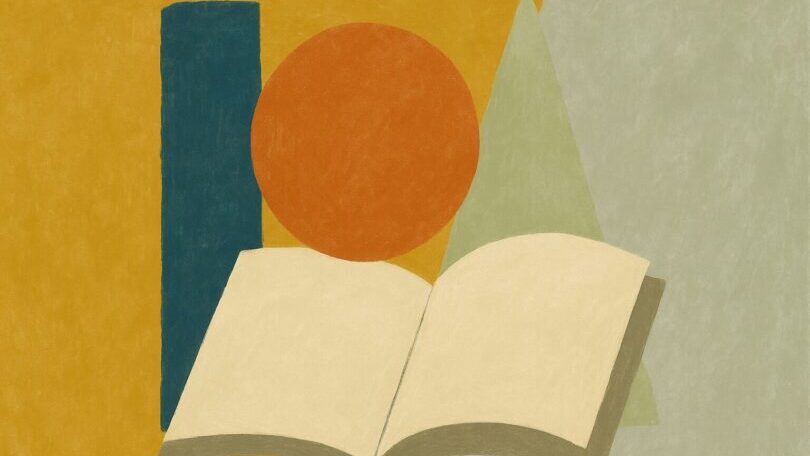
修論執筆を通じて得たもの
修論執筆というのは、単に論文を完成させるための作業ではなく、自分の思考や姿勢を見つめ直す過程そのもの。特に筆者にとってはそれまでのキャリアを一度総決算することに近い意味を持っていたと思います。
ここでは筆者がこのプロセスを通じて得た3つのことを振り返ります。
研究スキルを示す実績
修論の執筆を通じて身についた最も大きな力は、複雑な問題の構造を分析し、過去の研究成果を論理的に整理し、そこから自分なりの答えを導き出す力でした。
自ら問いを立て、関連する理論を整理し、現実のデータや政策と突き合わせながら検証していく。
この一連のプロセスそのものが、研究者としての思考訓練であり、仕事における分析・報告のスキルをさらに精緻なものにしていくのに不可欠であることを改めて感じました。
また、海外大学院での執筆を通じて、「自由」と「責任」についても改めて考えさせられました。
日本の組織で報告書を作成していたときに比べ、時間には余裕があり、書く内容にも制約がない。どこにも忖度しなくてよい。しかしその分、全ての論理構成と結論に対して自ら説明責任を負うことになります。自由度が高い分、別の種類の緊張感が常にありました。
修論は、思った以上に汎用的なトレーニングの場でした。完成した論文は、一つの「成果物」であると同時に、「自分がこのプロセスを遂行できた」という証拠。それは自分の人生にとって非常に意義深いものだと言えるでしょう。
専門性とキャリアの広がり
修論のテーマとして扱った気候変動政策やマルチレベルガバナンスの問題は、筆者のキャリアに新しい視野をもたらしました。
まず、自治体行政という出発点から、国際機関や民間セクター、研究分野など、「公共性の実現」には多様な担い手が存在することを改めて実感しました。
これは授業で得た知見とも重なる部分でしたが、実際に自分の手で「異なる主体がどのように関わるのか」というメカニズムを解き明かしていく過程を経ることで、理解の深さと納得感はまったく違うものになりました。
さらに、論文執筆を通じて、気候変動政策そのものに内在する多様性や複雑さに正面から向き合うことになり、これまで「国内行政の枠」の中で捉えていた政策課題が、国際的な枠組みや他都市の実践と交差する姿を、これまでとは異なる視点から眺められるようになりました。
その過程で、交換留学先のビジネススクールでサステナビリティについて基礎的な知識を身につけたり、課題解決やイノベーションを民間セクターの側から考える機会を得られたことも大きかったです。これらの学びは、気候変動がもたらす影響や対策を考えるうえでの理解を補い、論文の該当パートを構築する際にも非常にプラスになりました。

ビジネススクールの教授には副指導教官もお願いしていたのですが、タイミングが悪く叶わなかったのがちょっと残念でしたね。
このようにマルチレベルガバナンスを「グローバル・ガバナンスの構造」と「気候変動という具体的課題」の両側面から分析できたことは、自分の中に新たな専門性の萌芽をもたらしてくれたように思います。
そして今、卒業後の進路においても、気候変動やガバナンスの領域と接続できる可能性が少しずつ見え始めています。
大学院留学前には想像していなかったキャリアの道筋が見えてきたことに、素直にワクワクしている自分がいます。
すぐにジュネーヴに戻れるわけではないにしても、延長線上にはありそうな感じもしています。
やり遂げた自信
修論はインターネットで提出しました。期限の一週間前くらい。
何度かクリックするだけだったので、特段の感慨もなく、提出後の感情は「無」でした。
それでも時間が経つにつれ、じわじわと「やり遂げたんだな」「これで修士課程が終わったんだな」という実感が湧いてきました。そして同時に「終わっちゃったな」という少しの寂しさも。
特に求められていたわけではありませんが、締め切り前には再びジュネーヴに渡航しており、提出もジュネーヴから行いました(インターネット経由ですが)。正直、そのためだけに戻るのは少しもったいない気もしましたが、やはり特別なタイミングでジュネーヴにいることには意味があったように感じます。
修士論文というと、一つの課題をこなすような印象を持たれがちですが、その背後には、日々の迷いや停滞、言語の壁、構成の試行錯誤が確かにありました。それらを一つひとつ越えて積み上げていった経験は、論文という成果以上の価値をもたらしてくれたと思います。
自信もつきましたし、「これからは悪いことできないな」と思うくらいの達成感もあります(笑)。
この経験を糧に、これからのキャリアの中で少しでも活かせるように頑張っていきたいと思います。
まとめ
この記事では、筆者が修士論文を書いたプロセスをテーマ決めから振り返ってみました。
こうして改めて振り返ると、やはり大学院留学そのものが、それまでのキャリアとどれほど強く結びついていたかを実感します。
結局のところ、大学院入学前から抱えていた疑問や関心が、受講するプログラムや最終的に取り組む修論へと自然に繋がっていったのだと思います。
紆余曲折がありながらも何とかやってこられたのは、やはり職業生活の中で培ってきたスキルや経験があったからかもしれません(確実とは言えませんが)。
修論全般に言えるのは、プログラムが始まる段階である程度ゴール(修論)を見据え、戦略的に授業を選んでいくこと。そして、指導教官との関係を良好に保ち、常にアンテナを高く張っておくこと。このあたりができていれば、途方に暮れることはそう多くないのではないでしょうか。
もちろん、学びを重ねるなかで関心が変化し、リサーチ・クエスチョンが根本から変わることもあるでしょう。
特に若い学生の場合は、そうした変化を経て成長していく人の方が多いかもしれません。
そう考えると、修士論文は単なる最終課題ではなく、やはり「集大成」という言葉が似合います。
この記事が、これから修論に取り組む人や、途中で悩んでいる人にとって、ほんの少しでも参考になれば嬉しく思います。
以上です!
-1.png)
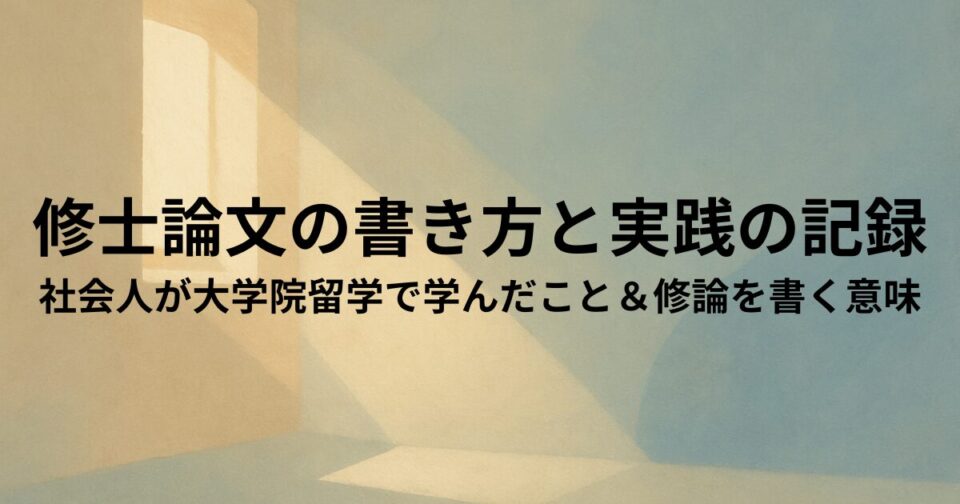
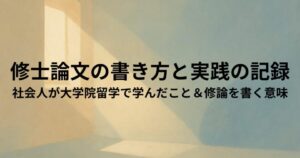
コメント