移動し続けることでチャンスを掴んだり、収入を上げることができる…。
『移動する人はうまくいく』という本は、「移動しないこと」を重視する日本人の安定志向に一石を投じる斬新な視点を示した本です。
この本を読み進めるにつれて、改めて思い出した体験があります。
それは羽田空港が私のとって「移動先」だったかもしれない、ということ。
空港は旅人が行き交う空間ですが、飛行機に乗らなくても手軽に非日常を味わうことができます。
食事や買い物に加え、筆者にとっては仕事に行き詰まったときや思考を整理したいときにも最適な場所でした。
駐在から帰国した後も何度か空港を訪問し、(ブログを書くようになってから目がいくようになった)無料Wi-Fiや電源のような便利さも体験。ますます空港のメリットを感じるようになりました。
この記事では『移動する人はうまくいく』の書評を交えつつ、空港という身近な移動先がどのように役立ったのかを体験談からご紹介します。
また、同じように「大きな移動は難しい」と感じる人のために、身近な移動先の見つけ方や活用法についても考えてみたいと思います。
『移動する人はうまくいく』書評
長倉顕太さんの著書『移動する人はうまくいく』では、「人は移動することで人生が変わる」という考えと著者自身の成功体験が一体的に展開されています。
本の中で紹介されている移動が人生に与える効用は、以下の3点に集約することができます。
- 環境が変われば感情も変わる
→ 普段と違う場所に身を置くことで気分がリフレッシュされ、新しい考えや視点が生まれる。 - 小さな移動の積み重ねが大きな変化をつくる
→ 海外移住のような大きな一歩でなくても、日常に「非日常」を取り入れることが未来につながる。 - 移動は自分をアップデートするきっかけになる
→ 新しい環境に触れることで自分のキャラクターがリセットされ、これまでの枠を超えた行動ができる。
このなかで特に印象的だったのは、「移動とは必ずしも海外に飛び出すような大きなものだけではない」という視点です。普段とは違う場所に身を置くことでリフレッシュしたり、新しい発想が浮かんだりする。そうした小さな移動の積み重ねが、やがて大きな飛躍につながるのだと説かれていました。
一方で指摘されているのは、移動することを選ばない人も多いということ。
確かに頻繁に移動する生活を実現するは容易ではありません。慣れない場所に行ったり、初めてのことを体験するようにすることは心理的・肉体的・時間的なハードルも非常に高く、たとえ国内であってもそのハードルが下がるかと言えばそうでもない…というのが現実です。
さらにそれが日本の社会構造に原因があるという指摘は筆者の考えともオーバーラップする部分があります。
かく言う筆者にも、このような状況については覚えがありました。
それは就職したてのとき。当時の自分も仕事のイライラや閉塞感に悩まされ、「日常的に移動する生活」に憧れながらも、仕事のスケジュールやお金の事など色々な理由を考えて躊躇していたのでした。
発散できるのはたまの週末旅行や年に1度の海外旅行くらいで、移動するライフスタイルなんて夢のまた夢…。
そんなとき、仕事帰りに羽田空港へ立ち寄ることが自分にとっての身近な「移動」だったのです。
今振り返ると、あのときの小さな移動こそが、日常に埋もれそうだった自分の夢をつなぎとめてくれていたのだと思います。そしてその積み重ねが、やがて駐在や海外留学といった大きな移動へとつながっていったのかもしれません。
空港は最高の「移動先」である

空港は、非日常を感じながらリラックスできる貴重な空間。
適度に人の流れがありつつも、独特の静けさが漂っていて、集中と休息の両方を叶えてくれます。
羽田空港では、国際線ターミナル(現・第3ターミナル)がオープンしてからカフェやレストランといった立ち寄りスポットが格段に増え、仕事帰りや休日にふらりと訪れる楽しみが広がりました。
これはまさに、本に書かれていた理想的な「移動先」。
物理的に遠くに行かなくても、心を解放して自由に思考したり、新しい行動パターンを試してみるには非常に適した環境なのです。
飛行機に乗らなくても楽しめる
空港には旅行客が立ち寄るために飲食店を始めとする様々な施設が併設されていますが、日本の空港はかなり充実しているところが多いです。
なかでも羽田空港の充実度は凄く、地方のお土産やおしゃれなスイーツなど空港限定のものがたくさん。飲食店のメニューにもかなり気合が入っており、東京にはない地方の有名店も多数出店。買い物や食事をするだけでもちょっとした旅気分に浸れます。
もはや空港自体が目的地と言っても良いほどなので、飛行機に乗る予定がなくても訪れる価値はありますね。

充実度という意味ではシンガポールのチャンギ国際空港も有名ですね。ローカル色あふれるフードコートを楽しんだり、滝を観たり…仕事で疲れたときにふらっと訪れて楽しんでいました。
気分転換に使える
空港にはいたるところに飛行機の発着案内が設置されていたり、日本的&海外的な装飾が多く見られます。行き交う人々の様子も話される言語も、そのほかの場所とは少し違います。
カフェの喧騒も悪くはないのですが、時々周囲の話し声や内容が耳に入ってくることで集中が途切れてしまうこともありますし、職場や自宅の近くでは知り合いと会う可能性もあります。
その点、空港で聞こえてくる外国語交じりの喧騒や航空会社アナウンスは他ではあまり聞かないものなので、自分が旅目的でない場合であっても、日常から切り離されたような感覚を味わうことができます。
空港は施設がかなり充実しているので、色々な使い方ができるのもメリット。
カフェでがっつり作業をするのも良いですし、疲れたら展望デッキから飛行機や景色を眺めてリフレッシュすることもできます。併設のホテルに滞在してみても面白いです。
関連施設や移動手段も楽しい
空港の魅力は、建物の中だけにとどまりません。
空港へ向かうまでの移動手段や周辺施設も含めて、ひとつの楽しみとして味わうことができます。
羽田空港であれば、モノレールや京急に乗ってアクセスする道のり自体がちょっとしたイベントです。車窓から広がる東京湾や街並みはもちろん、「これからどこかへ行くんだ」という高揚感を自然と引き出してくれます。
特にモノレールはレールが見えにくいため、まるで空を飛んでいるような気分に浸れるのもユニークです。
近年は羽田空港周辺の開発も活発で、車窓から眺める風景が訪れるたびに少しずつ変化しているのも面白いポイントでした。
さらに、空港直結のホテルやショッピング施設が増え、滞在そのものを楽しめるようになったのも魅力です。羽田エアポートガーデンのような新しい施設がオープンし、「行ける場所が広がっていく」感覚がワクワクを倍増させてくれます。
こうした変化の大きさや非日常感こそが、気軽な気分転換として空港を訪れる価値につながっているのだと思います。
そして空港のさらに良いところは、以上のような非日常感がありながらも、落ち着いて思考を整理する環境を確保するのも容易なところ。
筆者にはじっくり思索にふけることができる、お気に入りのお店がありました。
「ロイヤルドミニコ」の思い出
筆者は東京で就職してから仕事帰りにたびたび羽田空港に立ち寄るようになりました。
その羽田空港でもよく行っていたのが、イタリアンレストラン「ロイヤルドミニコ」です。
お店はコロナ禍で閉店し、筆者側も駐在や留学などを経てライフスタイルが大きく変わりましたが、今でも折に触れて思い出します。

静かに過ごす夜にピッタリ
このお店によく通っていた理由はイタリアンが好きだったからというのもありますが、決め手は営業時間が他のレストランと比べて長めだったこと。他のレストランは大抵8時半くらいには閉店するなか、このレストランだけは9時半くらいまでは営業していたのです。
入店はだいたい夜8時頃。窓の外に広がる滑走路を眺めながら閉店時間ギリギリまで過ごすのがお決まりでした。
BGMもいつも大体決まっていて、旅に関するもの。当時はYouTubeを使っていなかったので、それまでの海外旅行でよく聴いていた曲や海外にまつわる曲をまとめてプレイリストにしていました。
そんなプレイリストをかけながら飛行機を見ていると、「いつか海外へ」という気持ちが自然と高まっていくのを感じていました。
お決まりのメニュー
空港のレストランはどこも値段が高めで、就職したての当時の自分にとっては少し贅沢でした。
注文は数あるメニューの中でもちょっとだけ値段が安く、一皿だけで完結する「たらこスパゲッティ」と「ラザニア」。
特に意識していたわけではありませんが、訪問するために交互に頼むのがいつの間にか定番になっていました。
もうひとつのお決まりが、ホットコーヒーをセットにすること。当時ホットコーヒーが飲み放題(オーダー制)だったので、必ずコーヒーをセットにして、何杯もおかわりするのもお決まり(あのときの店員さんには迷惑を掛けました…笑)。
通いすぎたせいか一度だけ空港職員と間違えられて職員用のメニューを渡されたこともありました。
思い返すと微笑ましいエピソードです。
ジャーナリングで整える
コーヒーを楽しみながらやっていたのが、いわゆる「ジャーナリング」。
当時はそんな言葉があったかどうか分かりません。
ノートを持ち込んで、日記を書いたり、感情をぶちまけたり、翌日の仕事の予定を整理したり…。
思いついたことを書き殴りながら思考を整える、非常に有意義な時間でした。
思考を思いっきり解放できたのは、日常と非日常の境界にある空港という場だからこそ。
窓の外に広がる夜の滑走路と飛行機の光景を眺めながら、心のリセットボタンを押す。
ロイヤルドミニコはそんな特別な役割を果たしてくれる場所でした。
少しずつ世界を広げながら、移動を習慣化する
空港に通っていたのは、せいぜい月に一度ほど。
それでも「定期的に通う」というリズムがあったことで、日常と切り離された時間を確保でき、頭や心をリセットすることができました。
『移動する人はうまくいく』のなかで「小さな移動の積み重ねが大きな変化をつくる」と書かれていたのは、まさにこういうことだと思います。大げさな引っ越しや転職でなくても、半歩だけ日常から外れる習慣を持つだけで、自分の思考や感情は少しずつ変わっていきます。
そのうえでやはり重要なのは「繰り返す」こと。
一度の旅行では一時的なリフレッシュに終わってしまいますが、定期的に非日常の環境に身を置くことで、思考が整理され、夢や目標が埋もれずに残っていきます。私自身、羽田空港に通う小さな習慣が駐在や留学という大きな移動へとつながっていったのだと今になって思います。
またその一方で頻繁行きすぎないということも非常に重要だったと言うこともできます。
これが週1回や毎日のように高い頻度で行ってしまうと、非日常感が薄れて思考のスイッチが切り替わらなくなってしまいます。
このように移動を習慣にするのはバランス感覚が重要ですが、移動してみること自体は意外と簡単です。
少し距離のあるカフェに行く、図書館や公園で過ごす、街を歩いてみる──そのどれもが、立派な「移動」になります。
大切なのは、自分の思考のスイッチが切り替わる場所を見つけて、自分なりのやり方で「繰り返す」こと。
その積み重ねが、思考のパターンを変え、人生を少しずつ動かしていくのだと思います。
小さな移動を続けるコツ
ここまで書いてきたように、移動は必ずしも大きなものである必要はありません。
最後に、日常に取り入れやすい「小さな移動」を続けるためのポイントを整理してみます。
半歩だけ生活圏をずらす
遠出をしなくても、普段と違う駅で降りてみる、少し離れたカフェに入ってみる。
そんな半歩の違いでも、気分や発想は大きく変わります。
環境をガラッと変えるのも良いですが、急激な変化はパニックを生むので要注意。
できるところからいきましょう。
例えば、私は「空港に行く」という形でこの半歩を取り入れていました。別に実際に海外に行かなくても非日常の雰囲気に触れるだけでリフレッシュになり、考え方が整理されていきました。
移動を大きなイベントにせず、生活の延長で取り入れる。
このくらいの感覚がちょうど良いのだと思います。
また、そうして「非日常」が「日常」になったら、新たな「非日常」を求めてさらに半歩だけ生活圏をずらすのがおすすめ。そうして生活圏を広げていくと、それまで見えなかった選択肢が見えてくるかもしれません。
定番の場所を持つ
「ここに来れば切り替えられる」という場所を決めておくと、移動が習慣化しやすくなります。
毎回新しい場所を探すのも楽しいですが、定番の場所があることで「迷わず行ける」「安心して過ごせる」という利点があります。
私にとっては羽田空港のロイヤルドミニコがまさにその場所でした。
仕事帰りに立ち寄り、同じメニューを頼み、ノートを広げて思考を整理する。
ルーティンのように繰り返すことで「ここに来れば頭が切り替わる」というスイッチが自然とできていったのです。
定番の場所を持つことは、移動を「特別な非日常」ではなく「適度な非日常」に落とし込むことにつながります。
結果的に移動が続けやすくなり、さらに広範囲に移動する契機になります。
ただし「非日常」が「日常」になってしまうと移動の効果が薄れるので、通いすぎには要注意。適度な緊張感がある場所がおすすめです。
筆者の場合、注文とコーヒーのお代わりのタイミングがちょっとした緊張ポイントでした。
思考を残す習慣をつくる
移動の時間をより意味のあるものにするには、「思考を残す」ことが欠かせません。
ただ景色を眺めてリフレッシュするだけでも十分ですが、そこで生まれた考えや感情を書き留めておくと、後から振り返ったときに気づきが積み重なっていきます。
筆者の場合はノートを持ち歩き、いわゆるジャーナリングをしていました。
日記のようにその日の出来事を書くこともあれば、仕事への不満をぶちまけることもありましたし、将来の夢ややりたいことを思いつくままに書き殴ることもありました。空港の風景がインスピレーションをくれたことも何度もあります。
そのプロセス自体が心の整理になり、結果的に夢やキャリアの方向性を見失わずに済んだのだと思います。
スマホでメモを取るのもいいですが、手書きで残すほうが「頭の中をいったん外に出す」感覚が強く、思考の整理には効果的です。
大切なのは、完璧にまとめようとしないこと。思いついたままを言葉にすることで、移動先での時間が「未来につながる資産」へと変わっていきます。
また、他人に絶対見せないノートに書き殴るのがポイントかもしれませんね。むき出しの感情は後から読み返すと恥ずかしいですが、それが自分の飾らない考えや思考プロセスを知るためのヒントになりますし、読み返して勇気づけられることもあります。
余白を大切にする
移動先では「何をするか」以上に、「何もしない時間」を持つことも大切です。
予定を詰め込みすぎてしまうと、せっかくの非日常がただの慌ただしいスケジュールになり、心を整える余裕がなくなってしまいます。
私自身、空港に行くときも「作業をするぞ」と気合を入れる日もあれば、ただ海を眺めて過ごすだけの日もありました。何かを成し遂げようとしなくても、そうした時間の中で自然と考えが整理され、リフレッシュできることが多かったのです。
移動の効用は「外の世界に出ること」そのものにあります。
あえて余白を残しておくことで、思いがけない発想や気づきが訪れるのもまた移動の魅力です。
そのような余白が、かえって脳をフル回転させるスイッチになることもあります。結果として、自分の望む生き方や本当にやりたいことに気づくきっかけになるかもしれません。
まとめ
長倉顕太さんの『移動する人はうまくいく』を読んで思い出した、羽田空港やロイヤルドミニコで過ごした日々。
それは「大きな移動」ではなくても、自分にとっては夢やキャリアをつなぐ大切な時間でした。
もしかしたら、その先にある「大きな移動」の準備をしていた時間なのかもしれません。
本で語られていたように、移動には環境を変えて思考をリセットし、新しい発想を生み出す力があります。
そして振り返ってみると、その効用は、大きな挑戦でない日常の中の小さな移動でも十分に得られるのだと実感する瞬間が何度もありました。
大切なのは、とりあえず移動してみて、それを習慣として続けること。
まずはやってみる、を前提にしつつ、定番の場所も合わせてストックとして持っておくことで、移動はただの気分転換を超えて、自分をアップデートし、本にも書かれていた選択肢を増やしていくための力になります。
飛行機に乗らなくても、遠くへ行かなくてもいい。
その代わり、新しいことを少しずつ試すことを続けていく。
そのためにはまずは生活圏から半歩外に出てみることが、未来を動かす最初の一歩になるのではないでしょうか。
以上です。
-1.png)
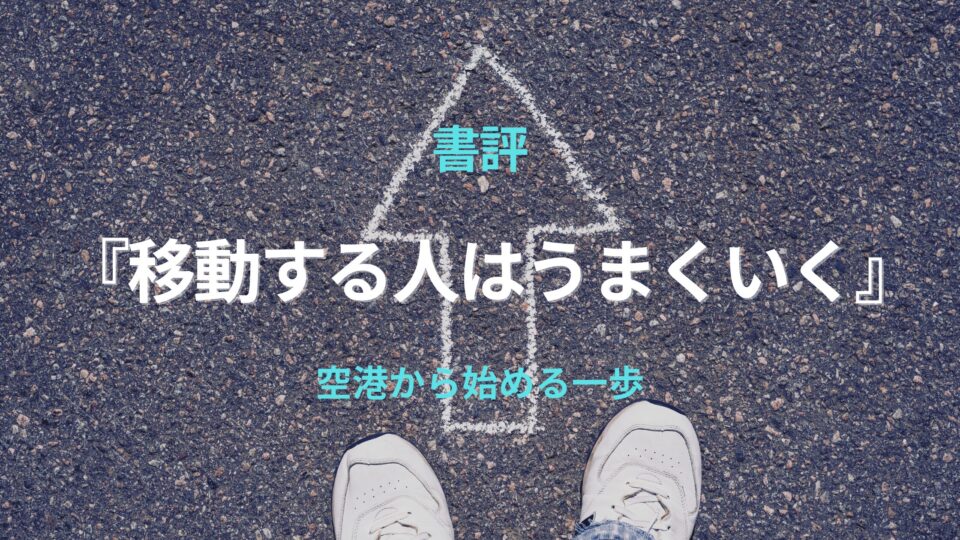
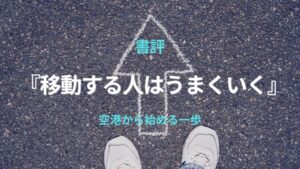
コメント